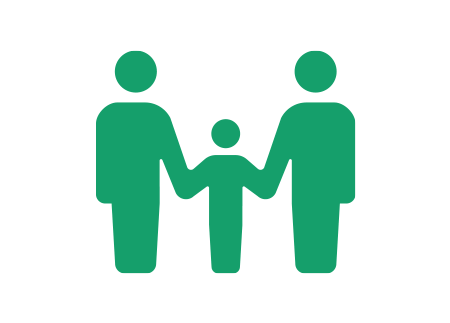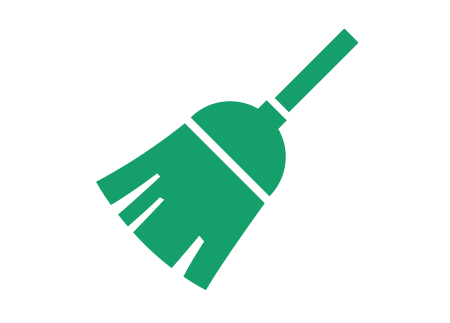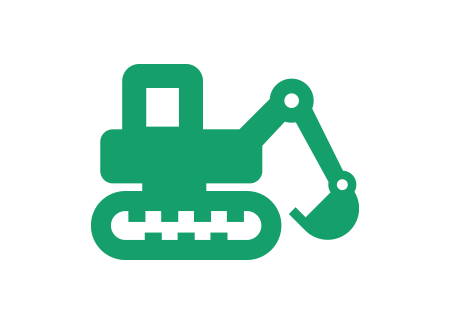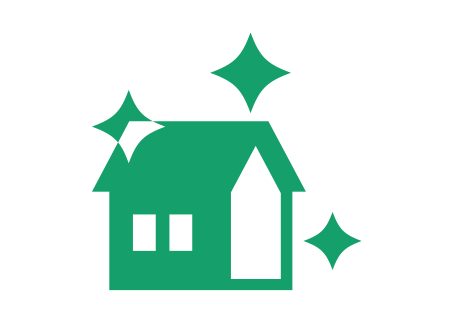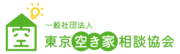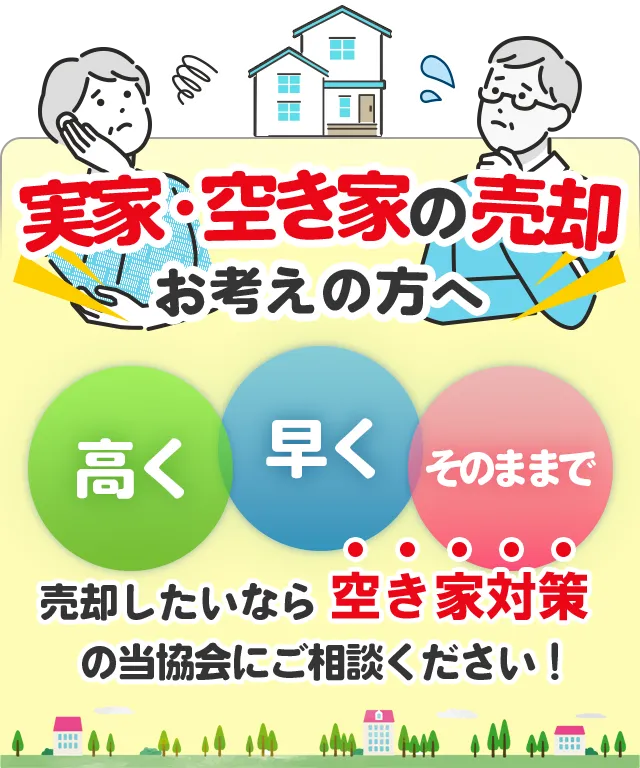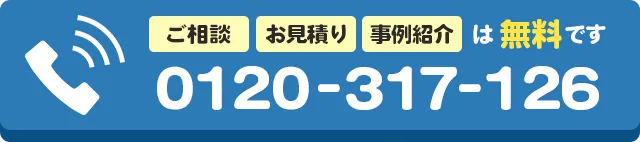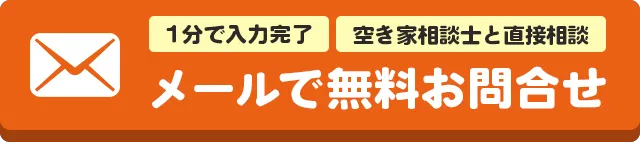皆様は「不動産」ならぬ「負動産」を抱えてはいませんか?
悩みの種である「売れない土地と早くお得におさらばするため、現実的な手段」について解説します。
精神的・経済的負担からの早期解放の一助にお役立てください。
こんな人におすすめ
- 「負動産」を抱えている可能性のある方
- 「土地を手放したいのにいつまでたっても買い手がつかず、売れ残りつづける」という悩みをお持ちの方
なぜ売れない?土地が売れない理由いろいろ
土地が売れないからには理由があり、主にこんな理由が考えられます。
こうした土地は買い手にとってニーズがなく、待てど暮らせど一向に売れない傾向にあります。
- そもそも高すぎる
- 利便性が悪い
- 土地が広すぎる
- 境界が未確定
- 再建築できない
- 災害リスクが高い
- 地中に埋設物がある
- 土壌汚染の疑いがある
そもそも高すぎる
土地の売り出し価格が高すぎる場合、なかなか買い手が現れない傾向です。
周辺に似たような条件で安く売り出されている土地があれば、買い手としては安い方を選ぶからです。
ヘタしたら一生売れない・・・利便性が悪い
最重視される立地条件。
売りに出している土地が駅や市街地から遠いなど、利便性の悪い場所にある場合買い手がつかないことがあります。
土地が広すぎる
土地の面積が広すぎて買い手のニーズと合わないがために、いつまでも売れ残っている可能性があります。
土地が必要以上に広い→買い手にとって購入価格が高くなりすぎる→毎年の固定資産税も増えてしまうからです。
境界未確定問題のせい
見落とされがちなリスクのひとつでもある境界未確定問題。
隣人とのトラブル回避の観点から、隣接する土地との境界未確定の土地は買い手がつきにくくなります。
最悪この境界問題をめぐって訴訟に発展する場合すらあります。
- 「ここからここまでがこの人の土地ですよ」がはっきりしていないがために、買い手としてはのちにこの境界をめぐるトラブルが起こりやすくなるからです。
- 買い手からすれば、土地の購入後に境界確認や再設定をする必要が生じ、そのプロセスで多大な費用と時間がかかります。
- 訴訟に発展するという件も、隣地所有者との交渉が難航すれば境界をめぐる法的な争いになるのは実際あり得る話です。
- やりたくてやるわけでもないのに避けられない訴訟沙汰になろうものなら、精神的負担や裁判費用が大きくなることが多いです。
- 境界が未確定の土地を売りたい場合
- 土地家屋調査士に依頼し、隣人の立ち合いのもと、まず境界を確定させなければなりません。
ただ何事もタダでは済まず、確定測量費用は約30万~80万と高額です。
また、もし隣人の協力が得られず立ち合いを断られた場合境界を確定できず、そのために結局売れ残ることもあります。
売ろうとしている土地に境界杭や境界標が設置されているか、正確な位置の確認とともに隣地所有者が協力的かどうかも確認の上、協力を得られない場合にはのちのトラブルの可能性も考慮しておかなければいけません。
- 「境界確認書」とは
- 隣接する土地の持ち主同士が「境界はここでしたよね」とお互いの土地の境界を確認し合い、その位置を正式に同意したことを記録する書類。
土地の隣人にこれに署名しトラブル回避してもらうことにより、のちの紛争を回避する効果的な対策ができます。
再建築不可
- 再建築不可とは
- ズバリ家を新築できない土地のことです。
この建築基準法で定められた「接道義務」(幅4m以上の道路に土地が2m以上接していなければならないこと)を果たさない土地やその土地に建つ建物のことを再建築不可物件と定めており、この接道義務をクリアしないかぎり新たに建物を建てられないことになっています。
- 接道義務とは
- 建築基準法に接道義務・・・とは何やらカタい響きですが、住宅用語のひとつです。
文字通り再建築できない理由の多くは、建築基準法の道路と2m以上接していない場合が該当します。
建築基準法の道路に2m以上接していない場合
原則として家を建てられないことになります。
路地や農道、通路、林道、里道などの非道路(建築基準法の道路に該当しない道)のみにしか接していない場合も原則、再建築不可です。
そもそも最初からこの接道義務をクリアしておけば再建築不可物件は現れないのですが、なぜこうした土地ができたのでしょうか。
それは現在の建築基準法が定められる以前からそこに存在していたからです。
関連記事
建築基準法ができた歴史
建築基準法ができたのは1950年(昭和25年)のこと。
また都市計画法ができたのは1968年(昭和43年)でした。
それ以前に建てられた家や都市計画区域などに指定される以前に建てられた家のなかには、この接道義務をクリアしていない物件が存在します。
旧市街地内の土地を買う際に多いのが、敷地に接している道路の幅が4mに満たないケースで、
世の中にはこうした建築基準法の接道義務を満たしていない土地が案外たくさんあります。
再建築できない土地を売りたい場合、この接道義務を果たし、再建築できる土地にする必要があります。
- セットバック(道路の中心線から敷地の縁を2m後退させなければならない)をする
- 隣地を取得する
- 敷地設定する
- 43条但し書き申請
- 50戸連たん制度
再建築できる土地にするためには手間やコストがかかる上、
利便性の悪いエリアにある土地の場合コストと手間暇をかけて再建築できる土地にしたところでなかなか買い手がつかず、結局いつまでも売れ残ることもあります。
災害リスクが高い
誰しもせっかく高いお金を出して買った家や、土地が災害リスクに晒されるのは、避けたいのが常です。
ひとたび自然災害が起これば、ひとたまりもないことは、台風による集中豪雨や土砂災害などの被害報道などでもよく分かります。
交通アクセスがいい、治安がいいなど、家を建てる土地選びでの優先項目のなかでも「災害に強いこと」を最優先で考える人は多いかと思います。
このことからも、家を建てても災害時に大きなダメージを受けるリスクが高い場所は、どうしても買い手から敬遠されます。
地中に埋設物あり
- 埋設物とは
- 浄化槽や井戸、コンクリート片など古い建物の残骸や廃材などのこと。
これらが地面に埋まっている土地の場合、建物を建てるときの基礎工事を阻む原因になるため、買い手がつきにくくなります。
売主の責任を問われることになり、撤去費用や賠償金などを請求されるおそれがあります。
よって、埋設物がある土地を売りたい場合は、土地所有者がコストをかけて撤去工事をしなければなりません。
撤去工事費用は1㎡あたり約1万円~2万円程度かかります(埋設物の種類により異なる)。
埋まっている区画面積が広いほど、その分撤去費用が高くなります。
土壌汚染の疑いあり
土地の価値と切っても切り離せない関係のひとつがこれです。
土壌汚染が懸念される土地は買い手がつきにくく、周辺の土地に比べ売れにくくなるのが常です。
- 土壌汚染がよく懸念される土地の例
- 主に過去に工場やガソリンスタンド、クリーニング店などの用途で使われていた土地の場合、土壌汚染が疑われます。
「現状では健康被害ももたらしていないし、とくに問題がないから」といって目をつぶってしまえば、将来悪影響が出るリスクがあります。
実際の健康被害が不明瞭でもリスク自体がある以上買い手に敬遠され、心理的に購入を避けたいと考える人が多いということです。
逆にいえばどんな土地であれ、土壌汚染が存在する可能性はあるといえます。
いつまでも空地状態のまま土地が動かなくなる土壌汚染です。
目に見えないからこそ、土壌汚染は対策を取らなければなりません。
早く手放したほうがいい理由
土地が売れないからといっていつまでも放置していると、相応のリスクを背負うことになります。
管理費や手間、固定資産税、ヘタしたら周辺からの損害賠償すら請求されることもあり、土地の所有者ならどれも心当たりがあるかと思います。
管理費がかかる
たとえ使っていない土地であれ、土地の管理は避けられません。
管理しないと見た目も悪くなって状況が悪化するため、さらに売れにくくなります。
せっかく購入希望者が現れて見学に来ても、草ぼうぼうで荒れ放題、ゴミも散らばり放題といった状態では印象ガタ落ち、購入意欲も下がるものです。
売却成功のためには、見学者に好印象をもってもらうために土地の定期メンテが必須となります。
固定資産税もついて回る
その上でついて回るのが「固定資産税」で、土地を持っているかぎり毎年これを払いつづけなければいけなくなります。
- 売れないことを理由に家が建っている土地を放置している
- ゆくゆく行政から特定空き家や管理不全空き家として見なされる
- 住宅用地の特例から外される
- 最悪固定資産税がMAX6倍になる
あな恐ろしや、放置問題・・・ですがこれらはどれも現実的な問題です。
- 管理不全空き家とは
- そのまま放置すると特定空き家に指定されるおそれのある建物のこと
- 特定空き家とは
- そのまま放置すると近隣に危険を及ぼす可能性がある建物のこと
- 住宅用地の特例とは
- 住宅用地における固定資産税の特例措置のこと
ですが、以前あった家を取り壊して土地だけにする場合も住宅用地の特例から外れるため、翌年以降は固定資産税(MAX6倍)も払いつづける羽目になるため、要くわばらです。
周辺に賠償責任を問われる
これもたまったものではありません。
リスクがリスクを呼ぶ事態になります。放置でろくなことはありません。
- 土地のメンテを怠ったがために売れにくくなる
- 周辺住民から損害賠償を請求されるリスク
- 土地の管理を怠り、放置すると、雑草や木が伸び放題になり、害虫などが発生、老朽化により建物が崩れ落ちる可能性
- 空き家が倒壊して隣家を直撃し、ヘタをすると死亡事故(億単位での賠償金を求められる可能性)
- ゴミの不法投棄問題や放火犯に狙われやすくなる
いざ、手放すために
売れない土地をいつまでも所有していると、それだけで固定資産税が掛かり続けたり、管理の費用や手間がかかるなどリスクも抱えます。
買い手がどうしても見つからない場合、相続放棄、国に引き渡す、買い取り業者、寄付や譲渡など売る以外の選択肢を検討しましょう。
手段① 相続放棄でおさらば
いっそのこと相続放棄してもらうことで手放す方法です。
どうしても売れない、活用が難しい土地を子どもや孫など次世代に遺したくない場合、自分が亡くなったあとに相続してもらうことも検討しましょう。
- 相続放棄とは
- プラスの財産も借金などの負の財産も相続自体を拒否する意思表示のこと
売れない土地を手放すこともできますが、以下のようなこともあります。
- 預貯金や株などプラスの財産も放棄しなければならない
- いったん相続すると相続放棄が認められなくなる
- 相続放棄すると原則取り消しできない
- 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に手続きする必要がある
- 預貯金や株などプラスの財産も放棄しなければならない
- 相続放棄すると原則取り消しできない
- 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に手続きをする必要がある
「相続放棄したから終わり」ではない
残念ながらいらない土地だけを相続放棄することはできません。
相続人ではなくなるので、借金などのマイナスの財産を相続しなくて済む代わりに、不動産、現金や預貯金などプラスの財産もすべて相続できないことになります。
また、相続放棄した=管理責任から逃れられるわけではありません。
管理責任からは逃れられないため留意してください。
相続放棄をした後も続くデメリット
次の相続人による管理が始まるまで、もしくは相続財産清算人が選ばれるまでは、相続放棄後も自分の所有物としての管理義務を負うことになります。
- 相続財産清算管理人とは
- 相続人の代わりに相続財産の管理をする人のこと
裁判所により、弁護士や司法書士などの専門家から選任されることが多くあります。
- 土地の相続放棄後、管理責任から完全に解放されたい場合
- 手続きを踏んで予納金を納め、相続財産清算人の選定申し込みをする必要があります。
- 予納金について
- 一般的な相場の目安としては20万~100万円程度です。
というのも、亡くなった人の財産によっても異なり、管轄の家庭裁判所によっても違います。
予納金の金額を家庭裁判所に聞く場合
申立人が支払う必要がある予納金ですが、相続財産管理人の選任申立てをする前に、管轄の家庭裁判所に予納金の金額を訊くことはできます。
とはいっても、正確な金額は教えてくれないでしょう。
あくまでも一般的な目安としての額を教えるに留まります。
なぜなら、申立て前に正確な金額を伝えてしまうと、予納金の額面が違った場合に「聞いていた金額と違うじゃないか!」というトラブルになるからです。
家庭裁判所に予納金の額面を訊く際は、キッチリ正確な額面ではなくあくまでも目安として捉えておきましょう。
予納金について
そもそも予納金を納めてもらうのは、相続財産の管理費用に充てるためです。
したがって、相続財産から管理費用が支払えるのであれば、予納金を請求する理由がありません。
亡くなった人の相続財産に預貯金などが潤沢にある場合、予納金が不要になるケースもあります。
予納金の検討時には、現金や預貯金など相続財産の流動資産が重要になります。
亡くなった人の相続財産に預貯金などがあり、相続財産からの支払いを希望するなら申立書に予納金について記載しておきましょう。
手段② 国に引き渡すなら相続土地国庫帰属制度
- 相続土地国庫帰属制度とは
- 相続などで土地の所有権を得た相続人が土地を手放し、国に返せる制度
所定の手続きをすることで、最終的に国に引き取ってもらうこともできます。
とはいっても、この制度で土地を国へ返すのは費用もかかり、実際難易度が高いといえます。
相続放棄とは違い、相続土地国庫帰属制度は売れない土地のみを手放せますが、この制度を使える土地の要件が細かく定められているのです。
- ガケ地
- 建物がある土地
- 境界が定かではない土地
- 隣人トラブルのある土地
- +この上で、売買などで得た土地も適用外
また、制度の利用に際し、管理費用として10年分相当の負担金を支払う必要があり、土地の種類により費用が違います。
土地の種類が宅地や田畑、その他雑種地などは面積にかかわらず負担金は20万円、森林の場合は面積に応じて負担金が算出されます。(法務省:相続土地国庫帰属制度の負担金 参照)
手段③ 買い取り業者に買い取ってもらう
居住目的で土地を探している人にはニーズがなくても、買い取り業者であれば活路を見出すことができ、買い取ってくれる確率も高まります。
買い取り業者が直接買主になるため、売り手が査定価格に納得さえできれば契約ができる分、手放すスピードを早くできます。
追って解説する売却以外の手放す手段(寄付や譲渡など)もありますが、手放せる可能性が低く、また費用がかさむ場合もあります。
売れない土地をいつまでも持ち続けて、税金などの負担がかさんでしまう前に、複数の買い取り業者に見積もりを取り、買い取り価格・信頼度ともに一番納得できる業者に依頼しましょう。
手段④ 寄付・譲渡編
無償でもいいから土地を手放したい場合、寄付や譲渡で手放す手もあります。
売れない土地を寄付・譲渡する対象として、個人や法人、市町村などの選択肢があります。
個人に受け渡す
個人に譲渡することで売れない土地を手放す方法です。
手放したい土地を欲しがるような人はそんなにいないと考えるのが現実的ですが、隣地の所有者であれば有効活用してくれる可能性があり、土地を受け渡す話を持ち出す価値はあるといえます。
土地を隣地の所有者に受け渡せば、自分の敷地が広くなり駐車場もしくはその他の用途で使うことができます。
取るところから取る税金の話になりますが、売れない土地でも個人に譲渡する場合、贈与と見なされて贈与税がかかる可能性があるからです。(※国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」参照)
あとで「贈与税だと・・・!?」「そんなの聞いてないぞ」とトラブルにならないよう、土地の個人への無償譲渡は税金が発生することを事前に説明しておく必要があるでしょう。
法人に寄付する
法人に寄付をして土地を手放すこともひとつの選択肢です。
近隣の法人であれば社宅や資材置き場にして活用するなど、土地を有効活用できる企業があるかもしれません。
こちらも付近に活用してもらえそうな企業があれば、話を持ちかける価値はあるでしょう。
- みなし譲渡所得税とは
- 資産を無償または定額で譲渡した場合、時価で売却したとみなして課税する税制(関連する税目は所得税と消費税)
なお、先方が一般企業ではなく公益法人の場合、所得税を非課税にする特例があるため活用を推奨します。
国税庁「公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし」
市町村に寄付する
公共性の高い土地であれば、市町村に寄付する手もあります。
市町村により寄付の有無が違っており、ここで結論を言うことはできないため、こればかりは市町村の窓口(まちづくり課など)で直接話を聞くしかありません。
また、一般的に市町村が寄付を受け付けてくれるような土地は少ない傾向であり、必ずしも引き取ってくれるわけではありません。
「不動産」が「負動産」と化す前に
場合により、いつまでも持っていると、不動産はネガティブな意味での「負動産」になりかねません。
恐ろしいことであり、だから悩みの種になる・・・しかし、いま悩み、今後どうしたらいいか迷っているということは決して悪いばかりではなく、言い換えれば最良の決断をするための考慮期間でもあるわけです。
「不動産」が「負動産」と化す前に当記事で述べた内容をいま一度吟味し、ご自身で最良の判断を下すための手立てとしてご活用ください。