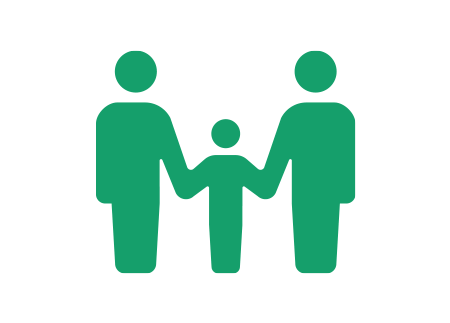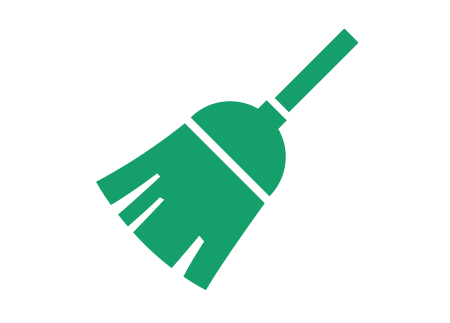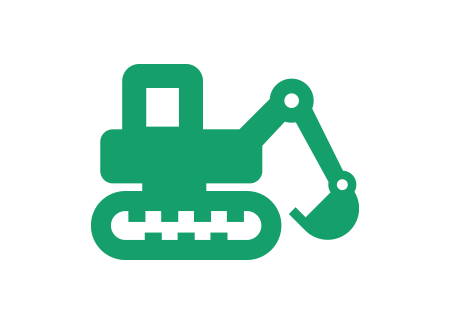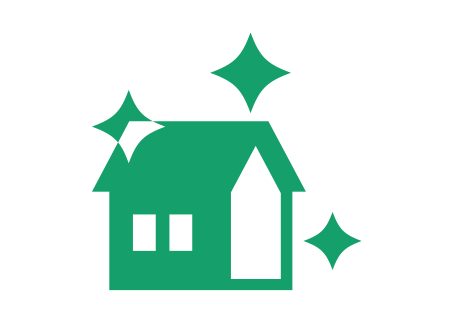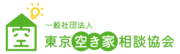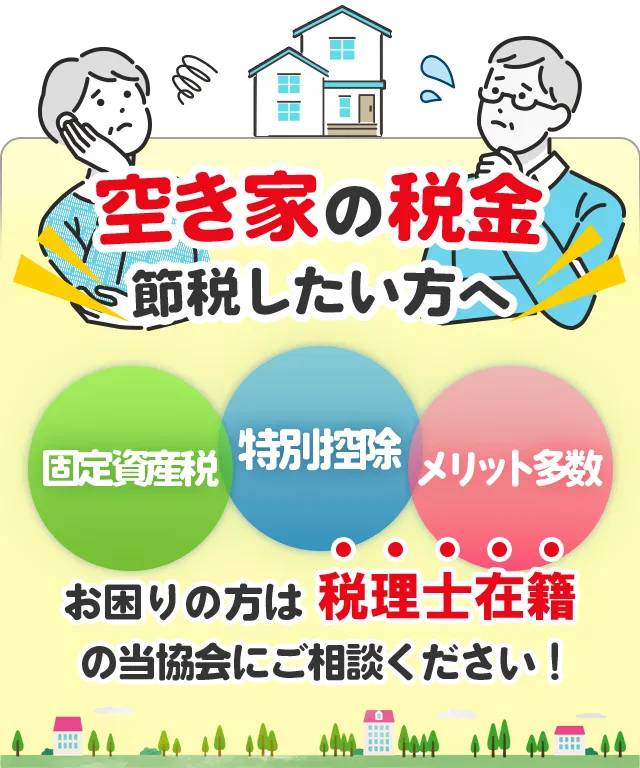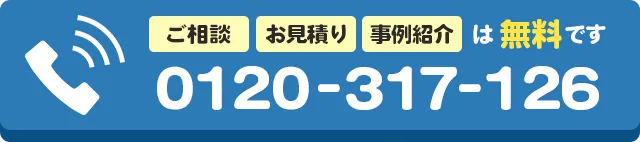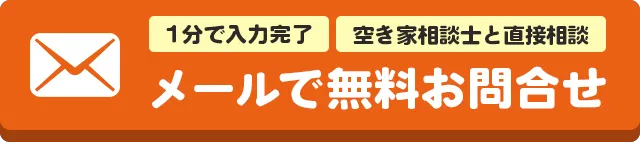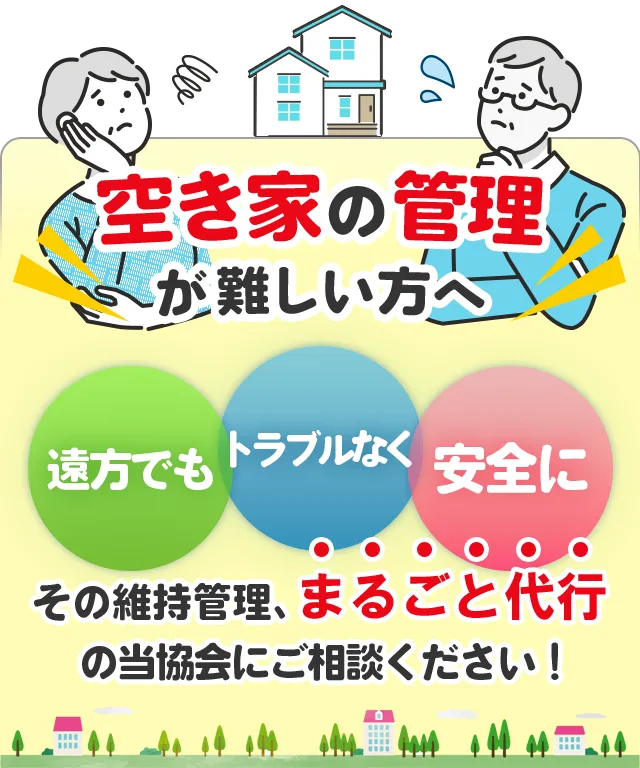遠方にある実家を相続することになった。
実家に一人暮らししていた親が亡くなった。
本記事では空き家に活用できる補助金・助成金制度をご紹介します。
なかには空き家の解体費用に50万円以上補助される制度が使える可能性もあります。
すこしでも空き所有のデメリットを減らすためにも、ご一読ください。
- 国が実施している空き家の補助金
- 物件オーナーへの支援制度
- 補助金・助成金の条件・上限
国が実施している空き家の補助金・助成金

政府では空き家の活用や再生を推進するための「空き家再生等推進事業」を進めており、自治体に財政支援を行なっております。
そのほかの事業も含めて、以下でご紹介します。
- 空き家再生等推進事業
- 「空き家の活用・利用」に焦点を当て、その支援を行なう事業です。
- 例えば空き家の改修や活用、空き家を地域交流の拠点や新しいビジネスの場として活用することを促進します。
- 補助率:市町村への間接補助(国が費用の1/3補助)
- 空き家対策総合支援事業
- 「不良住宅・空き家の除却・活用」両方を支援し、地域全体の居住環境を総合的に整備・改善する事業です。
- 例えば倒壊の危険があるなどの不良な空き家を積極的に撤去することも含め、地域全体の環境改善を図ります。
- 補助率:市町村への間接補助(国が費用の1/3補助)
- 住宅・建築物安全ストック形成事業
- 災害に強いまちづくりのために、「耐震改修・バリアフリー改修」などを支援する事業です。
- 例えば住宅・建築物の耐震化に対する支援事業や、耐震のための改修工事や建て替え工事に関して支援を行ないます。
- 補助率:工事費用の1/3(上限あり)
- 長期優良住宅
- 長期にわたり住み続けられる家づくりを推進している事業です。
- 具体的には、劣化対策・耐震性・省エネルギー性などの性能基準を満たしている住宅を約束することで、国が認定する制度です。
- 補助率:工事費用の1/3(上限あり)
- フラット35地域連携型及び地方移住支援型
- 地方公共団体の財政支援と連携し、フラット35金利の引き下げを行なう制度です。
- 子育て支援やUIJターン支援も含んでおり、フラット35金利の引き下げをすることで地域への移住を促進させます。
- 金利引き下げ幅:地方公共団体により異なる
- 住宅地区改良事業
- 不良住宅密集地区での住環境整備を行なう制度です。
- 具体的には、不良住宅の買取・除却や、改良住宅の建設を行ない、より良い住宅地をつくるための公共施設や地区を整える制度です。
- 補助率:市町村への間接補助
各自治体によって制度の名称や上限は異なりますが、基本となる制度は以上です。
【2025年10月改正】国が実施する「住宅セーフティネット法」
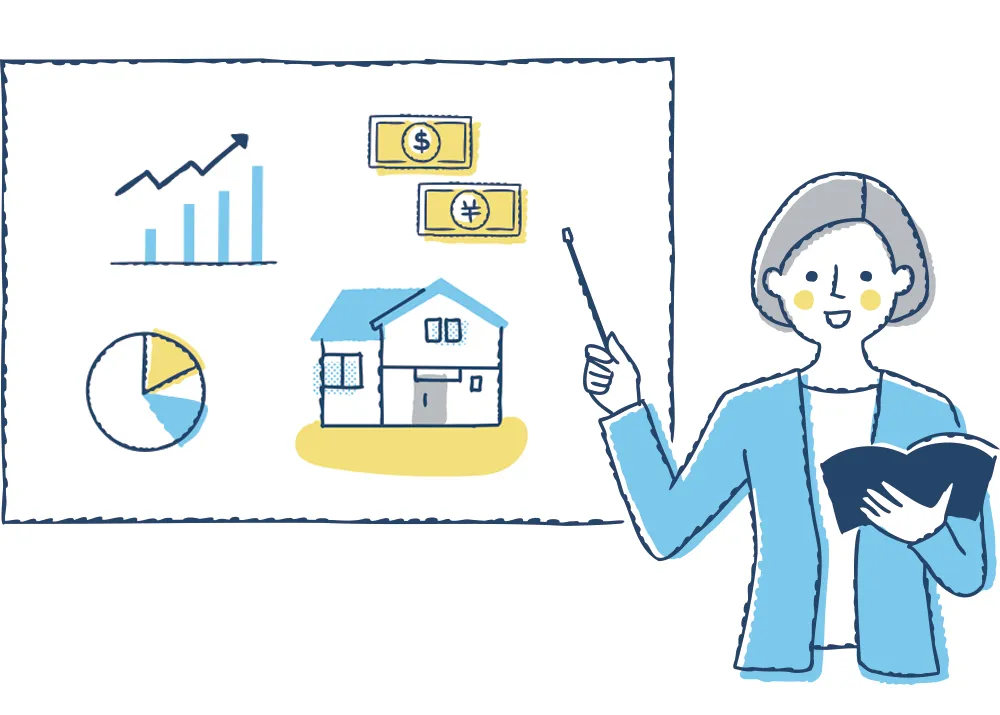
低額所得者や高齢者、被災者、障害者、子育て世帯、外国人などは、家賃滞納などのリスクから入居が断られるケースがあります。
国は、「住宅セーフティネット法」に基づき、賃貸住宅を要配慮者の入居を拒まない住宅(セーフティネット住宅)に登録した場合、一定の要件で物件オーナーに対して改修費や家賃の支援を実施しています。
2025年10月の法改正後の内容でご紹介します。
住宅セーフティーネット法の目的
「住まいの不安を感じやすい場面」を先回りで防ぎ、入居と管理の両面で安心できる環境を整えることが目的です。
支援方法
- どのように家賃を支援するのか
- 入居者から徴収する家賃を下げる代わりに、減額分を物件オーナーに直接支援するというものです。
- 戸建ての空き家を集合住宅へ間取り変更する際にも利用可能です。
2025年10月には法改正した
この法律は、2025年10月に法改正し、主に「大家の不安軽減」と「入居者の安全・安心の強化」が変更されました。
主な変更点として、具体的に以下の3つの指針で成り立っています。
- 大家が賃貸住宅を提供しやすく、要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備
- 居住支援法人等が入居中サポートを行なう賃貸住宅の供給促進
- 住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化
この3つの指針を、それぞれ詳しく解説いたします。
大家も借りにくい人も安心できる住まいの仕組みづくり
高齢者の孤独死や認知症による近隣トラブル、火災リスクや連帯保証人の立てにくさといった点をフォローし、民間賃貸の大家が安心して要配慮者へ貸し出すための法整備を定めたものです。
上記のリスクをフォローするための4つの内容で構成されています。
大家も借りにくい人もフォローできる住まいづくりのポイント
- 終身建物賃貸借の利用促進
- 居住支援法人による残置物処理
- 家賃債務保証業者の認定と保険適用
- 生活保護利用者向け:家賃の代理納付の原則化
終身建物賃貸借の利用促進
- 一般的な賃貸契約では…
- もし入居者が亡くなると、賃貸契約も相続人に引き継がれることになります。
- 相続人が判明するまでの家賃未払いや、単身者の孤独死によって”賃借権相続先不明で空室状態”が発生してしまうリスクがある。
上記のリスクを解消するための方法のひとつが、入居者が死亡すると自動的に契約が終了する、一代限りの契約「終身建物賃貸借」です。
今回の法改正により、今まで「終身建物賃貸借」契約の手続きに手間がかかっていたところ、簡素化され、手続きがしやすくなることで、中高年以上の単身者入居のハードルが下がることが期待されています。
居住支援法人による残置物処理
残置物撤去をしたいけど、相続人がみつからないため、すぐに対処できない。
大家であっても、入居者の所有物を同意なく廃棄できないし、原状回復費もかさんでしまいます。
高齢の単身者の場合、残置物撤去も大家にとってのハードルです。
今回の法改正では、居住支援法人が残置物処理業務を行なう要項が追加されており、居住支援法人が各都道府県から残置物処理の認可を受け、入居者からの委任に基づいて万が一の際に残置物処理を行なうことが想定されています。
家賃債務保証業者の認定と保険適用
国土交通省が行なった「令和3年度 家賃債務保証業者の登録制度に関する実態調査」によると、民間賃貸の約80%が家賃債務保証会社(家賃保証)を利用しています。
そんな時、法改正によって以下の仕組みによってリスクが低減されます。
- 要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者を、国土交通大臣が「認定保証業者」として認定。
- 認定された保証業者は、独立行政法人住宅金融支援機構の家賃債務保証保険を利用することができるようになる。
- これによって、要配慮者への保証リスクが低減される仕組み。
この仕組みによって、「要配慮者は審査が通りやすくなる」「大家は家賃の未払いを回避できる」、「家賃債務保証会社は債務不履行による損益が出ても保険で補填できる」といった、各者にとってもメリットばかりなのです。
生活保護利用者向け:家賃の代理納付の原則化
これまでは、生活保護を利用する人は住宅扶助(家賃の支給)は、利用者の口座に振り込まれていました。
- しかし、口座振込の場合は生活費など別の出費に充ててしまい、大家への支払いに周らず家賃滞納となってしまうこともありました。
上記を避けるためにも、今回の法改正によって、住宅扶助を利用者が大家へ支払うのではなく、自治体の生活保護課をはじめとする生活保護実施機関が賃貸人へ直接支払う方法が原則化されました。
居住支援法人と連携した「居住サポート住宅」の新設
「空き家予備軍」という言葉もあるように、単身高齢者は増加傾向にあります。
しかし、持ち家率は低下し、要配慮者の賃貸住宅ニーズは高まりをみせています。
要配慮者のニーズに対して、大家が安心して貸せる物件を目指したのが、「居住サポート住宅」です。
- 居住サポート住宅とは
- 居住支援法人等が入居中サポートを行なう賃貸住宅です。
- 具体的には、ICTなどによる安否確認サービスや、居住支援法人の訪問等による見守り、居住支援法人等と大家との連携、福祉サービスへの連携が付帯した住宅のことです。
2025年12月12日を期日に、2025年度の居住サポート住宅の民間事業者が行なわれております。
- 一戸につき補助対象工事費用の3分の1(上限50万円/戸)の補助が受けられます。
また、居住サポート住宅に入居する要配慮者については、認定家賃債務保証業者が家賃債務保証を引き受けることとなっています。
国土交通省と厚生労働省のクロスオーバーがより強化される
2017年(平成29年)に国土交通省の管轄でセーフティーネット法が制定されました。
要配慮者の入居の難しさに重きが置かれていたことから、条文には「住宅確保要配慮者」と名付けられています。
制度が発展するにつれ、要配慮者の入居前の支援だけでなく入居後の生活支援まで安定して受けられるようになりました。

国土交通省が管轄する”住宅施策”と厚生労働省の管轄である”福祉施策”が連携したうえで、地域の居住支援体制の強化をすることが、今回の改正で規定されることとなりました。
国土交通省・厚生労働省の共同基本方針策定
これまで住宅=国土交通省、福祉=厚生労働省と線引きされていました。
今回の法改正では、住宅施策と福祉施策の整合性をとるため、両省が共同で基本方針を策定しました。
このことにより、住宅提供だけでなく、福祉サービスも一体となった支援体制の強化を期待できます。
市区町村での居住支援協議会設置が努力義務に
- 居住支援協議会とは
- 地方公共団体、不動産関係者、居住支援団体などが連携し、「住宅確保要配慮者」(低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯など)が民間賃貸住宅にスムーズに入居できるよう支援する組織です。
法改正により、居住支援協議会の設置が努力義務となり、要配慮者と民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対する支援や、制度の周知を行なうことを目的に自治体単位で設置されました。
- 要配慮者に物件情報を提供したり、入居に向けた支援を行なう。
- 大家には入居希望者や居住支援法人へのマッチング支援、制度の活用支援が行なわれています。
2025年3月に政府が発表した資料では、居住支援法人が増加していることが記載されています。
改正住宅セーフティネット法(平成29年)施行後、全国で800を超える居住支援法人が指定され、地域の居住支援の担い手は着実に増加している。
引用:国土交通省
居住支援協議会が設置されることにより、自治体内での住まいに関する支援の強化が期待されます。
セーフティーネット住宅に登録するための条件や注意事項は次項で解説します。
セーフティーネット住宅に登録するための条件
登録は各市町村で行ないます。
登録できる集合住宅の基本的な条件は以下の3つです。
- 床面積が25㎡以上
- 耐震性があること
- 台所・便所・浴室・洗面等の設備があること
シェアハウスの場合は別途条件があります。
上記の条件は自治体によって変更可能なため、25㎡未満の住宅でも支援を受けられる可能性は充分にあります。
また、登録できるセーフティネット住宅には以下の2種類です。
- 登録住宅
- 専用住宅
- 登録住宅とは
- 住宅確保が難しい要配慮者も受け入れるが、一般の入居希望者も受け入れる住宅のこと。
- 専用住宅とは
- 要配慮者のみが入居できる住宅のこと。
物件オーナーが直接経済的な支援を受けられるのは、専用住宅のみです。
専用住宅であっても、低額所得者や高齢者、被災者、障害者、子育て世帯、外国人などのあらゆる要配慮者を受け入れる必要はありません。
高齢者のみ入居可能にしたり、低額所得者と障害者のみが入居可能な専用住宅にすることなども可能です。
物件オーナーへの支援内容
専用住宅にすることで受けられる、空き家活用に対する国からの経済的支援には以下の2つがあります。
- 改修費への補助
- 家賃低廉化への補助
改修費への補助
改修費の補助は、以下の工事にかかる費用が補助されます。
- 耐震改修
- 間取り変更
- シェアハウスへの改修
- バリアフリー改修
- 居住のために最低限必要と認められた工事
- 居住支援協議会等が必要と認める工事
- これらに係る調査設計計画の作成
これらについて国と地方それぞれに、一戸あたり最大50万円、合計100万円補助が受けられます。
補助率は国と地方合わせて2/3です。
家賃低廉化への補助
これは、要配慮者のうち、月収15.8万円以下の低額所得者の入居を認める際に受けられる補助金です。
低額所得者の負担を軽減するために、家賃を市場相場よりも減額した場合、その減額分が補助されます。
補助率は100%で、限度額は一戸あたり1ヵ月4万円(国・自治体が各2万円)です。
- 補助金の使用例
- 家賃が8万円のところ、低額所得者からの家賃は3万円にしたら、減額分の5万円が毎月オーナーに補助されることになります。
- 補助期間は最長で10年です。
専用住宅に登録する際の注意点

一戸あたりで補助が受けられる専用住宅に登録することには、大きなメリットがあります。
しかし物件オーナーが受けられる補助のうち、「改修費への補助」を受ける場合には以下の制約が生まれます。
- 家賃の上限が認められる
- 除却にかかる費用に上限がある
家賃の上限が定められる
国による改修費の直接補助を受けた場合には、10年間以上、公営住宅相当の家賃水準以下にする必要があります。
- 上限家賃の算出方法
- 67,500円 × 50/65 × 市町村立地係数
国土交通省の市町村立地係数の一覧表をもとにした算出例は以下の通りです。
- 北海道札幌市:上限家賃51,900円
- 東京都新宿区:上限家賃67,400円
- 愛知県名古屋市:上限家賃57,100円
- 大阪府大阪市:上限家賃64,900円
- 沖縄県那覇市:上限家賃51,900円
【活用編】自治体が実施している空き家の補助金
各自治体では、空き家の活用に関して補助金が出ています。
以下はいくつかの制度をピックアップしてご紹介します。
栃木県足利市:空き家バンク改修費補助制度
- 空き家バンクを活用して取得した空き家を改修場合に、市外から移住する取得者に改修費を補助するもの。
- 国の活用制度:空き家対策総合支援事業
- 補助率1/2。補助金限度額50万円。
富山県射水市:いずみ住まい等応援事業補助金
- 市内に所在する1年以上使用されていない空き家を、住居や住居兼店舗として利活用するために購入し、5年以上定住する意思のある方に対し、ポイント数に応じて補助するもの。
- 補助限度額200万円。しかし建物の取得費用が下回る場合は、当該費用が上限。
群馬県伊勢崎市:移住者支援空き家改修補助事業
- 市外からの移住者が、本市に10年以上定住するために空き家を改修する場合に、その改修工事費用を補助するもの。
- 国の活用制度:空き家対策総合支援事業
- 補助率2/3。補助限度額200万円。
静岡県小山町:小山町空き家活用・流動化促進助成金
- 自ら居住するため空き家を取得して行う改修工事や、空き家を完全に解体して新たに住宅を建設する者に対し費用を補助するもの。。
- 補助率1/2。補助限度額は改修30万円、解体50万円。子育て世帯または若者夫婦世帯の場合、それぞれ10万円を加算。
大阪府泉佐野市:泉佐野市空家住宅利活用耐震改修補助事業
- 空家住宅の利活用を促進するため、耐震性のない木造住宅を耐震改修し、地域の活性化に資する施設を10年以上運営する場合に、改修工事に要する費用の一部を補助する制度。
- 国の活用制度:空き家対策総合支援事業
- 一戸あたり120万円上限。所得月額214,000円未満の方は140万円上限。
和歌山県有田市:有田市空き家家財道具処分支援補助金
- 空き家バンクに登録した空き家の、家財道具等を処分する費用に対して補助する制度。
- 補助率10/10。補助限度額10万円。
広島県江田島市:空き家相続登記等補助
- 空き家の所有者または相続人が司法書士等と契約し、相続登記等費用の一部を補助するもの。
- 相続登記後、居住または空き家バンクに登録する必要がある。
- 国の活用制度:空き家対策総合支援事業
- 補助率1/2。補助限度額5万円。
福岡県中間市:中古住宅リフォーム補助金事業
- 市外に居住する子育て世帯や若年世帯が、移住・定住を目的に空き家バンクに登録されている中古住宅を購入または賃借し、市内事業者により40万円以上のリフォーム工事を行なった場合のリフォーム費用に対する助成制度。
- 国の活用制度:社会資本整備総合交付金
- 補助率1/1。補助限度額30万円。
福岡県中間市:中古住宅リフォーム補助金事業
- 市外に居住する子育て世帯や若年世帯が、移住・定住を目的に空き家バンクに登録されている中古住宅を購入または賃借し、市内事業者により40万円以上のリフォーム工事を行なった場合のリフォーム費用に対する助成制度。
- 国の活用制度:社会資本整備総合交付金
- 補助率1/1。補助限度額30万円。
沖縄県恩納村:中古住宅リフォーム補助金事業
- 定住や一時的に村外に居住していた方のUターンを支援するために、空き家に居住するための目的でリフォーム工事を行う際の費用を助成する制度。
- 改修工事および残置物撤去にかかる費用の1/2。補助限度額200万円。
【解体編】自治体が実施している空き家の補助金
次に、空き家の除却(解体)に関する補助金をご紹介します。
以下はいくつかの制度をピックアップしてご紹介します。
北海道旭川市:旭川市不良空き家住宅等除却費補助事業
- 老朽化した空家等または特定空家等の除却に対し、除却工事費の一部を助成するもの。
- 国の活用制度:空き家対策総合支援事業
- 補助率1/3。補助限度額30万円。
山形県大蔵村:空き家除却費支援事業
- 老朽化し、危険な状態にある空き家等を除却する工事を行なう当該空き家の所有者などに対して、補助金を交付するもの。
- 国の活用制度:社会資本整備総合交付金
- 補助率4/5。補助限度額100万円。
長野県長野市:老朽危険空き家解体事業補助金
- 老朽危険空き家の所有者が行なう空き家(特定空家等など)の解体費用を補助するもの。
- 国の活用制度:空き家対策総合支援事業補助金
- 補助率1/2。補助限度額100万円。(低所得者加算最大20万円あり)
福島県会津美里町:空家等除却推進事業
- 市町村内にある空き家所有者が行なう空き家の除去への補助事業に対して補助するもの。
- 国の活用制度:空き家対策総合支援事業
- 補助率1/2。補助限度額50万円。
東京都荒川区:老朽空家除却助成事業
- 空き家所有者等が行なう老朽空き家の除却工事にかかる費用の一部を助成するもの。
- 国の活用制度:社会資本整備総合交付金(地域住宅計画に基づく事業)
- 補助率2/3。補助限度額100万円。
- ただし、区が不良住宅と判定した場合、解体する建物の延べ面積1㎡あたり26,000円とし、延べ面積500㎡までを上限額とする。
愛知県安城市:安城市空き家除却費補助金制度
- 老朽化した危険な空き家の所有者が当該空き家を除却する際にかかる経費を補助するもの。
- 国の活用制度:空き家再生等推進事業
- 補助率4/5。補助限度額20万円。
滋賀県草津市:草津市不良空き家除却促進補助金
- 倒壊等により周囲の環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家の除却を促進し、近隣住民が安心安全で快適に過ごせるような空き家の除却工事を実施する所有者等に対して補助するもの。
- 国の活用制度:空き家再生等推進事業
- 補助率4/5。補助限度額50万円。
兵庫県小野市:まちなか広場整備事業
- 地域住民が有効活用できるまちなかの広場を確保するために、自治会等が主体となって空き家等の解体撤去、土地の整備を行なう場合、整備に要した経費の一部を助成するもの。
- 補助率1/2(特定空家等に指定された空き家を解体撤去する整備事業の場合は、補助率4/5。
山口県岩国市:老朽危険空き家除却促進事業
- 空き家の所有者等が行なう空き家(事前に老朽危険空き家として認定を受けたものに限る)の除却に補助するもの。
- 国の活用制度:社会資本整備総合交付金
- 補助率1/3。補助限度額30万円。
鹿児島県姶良市:危険空家の解体撤去工事に係る補助金
- 市内の適正な管理が図られていないために周辺に悪影響をおよぼすおそれのある危険な空き家の解体工事を行なう者に対し、解体工事にかかる費用を補助するもの。
- 国の活用制度:社会資本整備総合交付金
- 補助率1/2。補助限度額50万円。
沖縄県那覇市:那覇市不良住宅等除却費補助金
- 空家等の所有者等が行なう「不良住宅」または「特定空家等」の除去費用に対して補助するもの。
- 国の活用制度:空き家対策総合支援事業
- 補助率4/5。補助限度額40万円。
それ以外にも、当協会の拠点である23区でも空き家の解体に助成金活用が可能です。
関連記事
以上のように、除却やリフォームなど、制度を活用できる場面は異なります。
助成限度額も異なりますが、平均相場はいくらなのでしょうか?
全国の補助金・助成金額の相場
空き家の除却(解体)でいうと、全国の補助金・助成金額は20万円~100万円が平均相場です。
知っていて損はない助成制度

本記事でご紹介したように、ただでさえコストや手間がかかる空き家の支援制度は知っていて損はありません。
もし、「自分の持っている家が空き家になりそう」「空き家にかかるコストや手間をカットしたい」とお考えでしたら、ご連絡ください。
私たち東京空き家相談協会は、100社以上の専門家と連携しており、お困りごとやニーズに合わせて、一括見積後の厳選から業者へのお断り連絡まですべて代行します。
- 現在、無料の空き家現地調査を実施中!
- 空き家のご状況や相談者様のご意向に合わせて、最短即日~3営業日以内に適切な解決策や厳選した事業者をご紹介しています。