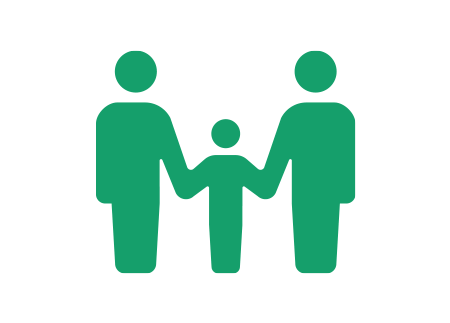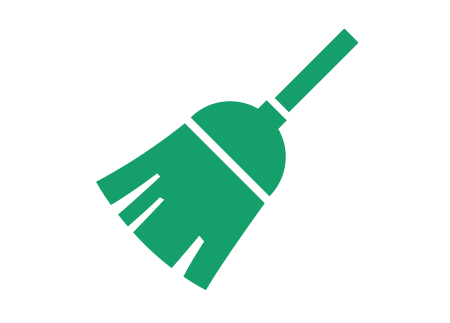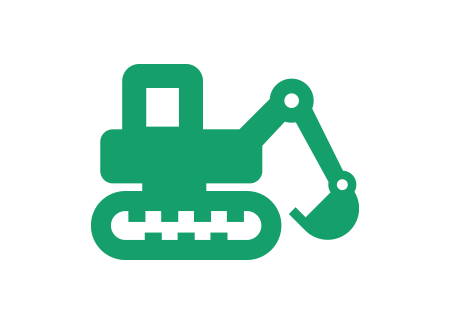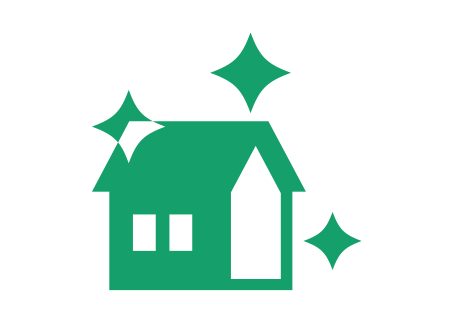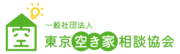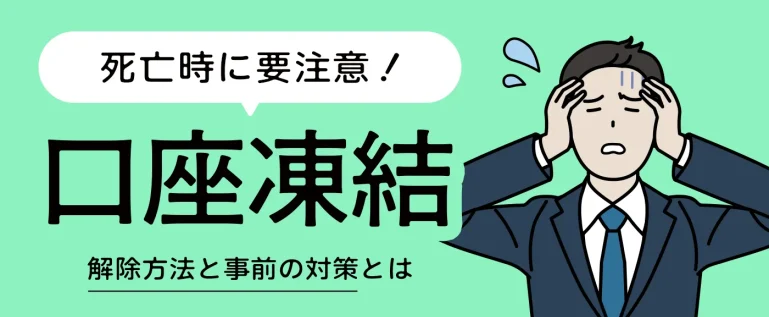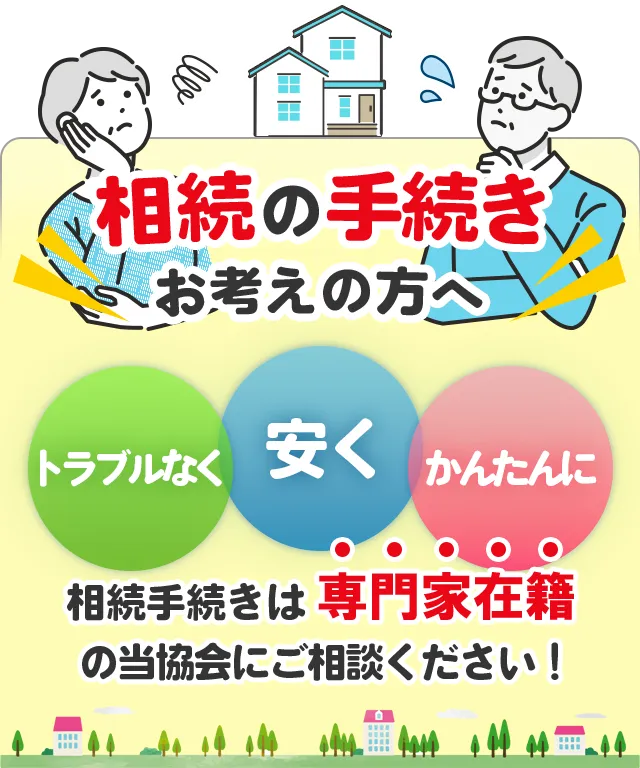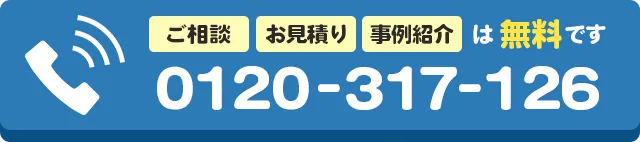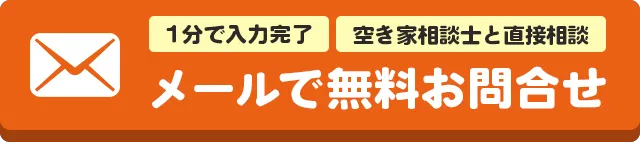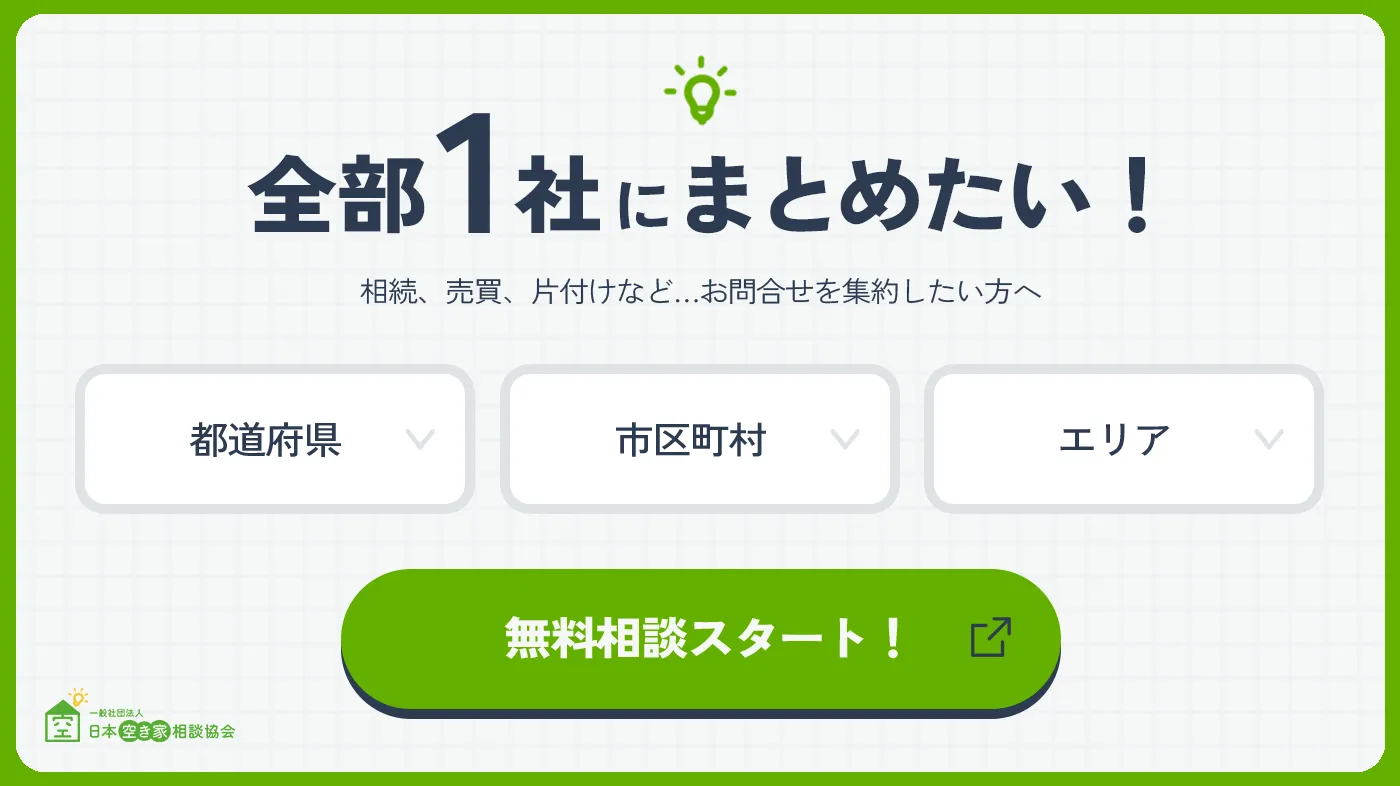こんな人におすすめ
- 相続や口座凍結について不安に思っている
- お金に対して未然に対策しておきたい
口座凍結とは?
口座凍結とは一定の条件に該当したとき、お金の引き出しなどの取引が停止されることです。
「取引の停止」であるため、お金を下ろすだけではなく、口座引き落としや振込も一切できなくなります。
自動的に解約されるわけではありませんが、元通り使えるようにするためには面倒でも手続きをしなければなりません。
口座を凍結させる意思はないが、亡くなった親の口座から現金を引き出そうと思い立ったが、口座名義人の死亡を伝えたことで思いがけず口座が凍結してしまった
口座が凍結すると、その口座から入出金が一切できなくなります。
未払いの状態が続くと…
光熱費であればガスや電気が停止したり、水道費であれば水道が停止するだけでなく、クレカの支払いであれば債権回収会社が動くことになります。
口座名義人が死亡した旨を速やかに伝え、こうした支払いに対応せざるを得ないということです。
凍結される条件
一般的に口座が凍結される条件としては以下が考えられます。
- 名義人が死亡した
- 名義人が認知症であると認められた
- 口座が不正取引に使われた
- 債務整理の対象になる
凍結のタイミング~役所は銀行に知らせない
口座名義人が亡くなると、銀行などの金融機関に口座名義人が死亡したことが伝わったタイミングで口座が凍結されます。
とはいえ死亡後に即、勝手に凍結されるわけではありません。
- 病院での死亡診断書交付とともに、病院から銀行へ死亡連絡をする
- 死亡届を提出した役所が、銀行へ死亡連絡する
通常、死亡した名義人の家族などの相続人が銀行などへ知らせることにより、銀行はその事実を知った時点で該当の口座をすべて凍結します。
また、A銀行に死亡連絡をしたから同時にB銀行やC銀行の口座も凍結するというわけでもありません。
死亡が分かるその他のタイミング
死亡が分かるその他のタイミングとして、以下が挙げられます。
- 地域新聞の訃報欄に掲載されたことで金融機関から家族へ連絡がいく
- 銀行関係者が葬儀を見かけたことで知る
- 残高証明書の取得申請から名義人が亡くなった事実を知る
- 回覧が回ってくる
名義人死亡後の口座凍結について、「家族の何の了解もなく何で銀行は勝手に凍結するんだよ!」というギモンを持つ方も少なくありません。
では、凍結される理由はなんなのでしょうか?
凍結される理由
口座を凍結される理由は、相続人の権利を守るためです。
名義人の預貯金は亡くなった瞬間から遺産になるため、相続人の権利を守らなければならないからです。
相続の確定前に、遺族のうちの一人に勝手に預金を引き出されました。
ありえません!いまは遺産相続トラブルに発展しています。
このように、トラブルに発展する可能性を未然に防いでいるのです。
また、以下のように、認知症の疑いがある場合にも口座が凍結されます。
- 家族などから連絡を受けた場合
- 口座名義人とのやり取りから認知症と思われる状態と判断された場合
名義人の資産が意図しない形で失われることを防ぐためでもあります。
このほか債務整理の対象になる場合、カードローンなど銀行からの借り入れがあることで債務整理になり、口座が凍結されます。こちらは債務整理が決定された時点で凍結されます。
凍結前後の出金やいかに?
では口座が凍結される前後の出金についてはどうなのでしょうか?
「凍結される前に口座からお金を引き出しておこう」と考えた際に気をつけなければいけない点があります。
とりわけ死亡による口座凍結の際、起こりがちな注意点は以下の通りです。
- 共同相続人との間でトラブルになりかねない
- 相続放棄ができなくなる
それぞれを次項で解説します。
凍結前に出金する影響は2つ

凍結前に出金する影響は以下の2つです。
- 共同相続人とのトラブル
- 相続放棄ができなくなる場合がある
共同相続人とのトラブル
まず共同相続人とのトラブルについて。
被相続人の口座は遺産分割協議の対象になるため、それを勝手に下ろして使うことは本来許されません。先にも解説した「不要なトラブルを避けるため」という、口座凍結の目的に該当してしまいます。
相続放棄ができなくなる場合がある
遺産から引き出したお金を自分のために使ってしまうと、相続を単純承認したとみなされるためです。
そのことによって、借金などの負の財産があることが発覚した場合、相続放棄をしようにもできなくなってしまうため気をつけましょう。
関連コラム
凍結されたらもはやお金を引き出せないのか?
では口座凍結されたあとは絶対にお金を引き出すことはできないのでしょうか?
本来であれば口座凍結された理由ごとに所定の手続きをし、凍結を解除することが必要です。
しかし死亡による口座凍結の場合には、仮払い制度の活用で一部お金を引き出すことができます。
仮払いの手段3選
-
- 家庭裁判所に申し立てる
- 相続人全員の同意書を提出する
- 相続人のうち一人が申請する
このうち、相続人一人が申請する場合には上限があり、以下の計算式で算出されます。(上限は150万円)
- 申請する場合の算出方法
- 相続開始時の預貯金残高 × 1/3 × 仮払いを望む相続人の法定相続分
また、仮払い制度を活用する場合でも相応の手間暇がかかります。
仮払いを受けた分は遺産分割時に相続分から差し引かれるため、使い道は紙面に書くなどして残しておくことを推奨します。
口座凍結の放置はリスクもある
口座凍結の放置によって挙げられるリスクは以下です。
- 「闇バイト」など不正利用として疑われる
- 振込詐欺救済法の手続きにより口座内のお金が消される
- 口座凍結に伴い、新しい口座が開設できなくなる
そもそも不正利用として疑われるのは、近年急増している、いわゆる「闇バイト」をはじめとする特殊詐欺事件で、犯行グループから悪用されたような場合です。
騙し取られたお金がいつ誰を介し、どこにいき、今どこの誰の手元にあるのか。
お金の流れや所在を分からなくさせるよう、詐欺集団は収益の隠ぺいのためにも犯行とは無関係の人たちを騙しては利用したり、仕入れた口座情報を悪用しています。
騙しの手口は手を変え品を変え、もはやキリがないイタチごっこになっています。
口座の凍結を放置しておくと、振込詐欺救済法の手続きによりその口座内に入れておいたお金が消されてしまう可能性が出てきます。
解除は大変。手続きいろいろ
結論からいいますと凍結は簡単でも解除は大変です。
口座凍結の解除には所定の手続きが必要であり、以下は死亡と認知症による場合です。
口座名義人が死亡の場合、口座名義人の思慕による口座凍結の場合、相続人が遺産をどう相続するかを決めることができます。
口座名義人が死亡の場合
口座名義人の死亡による口座凍結の場合、相続人が遺産をどう相続するかを決めることがスタートです。
手続きに必要な書類は銀行や相続方法により違いますが、一般的な金融機関の場合は次の通りです。
遺言書、遺産分割協議なしの共同相続
- 戸籍謄本:口座名義人の出生~死亡までの連続した戸籍謄本、法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本
- 印鑑証明書:法定相続人全員分(通帳・証書、キャッシュカード、貸金庫のカギなども含む)
遺言書がある場合
- 遺言書:遺産の分割割合や継承者が明確に記載された遺言書の原本
- 戸籍謄本:口座名義人の出生~死亡までの連続した戸籍謄本、法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本
- 家庭裁判所の検認済証明書:家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認したことを証明する書類(公正証書遺言もしくは自筆証書遺言保管制度を利用している場合は不要)
- 印鑑証明書:銀行に預けている資産を受け取る人の印鑑証明書(通帳・証書、キャッシュカード、貸金庫のカギなども含む)
遺産分割協議書の場合
- 遺産分割協議書:遺産を誰が受け取るか明確に記載された書類の原本
- 戸籍謄本:口座名義人の出生~死亡までの連続した戸籍謄本、法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本
- 印鑑証明書:法定相続人全員分(通帳・証書、キャッシュカード、貸金庫のカギなども含む)
認知症の場合
家庭裁判所へ申し立てをし、成年後見人を選定後に銀行で口座凍結解除の手続きをします。
一般的に、成年後見人の選定には3か月程度かかるといわれています。
- 銀行での手続きに必要な書類
- 代理人自身の本人確認書類
- 代理権を持っていることが確認できる書類
- 通帳
- 届出印
凍結前の対策
解説の通り、口座凍結の解除には諸々手続きが必要です。
とくに口座名義人が亡くなったり認知症による凍結の際、解除手続きは家族がすることが多いため、家族の負担軽減のためにも対策を講じることを推奨します。
キャッシュカード、暗証番号情報の共有
親子間でキャッシュカードと暗証番号を共有することで、親の同意のもと、子どもが親の口座から出金ができます。
特殊詐欺の防止やキャッシュカードの磁気不足でATM操作の停止が起きたときは窓口で対応が必要になり、本人確認や本人の意思確認が求められます。
。
前述のように、相続人のうちの一人がお金を引き出していると、あとあとの遺産分割でモメる可能性も出てきます。
取引のある金融機関リストを作る
まずは取引のある金融機関リストを作りましょう。
近年では終活の一環で、エンディングノートに資産状況などの整理に役立つものもあり、いずれも万一のとき、家族が取引銀行の確認に役立ちます。
リストには以下を記入しておくといいでしょう。
-
-
- 銀行名
- 支店名
- 口座番号
- 口座の種類
- キャッシュカードの有無
-
関連コラム
保管場所の伝達
こちらも、万一のために通帳や印鑑など手続きに要るものの保管場所を家族に伝えておきましょう。
いざ手続きの場面になったとき、家族間で必要物のありかを把握していれば手続きがスムーズにできます。
金融機関の整理
先の金融機関リストを作ったら、場合により取引銀行の整理も検討しましょう。
亡くなられたあとはどれだけ残高が少なくても口座凍結の解除手続きは必要であるため、普段からあまり取引のない金融機関は解約するのも手です。
代理人カードや代理人予約サービスの利用
銀行によっては代理人カードという手段もあります。
- 家族間で同じ口座を共有し、事前に届け出た代理人もキャッシュカードを持つことで口座名義人に代わり入出金など一定の取引ができる
代理人カードの発行には本人が手続きをする必要があり、カード発行後本人から代理人にカードを渡します。
代理人による申し込みはできないため気をつけてください。
しかし、
・・・という考えは間違いです。
原則として代理人カードを作ってある口座でも関係なく、本人の判断能力低下を銀行が把握すると、口座凍結されてしまうのです。
本人の認知症が悪化した場合などは使えなくなる可能性がある点には留意してください。
また、銀行ごとに取扱いが異なります。
代わりに取引できるのは契約者本人と生計をともにする家族(同居している子どもや配偶者など)と定められていることが一般的ですが、「2親等以内の親族」と定めている銀行もあります(配偶者、子ども、孫、兄弟姉妹など)。
-
-
- 代理人になれる人
- できること
- できないこと
-
これら条件の詳細は、各銀行のHP、電話や窓口などで確認しておきましょう。
任意後見契約の締結
子どもをあらかじめ後見人に指定しておく手もあり、それが任意後見契約です。
親と、任せたい子どもとの間で任意後見契約を締結します。
ゆくゆく親が重度の認知症になり、契約や資産管理が難しくなった場合、子どもが優先して後見人に選ばれるしくみです。後見人になった子どもは、親の代理人として銀行預金の手続きができます。
また、後見人になるためには後見監督人をつけなければならないのです。
- 後見監督人とは
- 後見人になった子どもをサポートしたり、子どもが親のお金を使い込まないよう監視する役割を果たす人です。
- 後見監督人を誰にするかは家庭裁判所が選び、弁護士や司法書士がなります。
後見監督人になった専門家には報酬額が発生します。
本人が亡くなるまで、全額本人の資産から払うことになります。
家族信託契約の締結
親子間で家族信託契約を締結しておくことで親のお金を子どもが代わりに管理します。
- 家族信託の主な登場人物
- 委託者:資産の最初の所有者で信託する人
- 受託者:資産の管理運用処分を任される人
- 受益者:財産権を持ち、信託財産から経済的利益を受ける人
家族信託5つのメリット
家族信託のメリットは以下の5つです。
-
-
-
-
- 受託者を家族や親族内から自分で選べる
- 資産を子どもに引き継ぐことができる
- 認知症対策ができる
- 成年後見制度より柔軟
- リスクのある不動産共有を回避できる
-
-
-
受託者を家族内や親族内から自分で選べる
資産管理を誰に任せたいか、受託者を自分で選べます。
通常、配偶者や子ども、兄弟姉妹、甥姪が受託者になります。
しかしながら名前は「家族」信託とは呼ばれるものの、親族関係でなくても信頼できる人がいれば受託者になることができます。
また、家族信託契約を本人と受託者間で締結するだけでなく、受託者名義の口座に対象のお金を送金することが必要です。
資産を子どもに引き継ぐことができる
将来の相続対策ができることも家族信託契約のメリットです。
遺言同様、家族信託契約に定めることで相続で資産を誰に受け渡すかを決めることができます。
先々、相続人同士の間で遺産分割協議でモメることを防げます。
認知症対策ができる
近年増加している認知症問題ですが、家族信託の活用により家族の認知症対策ができます。
認知症が悪化するほど判断能力や意思能力が失われてしまうため、口座が凍結されてしまいます。
また、名義者本人に能力がないため、資産を自由に動かすことができなくなります。
そうした状況に陥る前に家族信託を活用することで、資産管理や処分権を家族に受け渡し、資産をいつでも動かせる状態が作れるメリットがあります。
成年後見制度より柔軟
成年後見制度と違い、家裁の関与が入りません。
専門家の監督人をつける必要がなく、家族だけで管理ができるため、成年後見制度より柔軟な対応ができます。
実際に、成年後見制度の活用を考えている方には以下のようなお悩みも出てくることも。
顔見知りの司法書士に依頼するつもりでしたが、選ばれたのは裁判所とつながっている司法書士の先生でした。
そのため、報酬額も想定より高くなり、これを毎月払い続けることに精神的にも経済的にも負担を感じています。
リスクのある不動産共有を回避できる
- 守りたい資産が金銭だけでなく不動産もある場合、家族信託は大きな効力を発揮します。
- 複数人が持分をもっている不動産でも、あらかじめ相続者を決めておくことができるため、発生しがちなトラブルを避けることができます。
親の資産に持ち家などの不動産がある場合は、相続発生後の遺産分割協議で話がまとまらないと、不動産を共有で相続することになります。
親の持ち家を共有で相続した場合、相続人同士で今後家をどうするかのビジョンや意見が対立するとモメて厄介ですが、家族信託をしておくことによって、先述の理由で回避できます。
おわりに
解説したように、事前対策は親が生きているうちに家族信託を推奨します。
今後の万一に備え、ご家族の負担を減らしたい場合は今回解説した対策を講じるといいかと思います。
さらに踏み込んでより具体的に対策したい場合は、相続相談もできる東京空き家相談協会へご連絡ください。