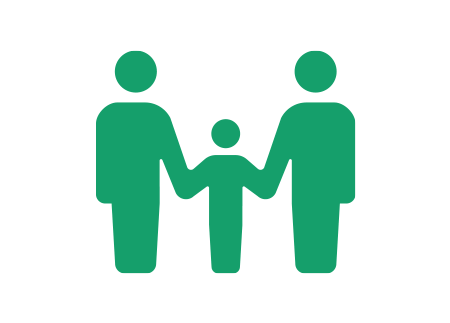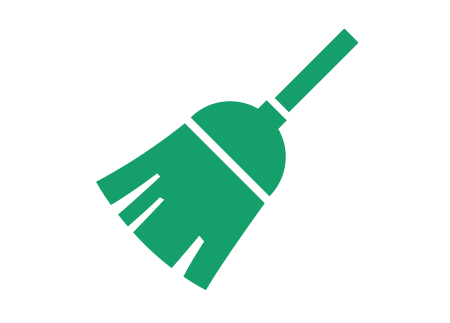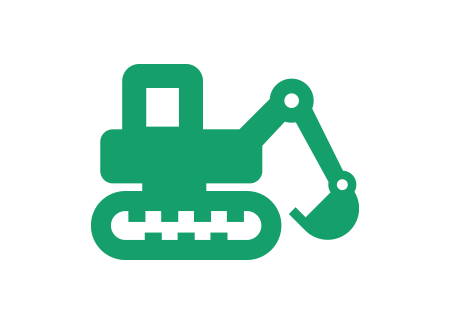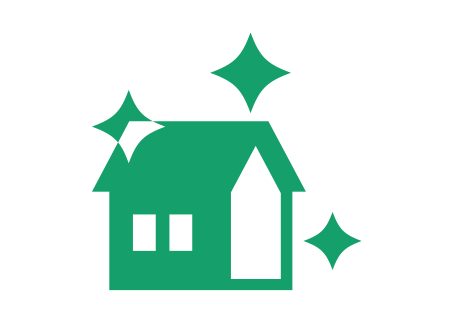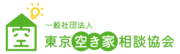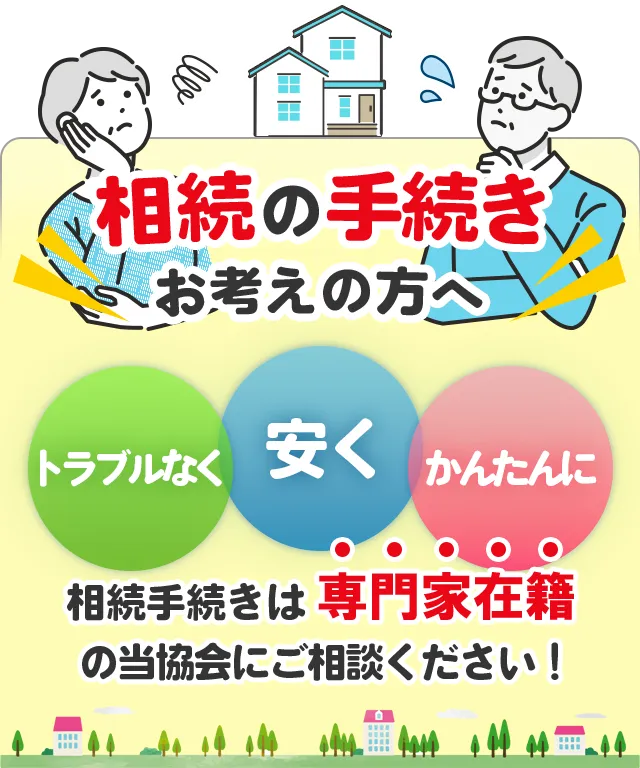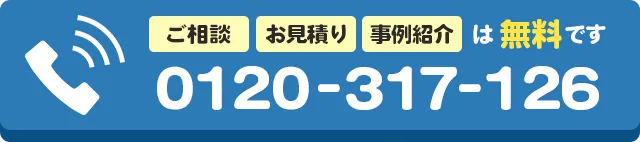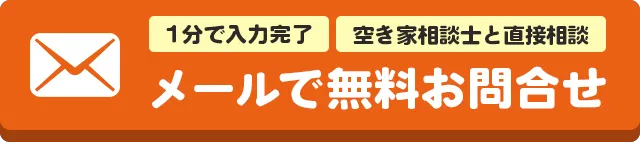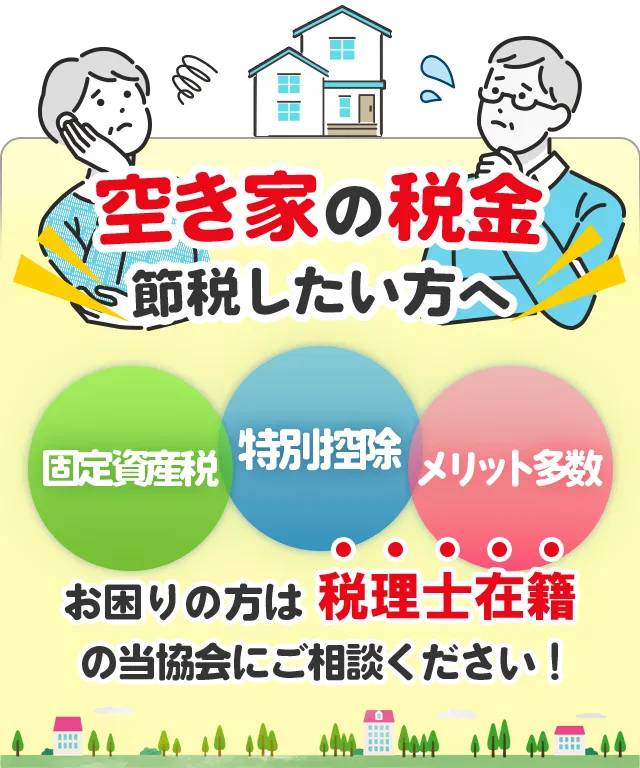親や身内が亡くなった際、役場や相続人間で多くの手続きを進める必要があります。
手続きをスムーズに進めるためにも、本ページに掲載している「親や家族が亡くなったあとの手続き一覧表」を活用しながら、漏れを防ぎましょう。
- 期限別親の死亡後に必要な手続き
- 手続きに必要なもの
- 手続きに関するよくある質問
親や身内が亡くなったあとの手続き一覧表
以下は、親や家族などの身近な人が亡くなった際に進める手続きの一覧表です。
画像を保存して、あとから見返せるようにしましょう。

なかには手続きを怠ることで罰金などの不利益が発生するものもありますので、忘れずに進めましょう。
各手続きの詳細は、次項より解説いたします。
親や身内が亡くなった時の手続き【死亡後すぐにすること】
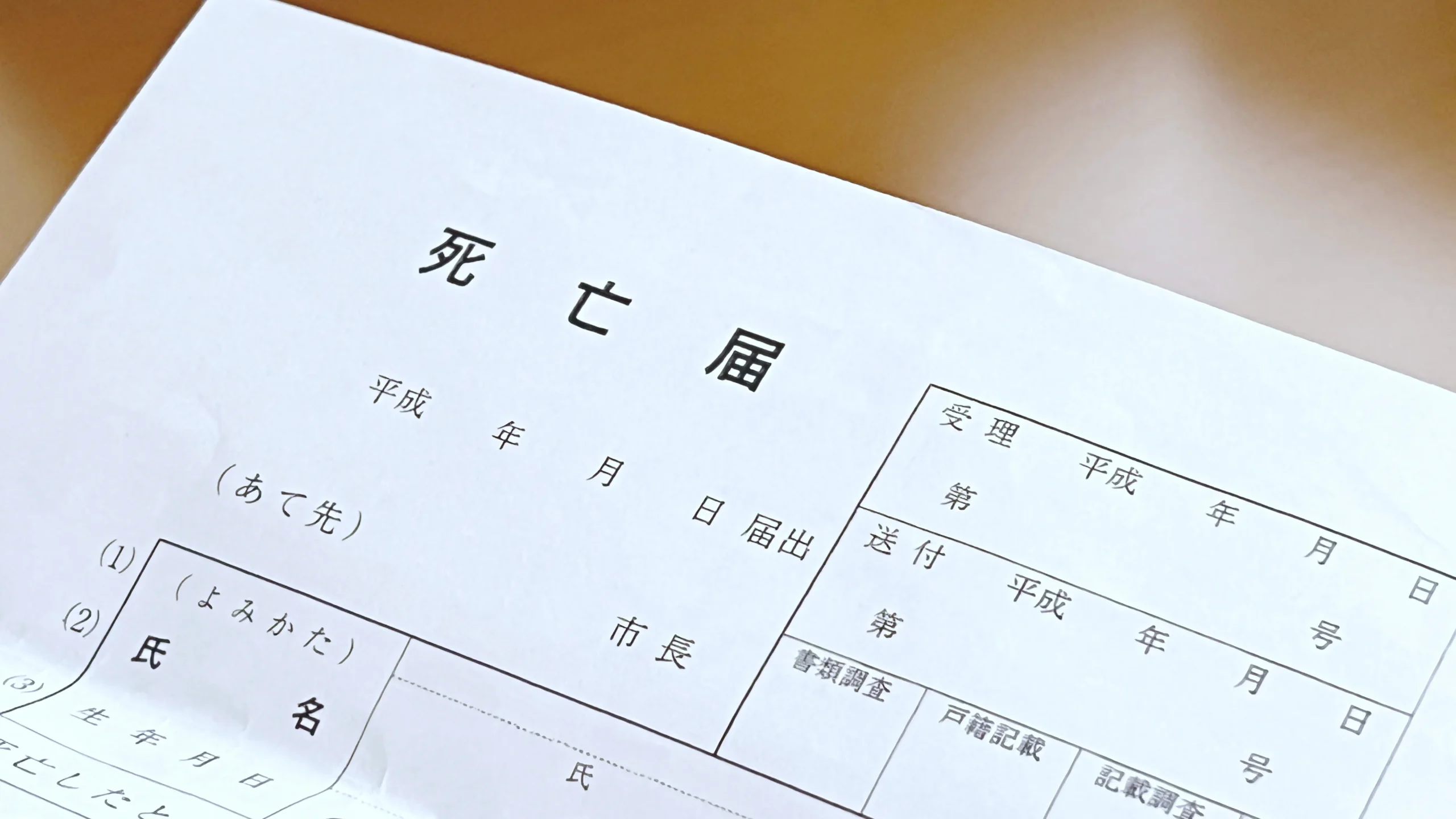
親や身内が亡くなった場合、遺族は悲しみのなかで対応しなければいけないことが数多くあります。
はじめに、死亡後すぐに進めるべきことをご紹介します。
- 死亡診断書・死体検案書の受取
- 死亡届の提出
- 埋火葬許可証受取
- 訃報の連絡
- 葬儀社と打合せ・葬儀
- 遺言書の確認
公的な死亡後の手続き
死亡後すぐに行なうべき公的な手続きは以下の通りです。
死亡診断書・死体検索書の受取
- 死亡診断書とは
- 医師が死因を確認した際に発行する書類のこと。
病院で死亡した場合は、医師が即時「死亡診断書」を発行しますが、自宅などで死亡した場合は違います。
そして検視を経て「死体検索書」が発行されます。
かかりつけ医がいる場合、「生前に治療を受けていた病による死亡」と認められると、死亡診断書が発行されます。
これらの書類は、以下などのすべての手続きに必要となるため、複数枚コピーをとっておくと便利です。
- 死亡届の提出
- 葬儀
- 火葬
死亡届の提出・埋火葬許可証の受取
死亡診断書または死体検索書を受け取り次第、7日以内に死亡届を提出しなければいけません。
- 死亡届とは
- 故人の死亡を法的に確認するための重要な手続き。
- 提出先:故人の本籍地や死亡地、届出人の住居地の市区町村役場
- 埋火葬許可証とは
- 火葬や埋葬をするための届出。
- これがなければ火葬や埋葬ができないため、届出と同時に受け取り、火葬まで大切に保管する必要がある。
- 死亡届の提出や埋火葬許可証の受取は葬儀社のスタッフが代行してくれることがほとんど
病院に遺体を迎えにきてくれた際や葬儀の打ち合わせの際に、手続き代行を提案されるため、死亡診断書(死体検索書)を揃えておきましょう。
私人間の死亡後の手続き
つぎに、私人間で行なうことです。
訃報の連絡
故人の訃報を家族や親族、友人や関係者に連絡しましょう。
連絡は、以下の優先度で進めるとスムーズです。
- 近親者
- 親しい友人や職場の関係者
電話での連絡が難しければ、メールやLINEでの報告でも問題ありません。
近親者に送る内容は、以下がよいでしょう。
- 故人の名前
- 死亡日時
- 決まっている場合は葬儀の日程
とくに参列が予想される方には、詳細な情報を提供し、当日の流れを確認してもらうことが重要です。
葬儀社との打ち合わせ・葬儀
訃報の連絡をした後は、どのような葬儀にするか葬儀社と打合せを始めます。
葬儀社との打ち合わせでは以下を決め、必要な物品やサービスの手配を進めます。
- 葬儀の形式
- 規模感
- 日時
- 場所
ミスマッチが起こらないよう、予算に合わせたプランの選定や、宗教的な儀式の要望を伝えましょう。
葬儀の準備にかかる時間には限りがあります。
しかし、早急に進めるだけではいけません。
トラブルを避けるためにも、故人をはじめ親族の意向を尊重しすり合わせながら、計画的に進めていきましょう。
相続関係の死亡後の手続き
さいごに、相続関係の死亡後の手続きです。
遺言書の確認
遺言書の有無によって、その後の遺産分割がスムーズにいくかが決まります。
故人が遺言書を残していた場合は、その内容を早急に確認しましょう。
遺言書には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
- 公証証書遺言とは
- 公証役場で公証人が2人以上の立ち会いのもと、遺言者の意向を文書にして作成する遺言の形式。
- 専門家である公証人が立ち会うため、法律的な不備による無効のリスクが低い。
- 公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクも低い。
- 家庭裁判所の検認が不要
- 自筆証書遺言とは
- 遺言者自身が遺言の全文、日付、氏名すべてを手書きし、押印する遺言の形式。
- 作成費用がかからず、誰にも内容を秘密にできる。
- 紛失や改ざんのリスクがあるため、最近では遺言書の原本を法務局に保管できる「自筆証書遺言書保管制度」が注目されている。
- 開封前の家庭裁判所での検認が必須
自筆証書遺言の場合は検認をせずに開封すると、過料が科せられる可能性があるため、注意が必要です。
親や身内が亡くなった時の手続き【14日以内にすること】

親や身内が亡くなったあと、14日以内に行なうべき手続きが数多くあります。
これらの手続きは、期日後に進めることが困難なものもあるため、速やかな確認と進行が重要です。
- 年金受給停止手続き
- 健康保険資格喪失の手続き
- 介護保険資格喪失の手続き
- 住民票の世帯主変更手続き
- 電気・ガス・水道の契約者変更
- 新聞・インターネットの契約者変更または解約
- 携帯電話の解約
- クレジットカードの解約
- その他契約サービスの解約
- 運転免許証の返納
- パスポートの返納
- 不動産の名義変更
- 預貯金の名義変更
- 株式の名義変更
- 自動車所有権の移転登録申請
公的な14日以内の手続き
まずは公的な、14日以内に行なうべき手続きです。
年金受給停止手続き
年金を受給していた人が亡くなった場合、年金の受給停止手続きをすみやかに行ないましょう。
年金の形態別の締め切りは以下の通りです。
- 国民年金は死亡日から14日以内
- 厚生年金は10日以内
最寄りの年金事務所または年金相談センターで行ないます。
また、その時に必要な持ち物は以下のとおりです。
- 年金証書
- 死亡診断書のコピー
- 年金受給権者死亡届
健康保険の資格喪失の届出
故人が健康保険に加入していた場合、死亡後すぐに資格喪失の届出をおこなう必要があります。
会社員であれば5日以内に勤め先が手続きをおこない、国民健康保険の場合は14日以内に市区町村の役場に届出をしてください。
この手続きをおこなうことで、故人の保険料の支払いが停止され、未支給の医療費が発生しないようにします。
介護保険資格喪失の届出
故人が介護保険の被保険者であった場合、死亡後14日以内に介護保険資格喪失の届出を市区町村役場でおこなう必要があります。
保険料の過払いを防ぐためにも、早急に役場の窓口へ向かいましょう。
住民票の世帯主変更手続き
故人が世帯主であった場合、住民票の世帯主変更手続きを14日以内に市区町村役場でおこなう必要があります。
役場での手続きを通じて、故人に代わって新たな世帯主が正式に登録されます。
私人間の14日以内の手続き
つぎに、私人間での14日以内の手続きです。
電気・ガス・水道の契約者変更
故人が契約者となっている電気・ガス・水道の契約は、速やかに名義変更や解約手続きをおこないましょう。
各サービスの名義変更の際には、該当の供給会社に連絡し、所定の書類を提出することで完了します。
いずれも早めに対応しましょう。
新聞・インターネットの契約者変更または解約
故人が契約者である新聞やインターネットのサービスも、死亡後速やかに契約者変更や解約手続きが必要です。
手続きは、各サービス提供者に連絡して解約または名義変更を依頼します。
できれば「エンディングノート」などを用意し、生前に確認しておくことをおすすめします。
関連記事
携帯電話の解約
故人が使用していた携帯電話は、キャリアのサポートセンターに連絡して解約手続きをおこないます。
以下は、代表的なキャリアの故人の解約手続きに関するページです。
解約と同時に、データの保管の有無や方法についてもスタッフや親族と話し合いましょう。
クレジットカードの解約
故人が所有していたクレジットカードは、速やかに解約手続きを行なってください。
クレジットカード会社に連絡し、死亡を伝えることで手続きが開始されます。
また、カードに未払いの残高がある場合は、精算後に解約が完了します。
その他契約サービスの解約
故人が契約していた各種サービス(サブスクリプション、レンタルなど)は、契約者死亡の事実を伝えたうえで解約手続きをおこなってください。
すべての契約情報を確認し、速やかに解約手続きをすることをおすすめします。
運転免許証の返納
故人が所持していた運転免許証は、最寄りの警察署または運転免許センターに返納します。
返納が完了すると、免許証は無効化され、必要に応じて形見として保管することもできます。
パスポートの返納
故人のパスポートは、速やかにパスポートセンターや市町村の窓口に返納しましょう。
パスポートは自動で期限が切れます。
返納されたパスポートは無効化され、希望すれば形見として保管することも可能です。
パスポートセンターは混雑が予想されるため、手続きが完了するまでの所要時間についても事前に確認しておくと安心でしょう。
東京都内では、窓口の混雑状況がリアルタイムでわかるページもあります。
相続関係の14日以内の手続き
つぎに、相続関係の14日以内の手続きです。
不動産の名義変更
故人が所有していた不動産の名義変更は、相続手続きの一環としておこないます。
不動産の名義変更は「所有者移転登記」といいます。
この手続きは法務局で行ない、相続人の間で遺産分割協議を経たうえで、相続登記を申請してください。
預貯金の名義変更
故人の預貯金口座は、相続人が名義変更手続きをおこなう必要があります。
手続きを完了することで、預貯金の引き出しや移管が可能になります。
口座にお金が入っているのに引き出しができなくなるのは、経済的ダメージが大きいですね…。
株式の名義変更
故人が保有していた株式の名義変更は、株式を発行している証券会社や信託銀行でおこないます。
株式の名義変更には時間がかかるため、早めに手続きを進めることをおすすめします。
自動車所有権の移転登録申請(相続から15日以内)
故人が所有していた自動車の所有権は、相続から15日以内に移転登録申請をおこないましょう。
この手続きは、運輸支局または自動車検査登録事務所でおこないます。
いざとなった時に必要なものを探し回ることになるため、あらかじめ保管場所を確認しておくことが大切です。

親や身内が亡くなった時の手続き【死亡後1年以内にすること】
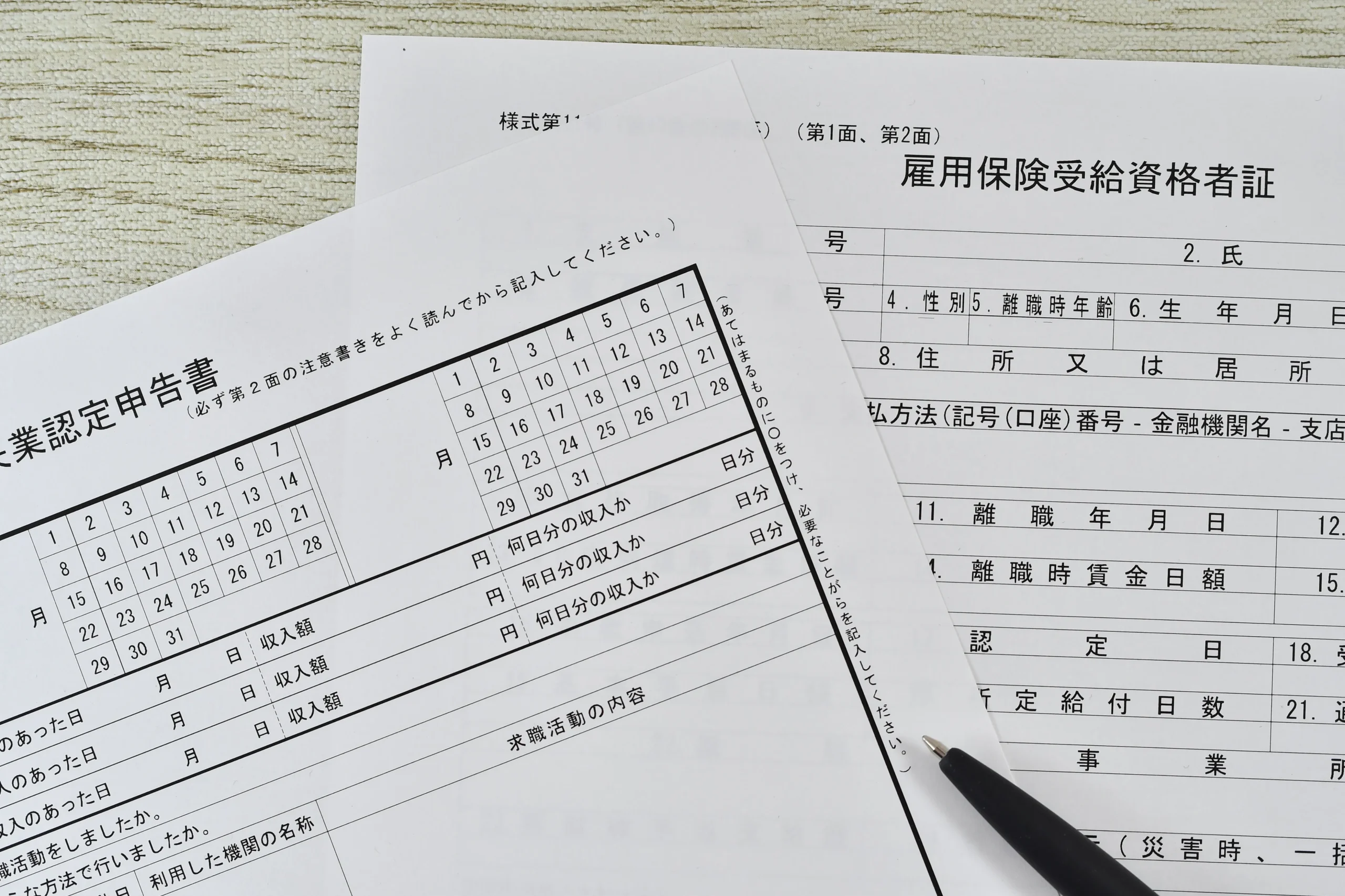
親や身内が亡くなった後には、1年以内に行なうべき手続きがいくつかあります。
これらの手続きは、以下の法律や税務に関わる重要なものが多く、期限が定められているため早めにおこないましょう。
- 相続
- 税務申告
以下では、死亡後1年以内におこなうべき手続きを詳しく紹介します。
- 雇用保険受給資格者証の返還(1ヵ月以内)
- 相続税の申告・納税(4ヵ月以内)
- 所得税準確定申告・納税(10ヵ月以内)
- 相続放棄(3ヵ月以内)
公的な1年以内の手続き
まずは、公的な手続きです。
雇用保険受給資格者証の返還(1ヵ月以内)
故人が雇用保険を受給していた場合、受給資格者証は死亡後1ヵ月以内にハローワークに返還してください。
速やかに手続きすることで、受給権が消滅し、未払い分がある場合は精算されます。
手続きは直接窓口に行くか、郵送で行なうことが可能です。
所得税準確定申告・納税(4ヵ月以内)
故人が自営業を営んでいた、または年収2,000万円以上の給与所得者であった場合、死亡後4ヵ月以内に所得税の「準確定申告」が必要です。
相続人が申告を代行し、故人の収入に基づいた納税をおこないましょう。
不明な点がある場合は、税理士に相談しましょう。
税理士が所属している当協会でも無料相談を承っているため、お気軽にご連絡ください。
相続税の申告・納税(10ヵ月以内)
故人の相続財産が基礎控除額を超える場合、相続税の申告と納税を死亡後10ヵ月以内におこなう必要があります。
申告は、相続財産の評価や分割に基づいておこなわれ、税務署に提出します。
相続関係の死亡後の1年以内の手続き
相続関係では、なんといっても相続放棄の期限があります。
相続放棄(3ヵ月以内)
故人の負債が多く、相続人が相続を希望しない場合は、死亡を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行ないましょう。
- 相続放棄を行なうことで、負債を相続する義務を免れることが可能です。
マイナスの財産を受け継がなくてもよいという大きなメリットがある反面、プラスの財産も受け継ぐことができません。
「不動産は相続して、負債だけ相続放棄したい」ができないのです。
親や身内が亡くなった時の手続き【2~5年以内にすること】

親や身内が亡くなった後、2〜5年以内におこなうべき手続きは、保険金や年金の請求、医療費の還付など、金銭に関わる重要な手続きです。
期限が過ぎると受け取れるはずの金銭を受け取れなくなる場合もあるため、期限内に必ず請求手続きをしましょう。
- 国民年金の死亡一時金請求
- 埋葬費の請求
- 葬祭費の請求
- 高額医療費の還付申請
- 生命保険金の請求(3年以内)
以下では、該当期間内におこなうべき手続きを詳しく紹介します。
2年以内にやらなければならない死亡後の手続き
はじめに、2年以内にやらなければならない手続きです。
国民年金の死亡一時金請求
故人が国民年金の第1号被保険者であった場合、死亡一時金を請求できます。
請求期限は、故人の死亡日の翌日から2年以内となります。
この一時金は、故人が年金を受給していなかった場合に支払われるもので、請求を忘れると受給権が消滅してしまいます。
請求は市区町村役場や年金事務所で行なえるため、手続きするうえで不明点がある場合は、担当窓口で確認することをおすすめします。
埋葬料の請求
故人が健康保険に加入していた場合、埋葬にかかった費用として埋葬料の請求が可能です。
請求は、故人の死亡日の翌日から2年以内におこなう必要があります。
埋葬料の請求は義務ではありませんが、受け取るべき費用が受給できなくなるため、早めに手続きを行なう必要があります。
健康保険組合や協会けんぽが窓口となるため、疑問点などは各担当者へ確認してください。
葬祭費の請求
国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた故人の葬祭費は、葬祭を行なった日の翌日から2年以内に請求可能です。
市区町村によって受給金額や手続き方法が変わるため、該当の市区町村に確認のうえ、手続きを進めていきましょう。
高額医療費の還付申請
故人が亡くなる前に高額な医療費を支払った場合、2年以内に高額医療費の還付申請をすることができます。
高額医療費制度を利用することで自己負担限度額を超えた部分の医療費が還付されるため、申請はお忘れなく!
手続きの方法は、各種健康保険組合や市区町村の窓口で確認しておきましょう。
5年以内にやらなければならない死亡後の手続き
つぎに、5年以内にやらなければならない手続きです。
生命保険金の請求(3年以内)
故人が生命保険に加入していた場合、死亡保険金の請求は死亡日から3年以内に行ないましょう。
生命保険金の請求をしないと、請求権が消滅するため、すぐに保険会社へ連絡して手続きを進めてください。
保険会社によって手続き方法や必要書類が異なります。
事前に確認しておきましょう。
遺族年金の請求
遺族年金は、故人によって生計を維持されていた配偶者や子どもが受給できる年金のことです。
請求期限は死亡日から5年以内です。
手続きは年金事務所または年金相談センターで行ないます。
期限内に請求しないと、受給権が消滅するため、迅速に手続きを進めましょう。
故人の未支給年金の請求
故人が受給すべき年金が未支給であった場合、未支給分を請求できます。
請求期限は、死亡日の翌日から5年以内で、年金事務所または年金相談センターで手続きを行ないます。
請求を怠ると、未支給年金を受け取る権利が消滅するため、迅速に手続きを進めましょう。
親の死亡後の手続きに関するよくある質問

親の死亡後に行なうべき手続きが数多くあることは本ページでもご紹介しました。
そのような状況で、よくいただく質問とその解答をご紹介します。
親の死亡後の手続きの優先順位が知りたい
多くの手続きがあることが分かっても、何から完了すべきか迷いますよね。
まずは、公的な手続きから始めましょう。
- 死亡届の提出
- 年金の受給停止手続き
そのつぎに、以下の私人間の手続きを進めましょう。
- 訃報の連絡
- 葬儀の手配
- 契約の解約や変更手続き
遺産相続関係の手続きは期限が長いですが、早めに着手すると親族や税金に関するトラブルを防げるため、準備しておくことをおすすめします。
公的手続き → 私人間の手続き → 相続関係の手続きと優先順位をつけましょう。
親が亡くなったら仕事を何日休む?
親が亡くなった時の忌引きの日数は7日が目安といわれています。
一般的な日数が一般的な以下の通りですが、会社によって規定が異なるため確認しましょう。
| 配偶者 | 10日 |
|---|---|
| 子ども | 5日 |
| 祖父母や兄弟姉妹 | 3日 |
| 義理の父母 | 3日 |
死亡後の手続きで絶対に役所に提出すべき書類は?
- 死亡届
- 死亡診断書
- 埋火葬許可証申請書
- 国民健康保険資格喪失届
- 介護保険資格喪失届
- 世帯主変更届
親が亡くなった際に、役所に提出しなければならない書類は数多くあります。
とくに死亡届・死亡診断書は必須で、これを提出しなければ火葬や埋葬をすることができません。
つぎに、埋火葬許可申請書を提出することで、火葬許可証を受け取ることができます。
そのつぎは、以下の保険加入状況によって提出するものが変わります。
- 国民健康保険資格喪失届
- 介護保険資格喪失届
さらに故人が世帯主だった場合は、世帯主変更届も必須です。
これらの書類は、法的に必要な手続きです。
期限内に必ず提出しなければなりません。
親が亡くなったらいくら香典を包む?
親が亡くなったときの香典は、5~10万円程度が相場といわれています。
しかし、自身が喪主である場合は香典を出す必要はありません。
また、たとえば学生のように故人の扶養家族だった子どもは不要です。つまり、喪主でなく、かつ世帯を別に構えている場合は、たとえ子どもであっても香典を出すことが一般的です。
親が亡くなった時に香典を出すか、そして金額相場は以下によって異なるケースがあります。
- 家族間の関係性
- 自身の年齢
- 地域
親が亡くなったら銀行口座はどうなるの?
親が亡くなると、銀行口座は法的に凍結されます。
相続が確定するまでの間、相続財産を保護するために行なわれる措置です。
口座凍結後、相続人は銀行に連絡し必要な手続きをすることで、凍結解除とともに口座の名義変更や資金の分配が可能になります。
手続きに必要なものは、以下の通りです。
- 死亡診断書
- 相続関係を証明する書類
- 相続人全員の同意書
- 故人・相続人全員の印鑑証明
凍結解除の手続きには時間がかかるため、早めに対応するようにしましょう。
また、銀行によっては事前相談や手続き方法が異なる場合があるため、早めに確認しておくとスムーズです。
以下の記事で、口座凍結について詳しく解説しています。
関連記事
親や身内が亡くなった時の手続きは一覧表を見ながらスムーズに!
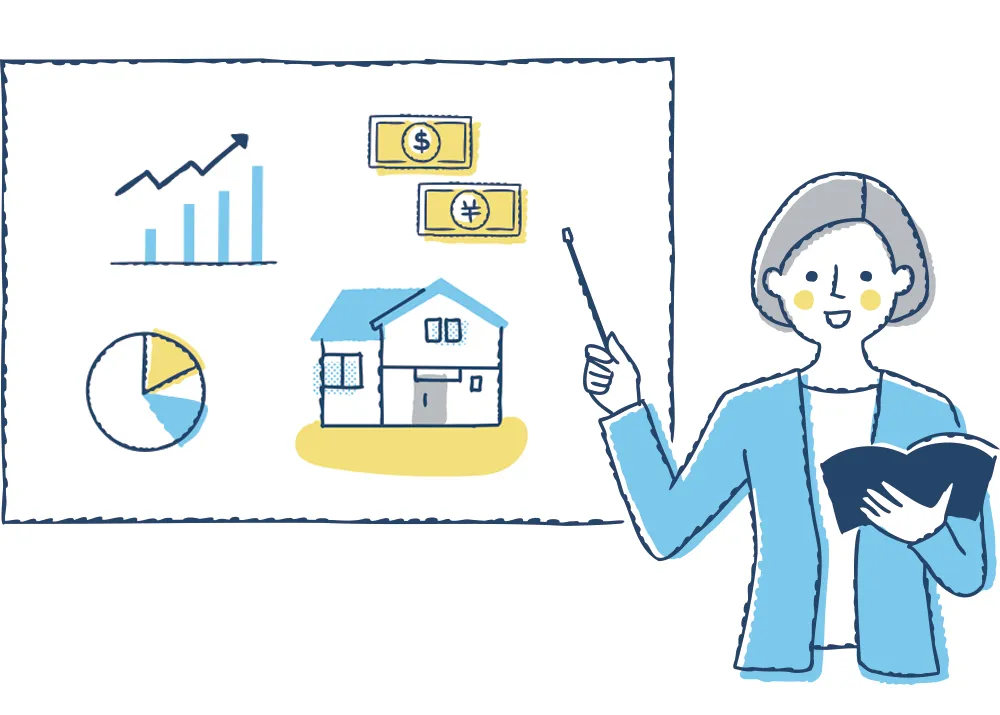
このように親や身内が亡くなった際、ゆっくりと過ごしたい気持ちとは裏腹に、対応しなければならない手続きも数多くあります。
そんな時、東京空き家相談協会にご連絡ください。
- 自分は何をすべきか
- 自分では抱えきれない
- 相続手続きにかかる金額を知りたい
- 親が住んでいた家の今後を決めたい
すこしでもこのように思った方は、ご連絡ください。
- 専門家所属!無料相談 実施中!
- 今回ご紹介したなかでも、相続や税金、ご実家の今後などは当協会の得意分野です。
- ご連絡いただければ最短即日~3営業日以内に適切な解決策やお困りごとに精通した専門家をご紹介しています。