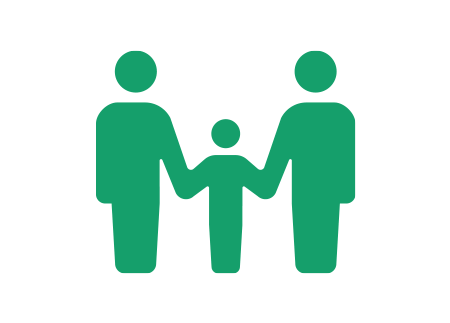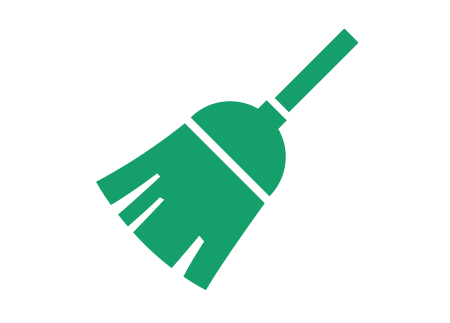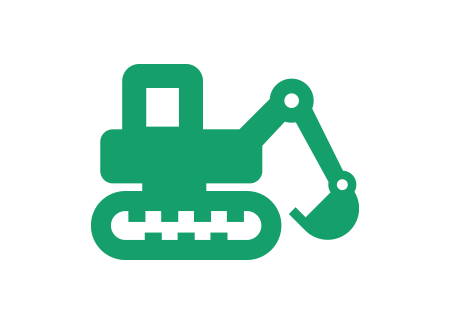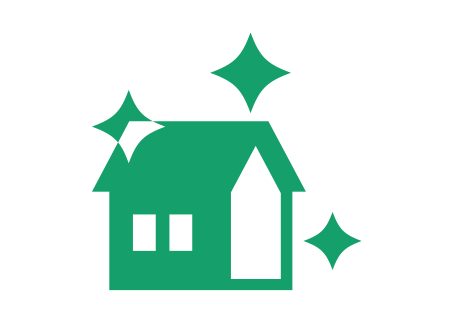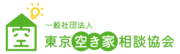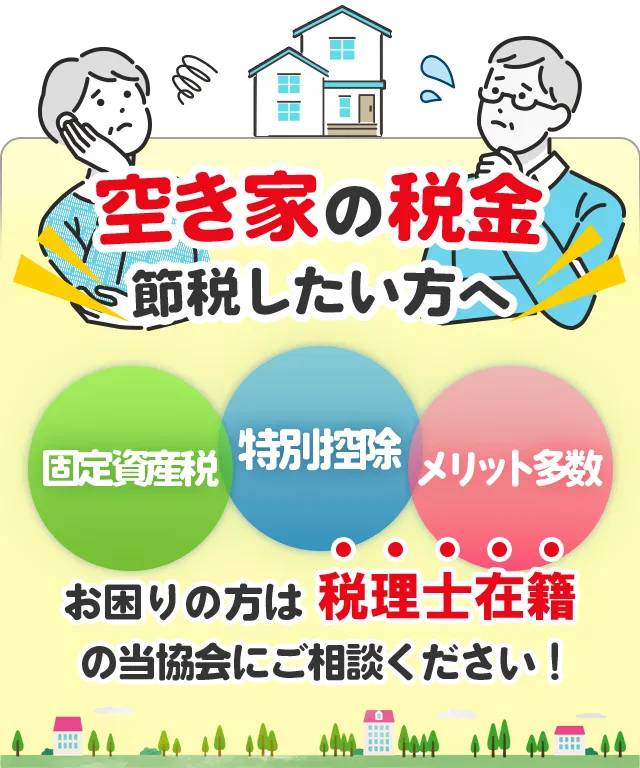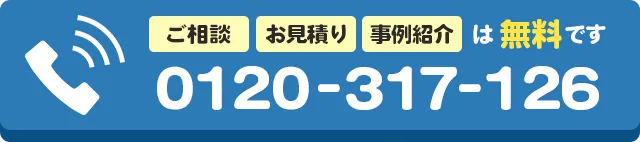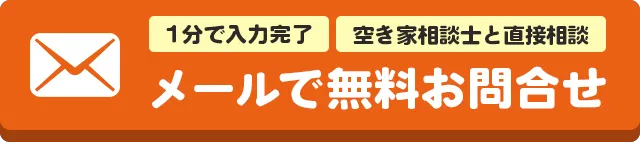築古のアパートを子供に相続すると、アパートの処分で子供に思わぬ負担がかかることがある一方で、節税対策になる可能性もあります。
子どもにアパートを引き継ぐ際には以下の方法をとることが可能ですが、どちらの方法が節税対策としてより適切なのでしょうか?
- 死後に相続する
- 生前贈与する
アパートの相続税・贈与税の考え方と計算方法
まずは、アパートを相続・贈与する際、相続税・贈与税はどのように考えていくのかを確認していきましょう。
評価額の計算方法については後ほど解説しますので、まずは「相続税・贈与税の基礎控除」についてチェックしていきましょう!
相続税・贈与税の基本と基礎控除
相続税と贈与税にはそれぞれ基礎控除があります。
- 基礎控除とは
- どんな人でも条件を満たせば適用でき、課税金額に対して発生する一定額の差し引きです。
相続税と贈与税で計算方法が異なりますので、下記で個別に解説していきます。
相続税の基礎控除
相続税の基礎控除額は、相続人の数によって上下します。
- 例えば相続人が3人いる場合4,800万円となり、遺産総額がこの金額以下でしたら相続税はかかりません。
- また相続財産となる生命保険金がある場合、「生命保険金額から相続人の数×500万円」で求めた金額を差し引くことができます。
- 相続人が3人の場合は1,500万円までの生命保険金は相続税がかかりません。
このように計算し、基礎控除額を差し引いた後の金額を「課税遺産総額」といいます。
贈与税の基礎控除
贈与税の基礎控除は、1月1日から12月31日の1年間で110万円と定められています。
したがって、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
出典:国税庁HP
アパートを相続または贈与するときは路線価評価で財産評価する
アパートを相続・贈与する際の評価額はどうやって出すのでしょうか?
これは、土地・建物によって算出方法が異なります。
- 相続土地:相続路線価を用いて算出
- 建物:固定資産税評価額をもとに算出
土地の評価方法
- 土地の評価額を計算する際に使う相続路線価とは
- 国税庁が土地に接する道路につけている土地1㎥あたりの金額です。
国税庁ホームページで各地域の路線価を確認することができますので、それをもとに評価額を計算していきます。
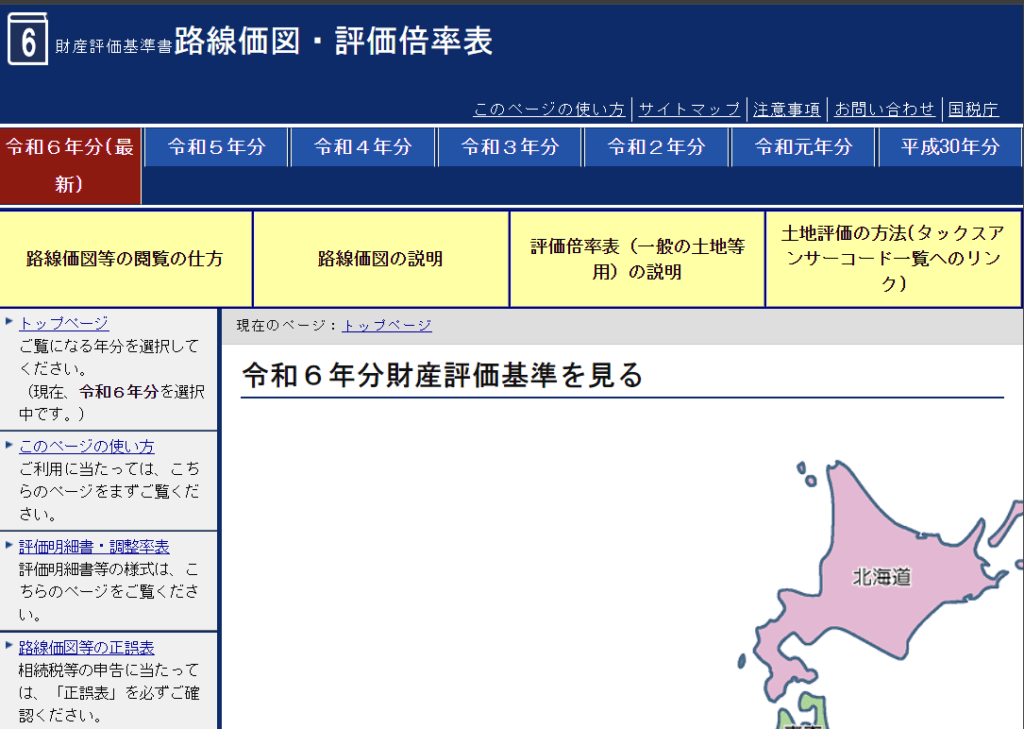
ただ、土地面積に路線価をそのまま掛ければいいわけではなく、土地の借地権割合や賃貸割合などを鑑みて、その分を減額しなければいけません。
- 評価額の計算方法
- 土地面積×路線価×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
- 賃貸割合とは
- 賃貸物件を第三者に貸している割合のこと。
同じ広さの部屋が10部屋あるアパートでは、賃貸割合を次のように判定します。
- 全部屋を貸している:100%
- 9部屋を貸して、1部屋は子が使っている:90%
- 9部屋埋まっている、1室は募集中:100%
- 9部屋埋まっている、1室は募集もしていない:90%
建物の評価方法
建物評価額は、固定資産税評価額から計算します。
- 固定資産税評価額
- 毎年届く納税通知書に綴られている課税明細書で確認することができます。
課税明細書に記載してある評価額をもとに、次の計算を行います。
固定資産税評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)
アパートを相続する際の遺産分割の方法
- 相続の際に被相続人の遺言がなかった場合
- 相続財産をどのように分割するかは遺産分割協議によって相続人同士が取り決めます。
その理由として不動産は財産価値が高く、分けにくいという特徴があることが挙げられます。
そのため、不動産を含む財産分割の際には、下記の4つの方法からいずれかを選択することが一般的です。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
- 共有分割
現物分割
アパートや現預金等の遺産がある場合、相続人Aがアパート、相続人Bは現預金というように物で分ける方法です。
非常にシンプルな分け方なので、すぐに手続きが終わります。
アパートと現預金等とで財産の価値が平等になりにくく、相続人間でトラブルにならないよう、注意が必要です。
代償分割
アパートを相続する代わりに、アパートを相続しない他の相続人へお金を支払う方法です。
相続人Aがアパートを、相続人Bがそれ以外の財産を相続し、アパートとその他の財産の評価額の差分だけAからBに現金が支払われます。
代償金として取得した財産は相続税の課税対象です。
不動産を含む財産の遺産分割を行う際によく使用される方法です。
遺産の評価や代償金の支払い方法などを巡って、相続人の間で意見が合わないことも多いです。
換価分割
アパートを売却してその代金を相続人で分ける方法です。
不動産を売却し、現金を1円単位で分割できるこの方法は相続人間でトラブルになることが少なく、遺産分割協議がスムーズに進むというメリットがあります。
ただ、アパート売却の際に手数料や譲渡所得税がかかりますので、その支払いを誰がするのか、という点を予め決めておき、トラブルを避けられるようにしておきましょう。
共有分割
アパートを相続人で共有する方法です。
共有持ち分は相続人間で平等に分けることも、特定の相続人だけ多くの持ち分を手にすることも可能です。
遺産分割協議でトラブルが発生しにくい。
共有後にトラブルが発生するケースがある点に注意すべきです。
売却や大規模な改修をしたくても共有者の同意が必要だけど断られたなど、アパート経営の融通が利かないことも少なくありません。
注意点!時価と評価の違い

不動産を遺産分割する時には評価額を用いますが、これは時価とは異なりますので、注意が必要です。
評価額とは先述の通り、路線価や固定資産税評価額など、国が定めた価格に基づいて計算されたものです。
- 時価とは
- その時々の不動産取引市場の動向によって変化する価格。
相続する不動産周辺の土地価格が上がれば当然その不動産の時価も上がります。
そのため遺産分割協議において、相続人Aは不動産を、Bはその他の財産を平等に分割した場合、「評価額で見ると公平な遺産分割だけど、時価で見ると不公平になる」ということが発生することがあります。
築古アパートの相続税を節税する2つのポイント
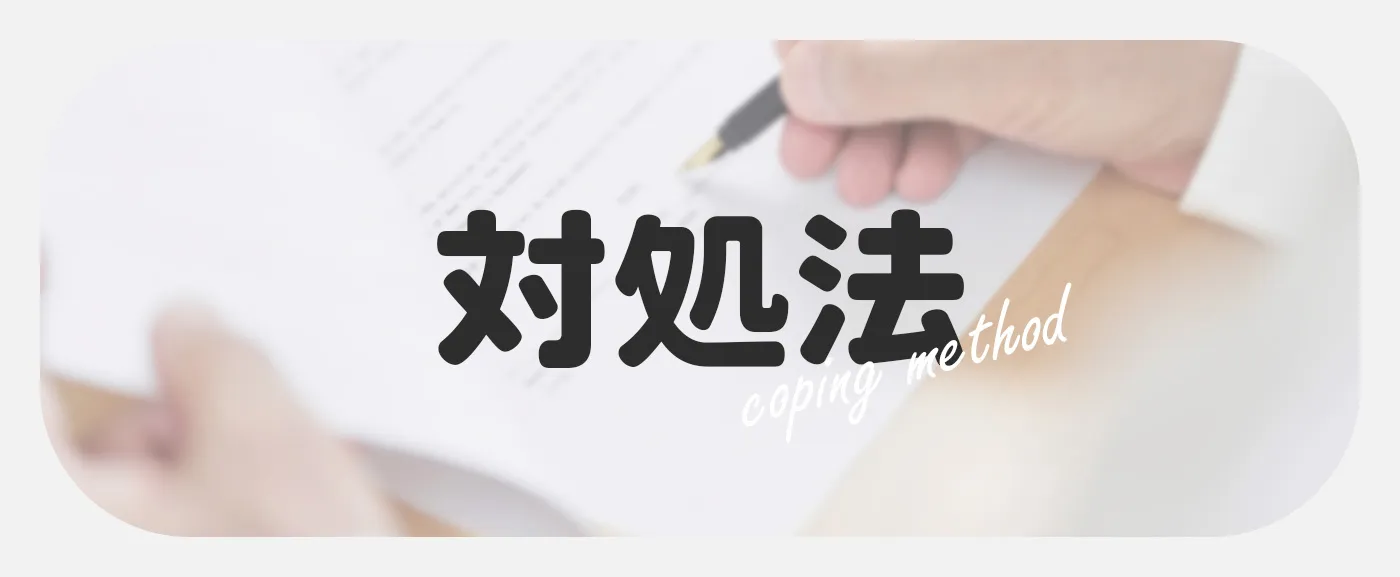
ここからは築古アパートを相続した際、相続税を節税する方法を紹介していきます。
今のうちに実践しておくことで、将来的な節税効果が期待できますよ!
空室対策を行い、賃貸割合を上げる
しかし、空室があっても募集もせずそのままにしておくと、賃貸割合が下がります。
賃貸割合が下がると結果的に評価額が上昇してしまい、より多くの税金が課せられますので、空室はそのままにせず、入居者募集をかけるようにしておきましょう。
借入金を増やし、相続財産を引き下げる
- 外壁や階段を塗装する
- 入居者が喜ぶ設備を導入する など
この場合、設備投資にかかる費用は親の財産から支払われることになるので、結果的に相続財産が減り、相続税が安くなることにつながります。
導入した設備は相続財産として計上されますが、償却といって年々その価格が減りますので、現金として相続するよりも節税効果が見込めます。
- 築古アパートを解体し、新築する
- 築古アパートを売却して違うアパートや小口化不動産等へ組み替える
アパートを生前贈与する2つの方法
生前贈与をする際の基礎控除は年間110万円なので、アパートを生前贈与してしまうと、あっという間に基礎控除額を上回ります。
アパートを生前贈与する場合はどのような手段をとれるのでしょうか?
以下方法をそれぞれ解説します。
- 暦年贈与
- 相続時精算課税制度による贈与
暦年贈与
- 先述の通り、年110万円までは非課税で贈与できるため、アパートの持分を子1人に毎年110万円ずつ贈与すれば、贈与税は課税されません。
- ただしアパートは高額な場合が多いので、何年かけて贈与をすればよいのかなどをシミュレーションしておく必要があります。
- 贈与のたびに登録免許税や取得税や、司法書士等への報酬の負担があるというデメリットもあるため、無料でシミュレーションしたい方はぜひご連絡ください。
相続時精算課税制度による贈与
- 相続時精算課税制度とは
- 生前贈与するときの贈与税の負担を軽くして、相続のときに精算するという制度です。
この制度の要件として、以下が定められています。
- 贈与のあった年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対する贈与
- 贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に申告書を提出
- 贈与財産の種類や金額、贈与回数に制限なし
- 非課税の上限は2,500万円
この制度を利用して贈与された財産は相続税の支払い時に相続財産として計算され、更に年110万円の基礎控除や、小規模宅地の特例(土地を贈与された場合)が併用できなくなります。
他の特例が使えなくなり、更に贈与された財産は後々課税対象となるので、この制度の利用は慎重に判断しましょう。
- 贈与した時点から、値上がりが見込まれる財産
- 高収益の不動産を子に移しておきたいとき
- とにかく生前に遺産分割を完了させたいとき
- 子が若いうちに多額の財産を必要としているとき
築古アパートの土地は贈与せず、固定資産評価額が低い建物のみ贈与する
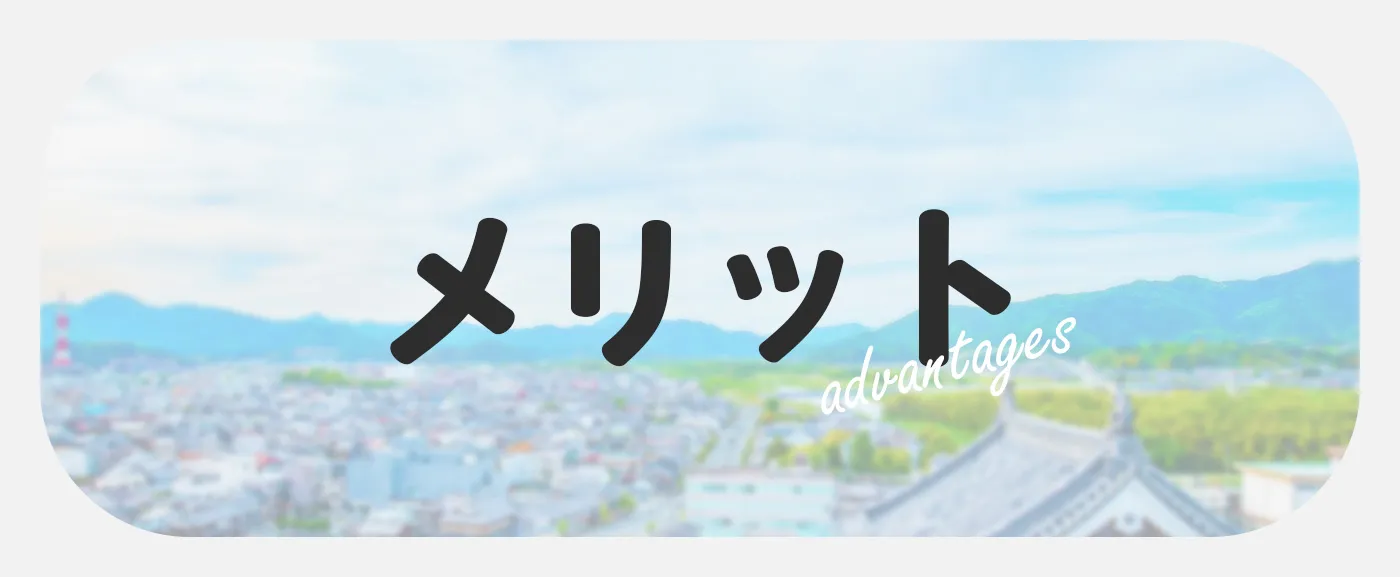
築古アパートを贈与したい場合は、建物のみを贈与するようにしてみてください。
土地の評価額は建物が古くなっても下がることはありませんから、アパートの建物を贈与することでメリットがあります。
贈与財産の評価額が低く抑えられる
建物は、年数が経過すればするほど評価額が下がっていきます。
築古アパートは総じて評価額が下がるため、贈与するときの贈与税や登録免許税などのコストを抑えることができます。
贈与後の賃貸収入を子に渡すことにより納税資金を準備できる
アパートの建物を子に贈与すると、賃料は親ではなく子の収入となります。
子が賃料収入を貯金することで、将来の相続税の支払い時に使うこともできます。
親の所得を減らし、子へ所得を分散できる
アパートの収入が親から子になるので、親の所得を減らすことができます。
相続財産が増えないことになり、相続税の負担も軽減できるでしょう。
築古アパートを生前贈与する際の3つの注意点と対策

築古アパートを相続する際には注意点もあります…。
今から紹介する注意点を全て確認してから、アパートの贈与を検討してみてください。
贈与後に入居者が変わると土地の相続税評価額が高くなることも
※一定要件を満たした場合、アパートの敷地200㎡まで評価額を50%下げることができる特例
これの対策として、オーナーと賃借人で直接賃貸借契約を結ぶのではなく、「不動産会社とのサブリース契約を交わす」という方法があります。
- サブリース方式では
- 不動産会社がオーナーと賃貸借契約を結び、その後不動産会社が賃借人と転貸借契約をします。
この場合、実際に住む人(転借人)が入れ替わっても賃借人自体は不動産会社のままなので、貸付用小規模宅地の特例の要件を満たすことが可能です。
築古アパートの生前贈与は負担付贈与に注意
- 負担付贈与とは
- 贈与を受ける受贈者側に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。
負担付贈与をすると、贈与税を計算する時の評価額が相続税評価額ではなく時価となります。
不動産の場合、時価の方が評価額より高い場合がほとんどで、贈与税の負担が大きく増えてしまいます。
築古アパートの敷金は負担付贈与となるため、敷金と同額の金銭の贈与が必要
アパートを親から子に贈与する場合、親が賃借人から受け取っている敷金に注意しなければなりません。
アパートのみを贈与してしまうと、敷金の返還時には子が自分の懐からお金を出すことになるので、負担付贈与とみなされてしまうのです。
ローンがある築古アパートの生前贈与は負担付贈与となる
アパートのローンも負担付贈与になります。
アパートローンが残っているアパートを贈与したいのであれば、ローン完済後に贈与を行うか、残債と同額の現金を併せて贈与する必要があります。
専門家の報酬、登録免許税、不動産取得税などの諸費用がかかる
贈与を行う際には、贈与税のほかにも次の費用が発生します。
- 専門家報酬:1物件あたり5万円~(目安)
- 登録免許税:固定資産税評価額×2%
- 不動産取得税:土地:固定資産税評価額×2分の1×3%
- 不動産取得税:建物:固定資産税評価額×3%
贈与契約書を作成する場合には契約書に貼り付ける印紙代もかかります。
築古アパートは、相続したほうが良いか贈与したほうが良いかの判断基準
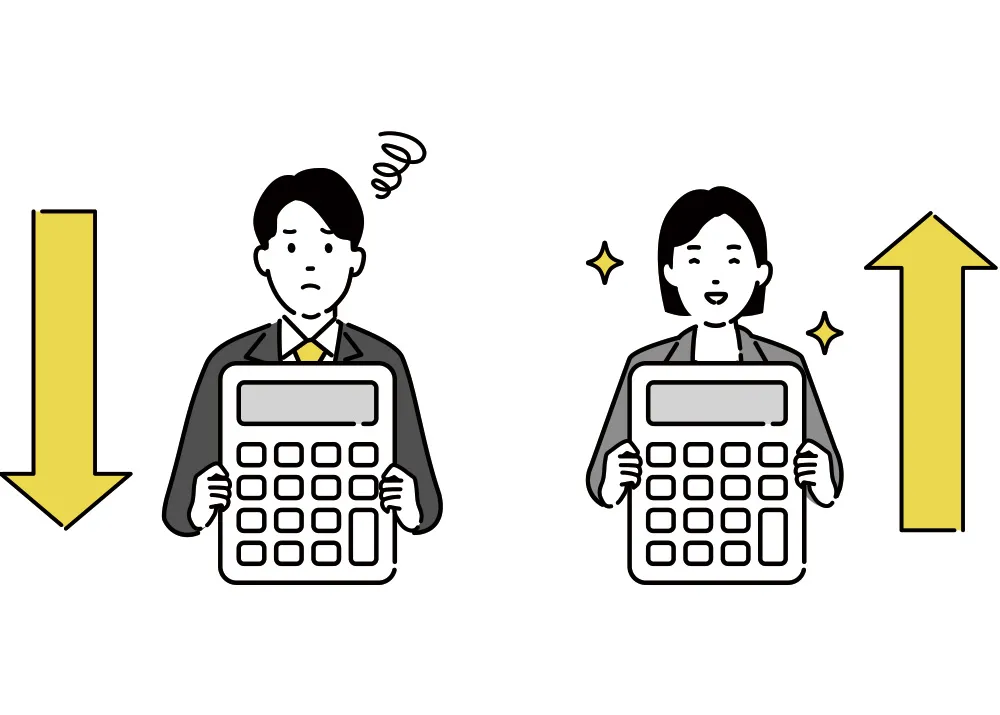
ここまでで、築古アパートの相続や贈与に関するあらましを説明してきましたが、結局アパートは相続と贈与のどちらがより適しているのでしょうか?
ここからはアパートの相続と贈与、どちらを行うべきかを決めるのに役立つ判断基準を紹介します。
築古アパートを相続したほうが良いケース
- 家賃収入が親の生活資金になっている
- 相続後にアパートを売却する予定がある
賃料収入が親の生活資金の場合にそのアパートを贈与してしまうと、親の収入がなくなってしまうためです。
また、アパートを売却する予定があるのであれば、相続後の方がお得になるケースもあるので、上記の場合には相続をおすすめします。
①安く相続で取得して高く売ることで現金を多く残せる
親の生前にアパートを売却すると、手元に残るのは売却した分の現預金で、現金のままだと相続税は高くなります。
また評価額が低いアパートを相続して、その後評価額以上の価格で売却すれば、手元により多くの現金を残すことができます。
②相続税を取得費に加算でき譲渡税を安くできる可能性がある
将来アパートを売却したときに発生する譲渡所得税は、アパートの売却益がその取得費用を上回っていた際に発生する税金です。
ですが、アパートの相続税を支払っていた場合、取得費加算の特例により、節税することができる可能性があります。
- 売買代金−(購入時の経費等+売却時の経費)=譲渡益(利益)
- 譲渡税=譲渡益 × 譲渡税率
取得費加算の特例を用いた場合、すでに支払ったアパートの相続税額を購入時の経費にプラスできますので、ある程度の節税ができます。
アパートの相続をしたらすぐに売却活動を行いましょう!
築古アパートの生前贈与を検討したほうが良いケース
当てはまる方は、生前贈与を検討すべきです。
- 親の財産が多いため、賃料収入を減らして相続税を下げたい
- 親を被保険者とする生命保険に加入して保険料を賃料収入から当てたい
- アパート経営を学んでおきたい
相続税を下げたい時や賃料収入を活用して対策を講じたい時は生前贈与を検討した方がよいでしょう。
そもそも築古アパートを引き継ぎたいかどうか

アパートの相続や贈与を考える以前に大事なことがあります。
それは子供がアパートを継ぎたいのかどうかです。
節税対策ばかりに気を取られていると、子供にアパートを引き継いだ後にトラブルが起こる可能性が高いです。
ここからは「アパートを子供に引き継ぐか、手放すかを考えるための判断基準」を紹介します。
不動産調査をして問題点と解決方法とそのコストを把握する
アパートの場合、以下の点を調査しましょう。
- 賃貸借契約書の内容、更新の有無
- 賃借人の属性、滞納者、悪意のある賃借人の有無
- 土地の測量の有無、境界点で隣地と争いがあるかどうか、越境物の有無
- 建物の躯体、アスベストの有無、増改築の履歴
これらの項目は、役所や現地で調査可能です。
問題を見つけた場合はその解決方法と必要なコストを割り出しましょう。
修繕履歴から将来必要そうな費用を予測する
アパートは古くなるにつれ、設備や配管などが劣化していきます。
設備の修繕費や配管の入れ替え費用を計算し、将来的にかかるコストを把握しましょう。
収入と支出のキャッシュフロー
確定申告等で収入と支出を算出しましょう。
- 収入とは
- 号室ごとに賃料・管理費、自動販売機や太陽光売電の収入など
- 経常的な項目(管理会社への委託管理費、インターネット回線料、火災保険料など)
- 突発的な項目(入退去時の原状回復、設備交換など)
修繕履歴や不動産の問題を解決するためのコストを考慮しつつ将来的な収支のシミュレーションを作ります。
そうして作られたキャッシュフローから、アパートを引き継ぐか、売却するかを判断すると良いでしょう。
まとめ
- アパートの相続や売却など今後について考え始めている
- 家屋を解体し、その土地を何かに活用したい
- アパートの管理会社を変えたいと考えている
- 空き家(空室)が増えて困っている
このような方は、ぜひ当協会にご連絡ください。
税理士、司法書士、弁護士といった相続や税金の専門家も所属しているので、「まずは電話だけで相談したい」という方もご活用ください!!
また、相続税の申告には期限があります。詳細はこちら→相続税の申告期限を過ぎるとどうなる?
- 現在、無料の空き家現地調査を実施中!
- 空き家のご状況や相談者様のご意向に合わせて、最短即日~3営業日以内に適切な解決策や厳選した事業者をご紹介しています。