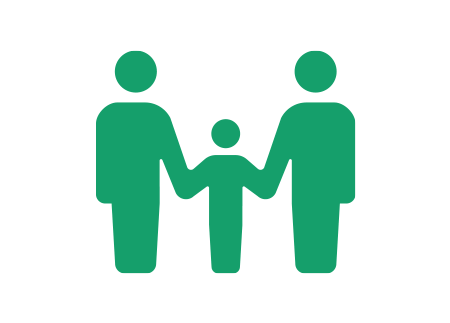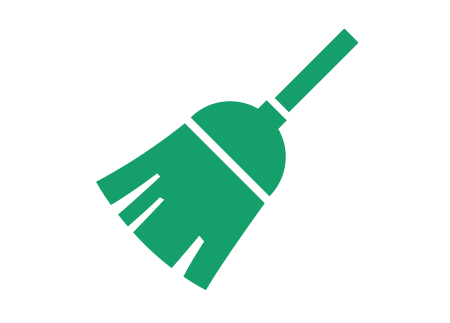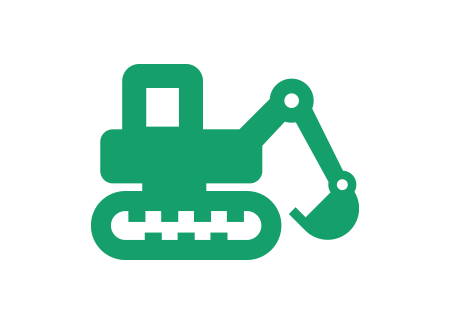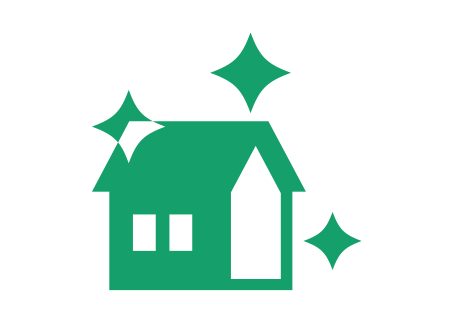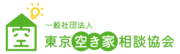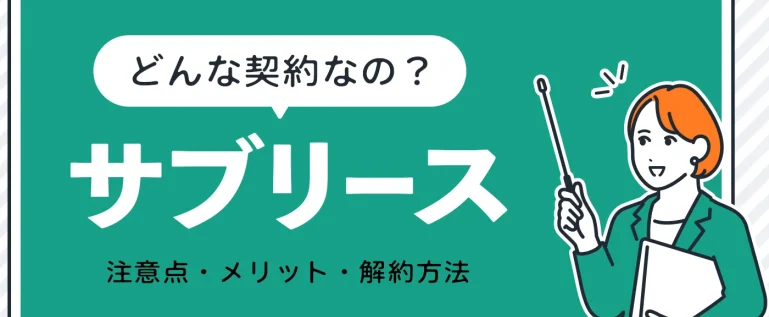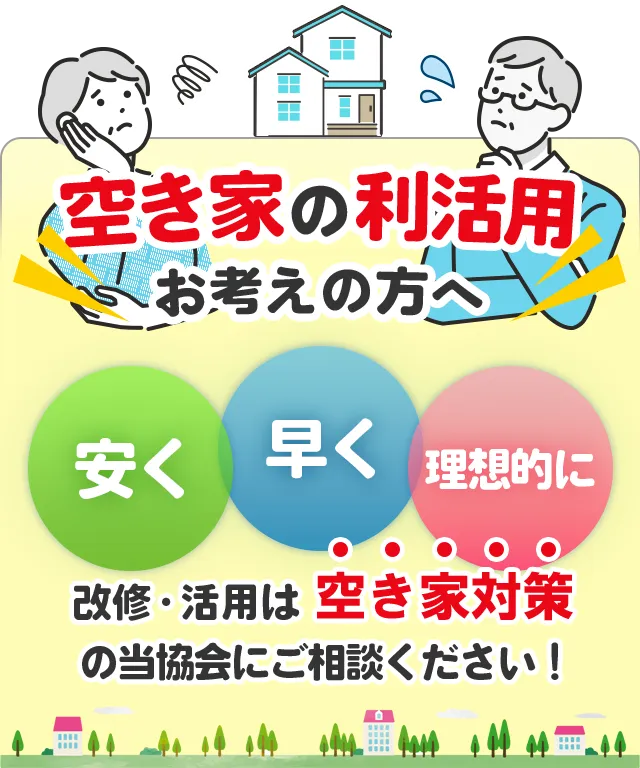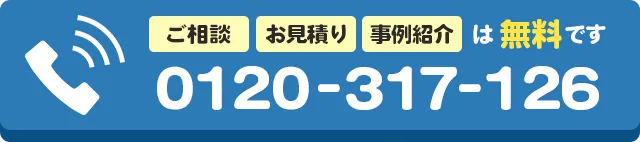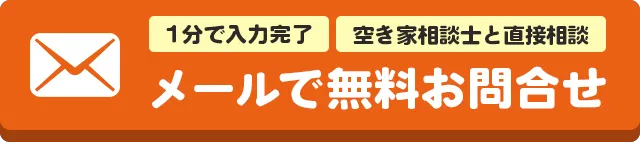不動産投資や賃貸経営にあたり、選択肢のひとつとして注目をあつめる「サブリース契約」。
便利な一方で、危険でトラブル多発という一面も。
サブリースはなぜ危険視されるのでしょうか?
今回の解説内容
- サブリース契約とは
- サブリース契約のメリット・デメリット
- サブリース契約の注意点
- サブリース契約を解約するための正当事由
サブリースとは?
- サブリース契約とは
- オーナーからアパートなどの賃貸物件をサブリース会社が一括で借り上げる契約です。
- サブリース会社は入居者へと転貸借、つまり又貸しして利益を得るのです。
また、マスターリースによって賃借した者が実際の賃借人に転貸することを「サブリース」という。
出典:三菱UFJ不動産販売
サブリース契約は危険?注意点を解説
それでは、オーナーが踏まえておくべき注意点はどのようなことがあるのでしょうか。
おもな注意点は以下の通りです。
- 賃料は下げられることもある
- サブリース事業者から解約されることもある
- リフォーム費用を負担することもある
この3点は、国土交通省も提示している「オーナー自らが十分理解しておく必要がある」注意点であり、サブリースにかぎらず、賃貸経営をするなら起こり得る落とし穴です。
とりわけ建物は、建設当初から劣化がはじまり、遅かれ早かれいずれは賃料は安くなり、多くのサブリース契約では、最低2年ごとに保証賃料の見直しがされますが、その際に減額を求められる可能性が出てきます。
- 景気の悪化
- 物件が周辺の賃貸ニーズと合わなくなってきた
- 競合物件が増えた
「家賃保証」という聞こえのいい言葉だけを捉えてしまうと、このような落とし穴が見えにくくなってしまいます。
これが、サブリースが危険視されるようになった要因のひとつです。
賃料を下げられることもある
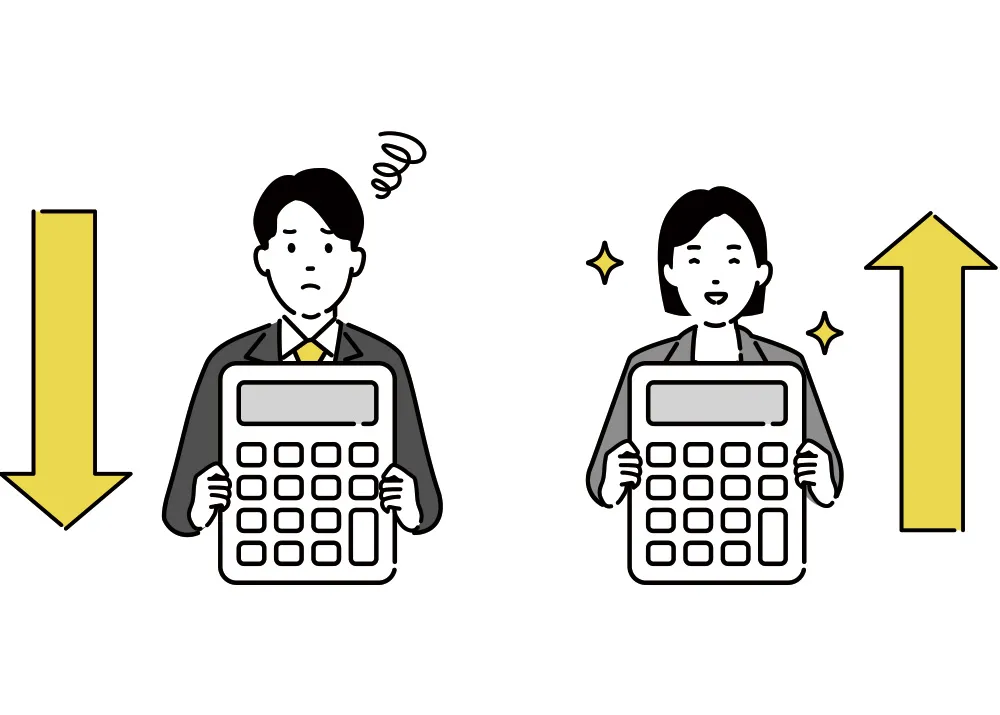
契約書には約定家賃がありますが、築年数が経ち入居率が悪くなるとサブリース会社の収益性が悪くなります。
このことによって、サブリース会社からすると空室分の負担となるのです。
- 景気の悪化
- 物件が周辺の賃貸ニーズと合わなくなってきた
- 競合物件が増えた
サブリース会社側はオーナーに対して、賃料の減額を請求してきます。
オーナーが減額請求に応じない場合、サブリース会社にはマスターリースの途中解約という手段があります。
契約書に記載されている家賃と差がうまれると、オーナーにとってもサブリース会社にとってもデメリットしかなくなります。
安定した収益が得られると思いサブリース契約をしました。
しかし実際には契約当初の賃料を長期にわたって約束してくれるわけではありませんでした。
サブリース会社から案内される際は「安定」「保証」「生活の足しになる」といった言葉があったが、安心したのも束の間。
結局、賃料の減額を求められたため安定した家賃収入を確実に見込めるわけではないことを知りました。
事業者からの解約
上記のように、オーナーが賃料の減額請求に応じない場合、サブリース会社からマスターリース契約の途中解約を求められることがあります。
反対に、オーナーからの途中解約については借地借家法によりほとんど認められることはありません。
借地借家法では貸す側よりも借りる側を守るしくみがあります。
このため、マスターリース契約でも同様に、物件を貸すオーナーよりも借りる側であるサブリース会社側の方が保護されるのです。
例えば、以下のような動きです。
- 新しい管理会社を見つけてサブリースでの賃貸事業を継続する
- 管理会社に管理を委託する
- 入居者と直接契約する
サブリースでの賃貸事業が継続できない場合は、空室分の家賃収入を失い、これまでの家賃が減るおそれがあります。
のしかかるリフォーム費用
このように頭を痛める方も多いです。
入居者の募集を含めた実質的な賃貸事業はサブリース会社が行なうため、物件の修繕計画など、入居促進関連の事業については、サブリース会社の主導で行なわれる方が多くあります。
これに対し、オーナーはサブリース会社が提案する修繕計画に反対できることは少なく、ほとんどの場合サブリース会社の意向でそのまま実施されます。
物件が古くなると、経年劣化で壁や水回りの設備などが壊れてしまうことがあります。
通常、これらの修繕が必要な場合、貸主が費用負担することが一般的です。退去時に借りた状態で返す必要があるため、入居者が原状回復費用の一部を負担しますが、経年劣化によるリフォームや交換費用はオーナー負担となる点には注意しましょう。
- 退去時の主な原状回復工事内容
- ハウスクリーニング費用
- フローリング、畳の交換費用
- クロス貼り替え費用
- 壁、ドアなどの破損部分の修復費用
- 水回りのパッキン交換費用
これら費用をだれが負担するべきかをめぐり、賃貸借契約ではオーナーと入居者間でトラブルがよく発生します。
このような問題を解決すべく、貸す側と借りる側の負担分を線引きするために国土交通省で定めたのが「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。
なお、利用するサブリース会社やサービスによっては、修繕費の一部を負担してくれる場合もあります。
手数料が負担になる
サブリース契約では、オーナーがサブリース会社に手数料(もしくは賃料差額分)を支払う必要があります。
相場は以下のようになっており、サブリース契約の方が手数料は高い傾向です。
- 相場:家賃の10~20%
- 普通委託契約の手数料は一般的に賃料の5~10%
このため、同じ賃料の物件であればサブリース契約の方がオーナーに入る収入は少なくなります。
さらに、敷金礼金、更新料はサブリース会社の利益です。
前述の原状回復工事や大規模なリフォームはオーナーが負担することが多くあるため、これらと併せて手元が残りにくくなるおそれがあります。
免責期間の存在
免責期間が存在するかも確認しておきましょう。
サブリース契約に空室時の賃料保証がある場合、この免責期間が設けられていることがあります。
免責期間とは
- 空室時の賃料を支払わなくてもよい期間のことです。
- 物件を契約してから募集をかけ、入居者が決まるまでの期間や退去後の数ヵ月間がこの期間に該当する場合があります。
この免責期間の間は、入居づけを行なうための期間として、管理会社は家賃保証をしてくれません。
通常この期間は1ヵ月~半年ほどで設けられています。この期間が設定されている場合、期間中はサブリース契約でも家賃収入を得られないため注意が必要です。
契約前に免責期間が設けられているか、ある場合はどのくらいの期間なのか確認しておきましょう。
サブリースのメリット
上記では注意点を上げましたが、賢く利用すれば賃貸経営の強い味方になってくれるサブリース契約。
メリットには、以下のようなものがあります。
- 空室、滞納リスクを回避し安定収入
- 管理事務はすべておまかせ
- 広告料、原状回復費の負担軽減
- 相続税対策にもなる
次項から詳しく解説します。
空室、滞納リスクを回避し安定収入
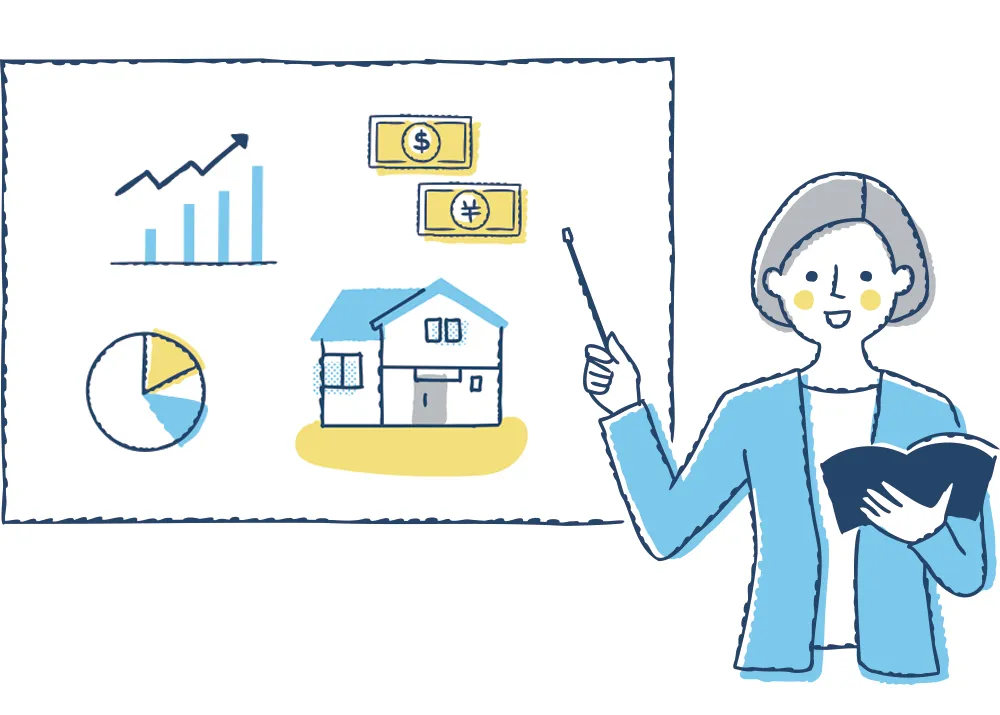
一般的な管理契約の場合、家賃収入が収益となるため、物件に空室がある=その分オーナーの収入は減ります。
これに対し、サブリース契約サブリース会社が物件をまるごと借り上げ、オーナーに賃料を支払うしくみになっています。
このため、オーナーは物件の空室の数にかかわらず、毎月一定の家賃収入を得られます。
また、賃貸経営においては入居者が家賃を支払えない状況になることがあります。
これも一般的な管理契約の場合、家賃が滞納した分の収入は当然減ることになりますが、サブリース契約ではこの場合も一定の家賃の支払いがされます。
- 物件にどれだけ空室や滞納があっても安定して家賃収入を得られる
管理事務はすべておまかせ
これもサブリースの大きなメリットです。
賃貸管理の関連業務をすべてサブリース会社におまかせで、手間と時間を省くことができます。
賃貸経営は片手間でできるものではありません。自分でする場合、ざっと以下のような多岐にわたる業務をすべて一人でこなす必要があります。
- 入居者の募集
- 入居者の契約更新の手続き
- 家賃管理
- 入居者や設備の管理
- 空室対策
- 設備の修繕工事の実施判断
- 入居中のさまざまなトラブルへの対応
これらには、ノウハウが必要です。
反対に、サブリースでは以下の業務を行ないます。
- 自ら経営に携わらずして賃貸経営が継続できる
- 初心者オーナーや海外に居住中などで賃貸経営に専念できない事情がある場合は、有力な選択肢
広告料、原状回復費の負担軽減
物件の賃貸経営において、入居者が入退去を行なう際、以下のように多くのコストが発生します。
- 入居者の入居が決まった際、例えばエイブルさんなどの仲介業者に支払う広告費
- 退去時に発生する部屋の原状回復費
入退去のたびにこれらの費用が発生するのは、オーナーにとって大きな負担です。
- サブリース会社が負担することが多いため、全額負担ではないものの費用の負担軽減ができる
相続税対策にも

サブリースで税金がどのように扱われるのか、気になる方も多いでしょう。
サブリースには相続税を抑える効果もあります。
物件のオーナーが亡くなって相続が発生すると、物件に対して相続税が発生します。
- サブリースが節税対策になる理由
- 税金の世界では、人に部屋を貸している=資産価値を下げると考えられているため、物件の入居率が高いほど物件の相続税が低くなります。
- したがって、サブリース契約においては、この入居率が100%(つまり満室)であるとして相続税の計算がされるため、相続税の節税対策が期待できるということです。
サブリースの解約は難しいのか?
解約がむずかしいといわれるサブリースですが、その理由について確認しておきましょう。
サブリース契約は、正当の事由がないとオーナーから解約できません。
借り手が強く保護される借地借家法
まずこれを押さえておきましょう。
サブリース契約はオーナーが貸主、サブリース会社が借主となるため、適用される法律が「借地借家法」です。
サブリースの解約が難しいといわれる理由はここにあります。
出典:借地借家法第27条
出典:借地借家法第28条
上記の条文がポイントです。
つまり、「正当の事由」がなければ、貸主であるオーナーからの解約ができないということです。
違約金は高額になる?
先述したような、賃貸経営の強い味方になってくれるメリットがある一方、物件の運営状況によってはサブリースを解約した方が収益が見込めるとして、解約を考える方もいるかと思います。
しかしながら、解約には高額な違約金がかかる場合もあるため注意が要ります。

サブリース契約には解約に対して違約金が設けられていることがあります。
違約金の相場としては月額の3~6ヵ月相当といわれていますが、中には1年分などという高額な場合もあります。
また、以下の場合などは違約金のほか、立ち退き料が必要なこともあります。
- サブリース会社が解約に応じない場合
- 「正当事由」が認められない場合
- 「正当事由」は認められたが、立ち退き料で補う必要がある場合
個々の事情により、違約金の額は変わりますが、契約条項に違約金が設定されている場合、高くつく可能性があります。
このような事態を避けるために大切なのは、契約内容を事前にしっかりと確認することです。
契約内容の確認が不十分だと、解約時に高額な違約金を請求されたなどの問題が起き、想定外の出費がおこることがあります。
契約内容に疑問点があればそのままにせず、契約前にきちんと確認しておきましょう。
正当事由で認められるケースとは?
- 老朽化などで解体の必要がある場合
- オーナー本人や親族などが物件を使う場合
- 生計維持のために売却の必要がある場合
- 再開発等やむを得ない理由がある場合
関連記事
老朽化などで解体の必要がある場合
建物の老朽化などで解体の必要がある場合、正当事由として認められる場合があります。
ひと口に「老朽化」といってもさまざまであり、抽象的な言葉になるため、具体的な内容を示す必要があります。
- 「老朽化」の判断に使われる「耐震診断」
- 地震大国である日本において、1981年(昭和56年)に「新耐震基準」が定められました。
- これに基づいて建てられた物件と、それ以前の「旧耐震基準」に基づいて建てられた物件では、いざ地震が起きたときの被害が大きく変わってきます。

現在の建築基準法では、地震に対して厳しい基準が定められているため、新築であれば耐震基準をクリアしていることが明らかですが、それ以前の「旧耐震基準」で建てた物件は「新耐震基準」を満たしていないものも多くあります。
入居者の生命や健康に大きなリスクをもたらし、明確な理由に基づいた「老朽化に伴う取り壊しの必要性」があると認められるのであれば、サブリース解約の正当事由に当たります。
物件が古くなって見栄えが悪くなったからリフォームしてきれいにしたい、といった理由では認められないため、注意してください。
比較的高い可能性があるのは、
オーナー本人や親族などが物件を使う場合
オーナー本人が自分で物件に住むなど、自己使用するために解約を申し出る場合、正当事由として認められる可能性が比較的高いです。
たとえば、以下のようなケースです。
- 海外に住んでいたオーナーが、帰国にあたり住居が必要になった
- サブリース契約を締結している物件とは違う物件に住んでいたが、何らかの理由があり住む家が必要になった
本人の経済状況にもよりますが立ち退き料を支払った上で物件を明け渡してもらうことは正当事由として認められやすい事情です。
これが、オーナー本人の自己負担ではなく、家族の使用となると必要度が下がり、話は変わります。
自己使用であれ家族の使用であれ、いずれにしても立ち退き料などの条件交渉は必要です。
生計維持のため売却の必要がある場合
オーナーが購入した物件の建築費など、ローンを組んでいる場合は毎月の返済があります。
サブリース会社からの保険賃料やそのほかの収入があるかぎりは生活とローン返済ともにやっていける可能性はありますが、サブリース会社からの保険賃料は年数の経過とともに下がっていくため、場合により資金繰りが厳しくなることもあります。
保証家賃を見直す年数など会社によりやり方は違いますが、何十年もずっと同じ金額のままではありません。
- 家賃収入が減ったことで、ローン返済やオーナー自身の生活そのものが苦しい、生活できないとなった場合生活維持のために物件売却が必要として正当事由として認められる可能性があります。
当初、サブリース物件による家賃収入でローンを払えるように計画したとしても、物件の修繕費など思いのほかランニングコストもかかるため、想定外の出費でせっかくの利益が圧迫されることもあるのです。
- 家賃収入が減る
- ローンが払えない
- オーナー自身の生活が立ちいかない
ともなれば、解約する正当事由として認めてもらった上で売却するしかありません。
再開発等やむを得ない理由がある場合
このほかサブリース解約の正当事由として認められるものに、以下があります。
- 行政による土地区画整理事業
- 市街地再開発事業
- 道路の拡張工事
といった、オーナー側ではどうしようもない理由により物件を売らなければならない場合
注意ポイントとしては区画整理により土地環境がよくなり、ゆくゆくオーナーが所有する土地の値段が高まる可能性がある点です。
また、区画の再開発がされる場合、行政から土地所有者に「都市計画補償金」が支払われます。
オーナーが将来的に大きな利益を手にする可能性が高くなることにより、サブリース会社からの明け渡し条件として、高額な立ち退き料を支払わないと解約不可能としていることもあるため、これも注意が必要です。
これは認められない。補足ポイントも押さえておこう
補足として、以下のような場合はサブリース契約の解約における正当事由としては認められません。
- 物件を少しでも高値で売却したい
- 物件の利回りを向上させたい
- 売却しやすい状態にしたい
これらはいずれも、オーナー側の金銭的メリットのみに徹した内容であり、借主であるサブリース会社側にとってメリットがありません。
貸主側の一方的な要望かつ借主にメリットが無い場合は、サブリース解約の正当事由として認められない可能性が高いのです。
失敗しないために。頼れるパートナー選びを。
今回の記事ではサブリース契約の注意点やメリット、解約方法を解説しました。
親から相続した物件が、建築当初からサブリース契約されていて、相続人である自分はそのままにして良いのかわからない。
サブリース会社から高額な改修費を請求されており、このままでは資産がマイナスになるのではないかと不安です。
当協会にはこのようなケースでお悩みの方も多くいらっしゃいます。
記事内で取り上げたように、重要なのは「サブリース契約の解約理由が正当事由に該当するかどうか」です。
正当事由として認められる解約理由、契約内容、借地借家法に基づいた借主の権利の強さなど、解約に際しては複数の要素を把握の上で手続きを進めていく必要があります。
その際、相談で負担が軽減することもぜひ思い起こしてください。
場合によっては手続きのすべてを自力で行ったがために損をし、「失敗した―!」となるおそれもあります。
そうならないために、各専門家と連携しており、業者へのお見積りやお断りまですべて代行する東京空き家相談協会へご連絡ください!