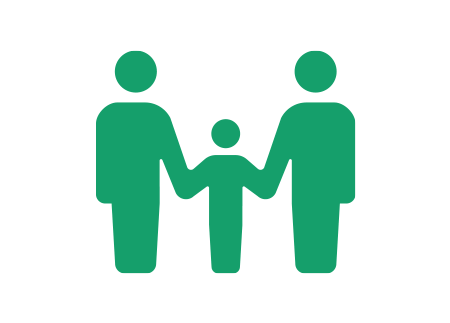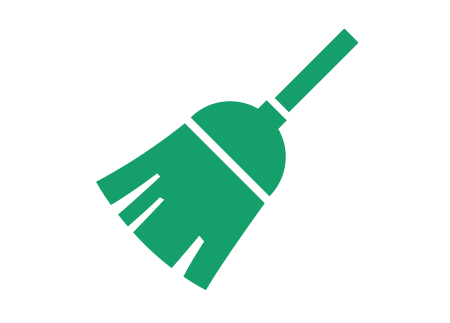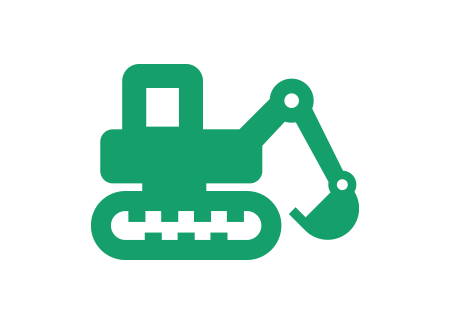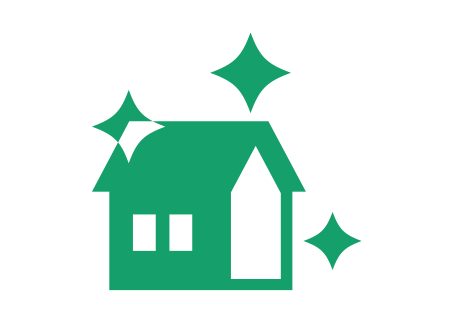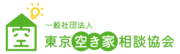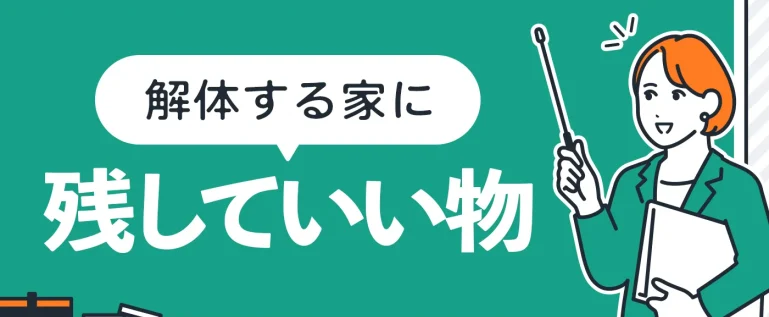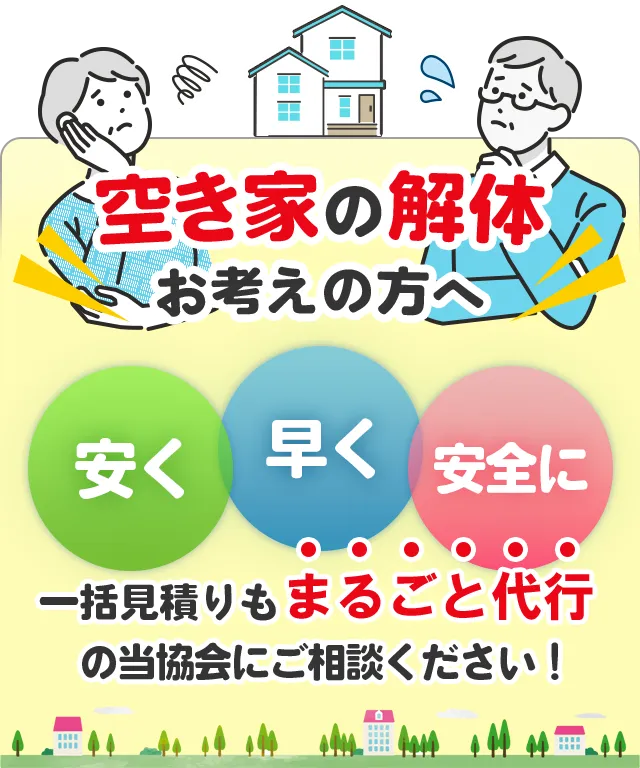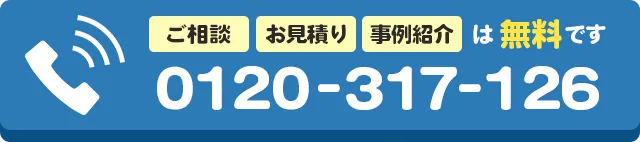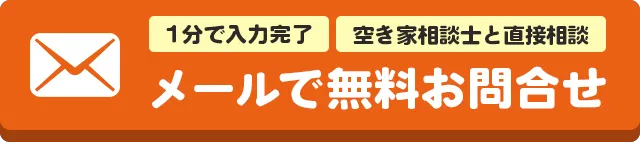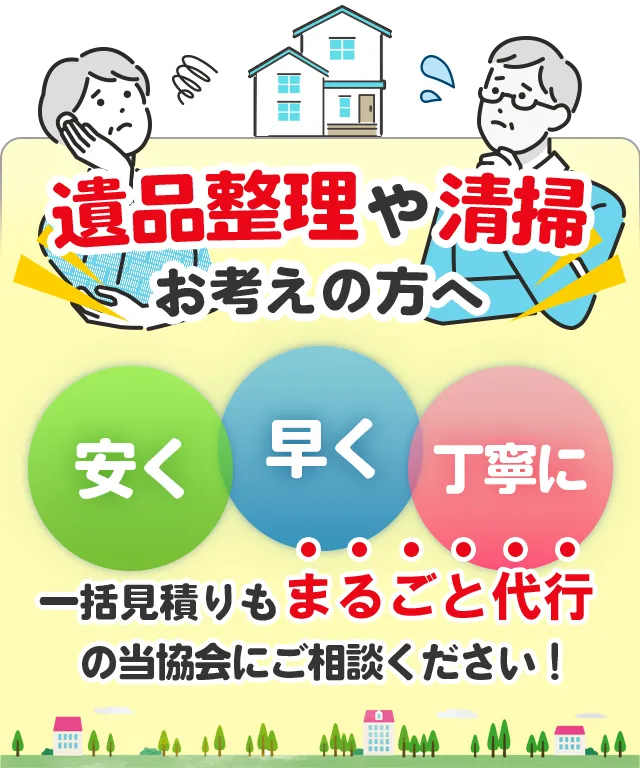解体する建物の中には、家具や私財がそのままになっているケースがあります。
そこで気になるのは、解体前に何から片付ければよいか、そしてそれにかかる費用ですよね。
すこしでもスムーズに片付け・解体を行なうために、今回は以下について解説します。
今回の解説内容
- 解体前にどのくらいまで片付けるべきか
- 解体する建物に残してもいいもの
- 処分費用が高くつくもの
- 解体業者に不用品処分まで依頼した場合の流れ
- 片付け業者に依頼する際の注意点
- 建物の解体前に忘れてはいけない届出手続き
解体前にどこまで片付いているのがベスト?

解体する前の建物の中の「家電や家具、家庭ゴミ」は、基本的に残しておいても問題ありません。
解体を始める前に建物内に残されたものは解体業者が片付けるためです。
その理由は、解体を始める前に建物内に残されたものは解体業者が片付けるためです。
しかし、あまりにも残置物がある状態ですと、以下のような影響があります。
- 解体工事の進行がスムーズにいかない
- 経済的負担がかかる
後々自分が処分することになり困ってしまう…ということがないよう、
- 建物内に残しても業者に処分してもらえるもの
- 業者が処分してくれない可能性が高いので自分で片付けた方がよいもの
を理解しておくことをおすすめします。
自分で建物の中のものを処分する方法
業者に依頼しないものや業者に対応できないものは、自分で処分しなければなりません。
自分で処分する場合には、以下のようにさまざまな手段があります。
解体前の家にある不用品を自分で処分する方法
- リサイクルショップに出す
- ネットオークションやフリマに出品する
- 行政の粗大ゴミ回収サービスを利用する
- 専門の買取業者に査定してもらう
- 地域の住民に無料で譲る
- 不用品の種類や状態によっては、フリマや買取業者で高く売ることができます。
- 具体的には、家電・電子機器や、ブランド品、レンズや三脚を含めたカメラやベビー用品などです。
- 高価査定を受けやすいものの特徴は付属品がついていたり綺麗な状態であることや、シーズン中のものです。
自分で処分する方がお得になるケースもあるため、自分で処分するか迷った時は、費用面も含めて業者に相談してみましょう。
解体する建物に残していいもの

建物内に施工前に、業者が建物内を片付けるとはいえ、すべてを残していいわけではありません。
「解体する建物内に残しても良いもの」として、以下の2つをご紹介します。
- 木製・金属製の家具
- ケーブル類
木製・金属製の家具
「木製・金属製の家具」は建物内に残しておいても問題ありません。
理由は、木造の建築物を解体する際に、まとめて家具も壊すことができるためです。
また金属製の家具は売却してもらえる場合があります。
解体中に出る鉄くずやアルミサッシなどの「金属スクラップ」とともに回収され、売却してもらえる場合があります。
したがって、木製・金属製のイスやタンス、照明器具は業者のサービスで処分してもらえる場合があるため、残しておいても良いです。
ケーブル類
パソコンやコンセント周りの「ケーブル類」も、残しておいても良いものです。
業者により回収されたケーブル類は「電線買取専門業者」へ売却され、売却できた分は解体費から値引きしてもらえます。
そのため解体費を安くしたいのであれば、ケーブル類の処分は業者に任せるのが良いでしょう。
建物の解体前に片付けておくべきもの

以下のように、解体予定の建物内外に残しておくべきでないものもあります。
- アルバムやぬいぐるみなどの思い出の品
- 家電・家具
- 家庭ごみ
- 雑草
片付ける時間がなかなかとれず、最低限の片付けに済ませたい場合は次項をご確認ください。
アルバムやぬいぐるみなど思い出の品
勝手に捨てられることで家族内でトラブルに発展することもあります。
家族と思い出を振り返りながら片付けることをおすすめします。
家電・家具
テレビやエアコン、掃除機などの「家電」は業者が処分対応していないケースが多いです。
家電リサイクル法については、こちらで詳しくご説明しています。
木製・金属製以外の家具は、自分で片付けるべきです。
とくにガラス製の家具は業者に処分を依頼すると高くなる傾向にあります。
家庭ゴミ
紙類や生ゴミ、ペットボトルなどの「家庭ゴミ」も許可証を持っていない業者には断られる可能性が高いため、自分で片付けておくと良いでしょう。
雑草
建物を解体する前に見落としがちなのが「雑草」です。
量が多かったり奥深くまで根付いていたりする雑草の処理は相当な手間がかかるため、業者に処理を依頼すると費用負担が大きくなります。
解体費用を抑えるためにも、敷地内に雑草が生えている場合には自分で抜いておくことをおすすめします。
解体業者が建物内外のものを処分するためにかかる費用相場
不用品処分の依頼を検討した時に、やはり気になるのが費用面ですよね。
以下が「解体業者が建物内のものを処分するためにかかる費用相場」です。
| 木くず・粗大ゴミ・紙くずなどの混合廃棄物 | 7,900〜13,000(円/㎥) |
|---|---|
| 金属くず(鉄くず・非金属のみ) | 4,000(円/㎥)〜 |
| ガラス・陶器類 | 25,000(円/㎥)〜 |
| 瓦・レンガ | 18,000(円/㎥)〜 |
| 雑草 | 42(円/kg)〜 |
例えば木造2階建て住宅を取り壊す際には、木くずだけでも「約5〜8㎥」もの廃棄量となり、「10万円」近くかかります。
そのため処分費用を安くするためには、できる限り自分で処分することをおすすめします。
建物の中のものを残したままにするメリット
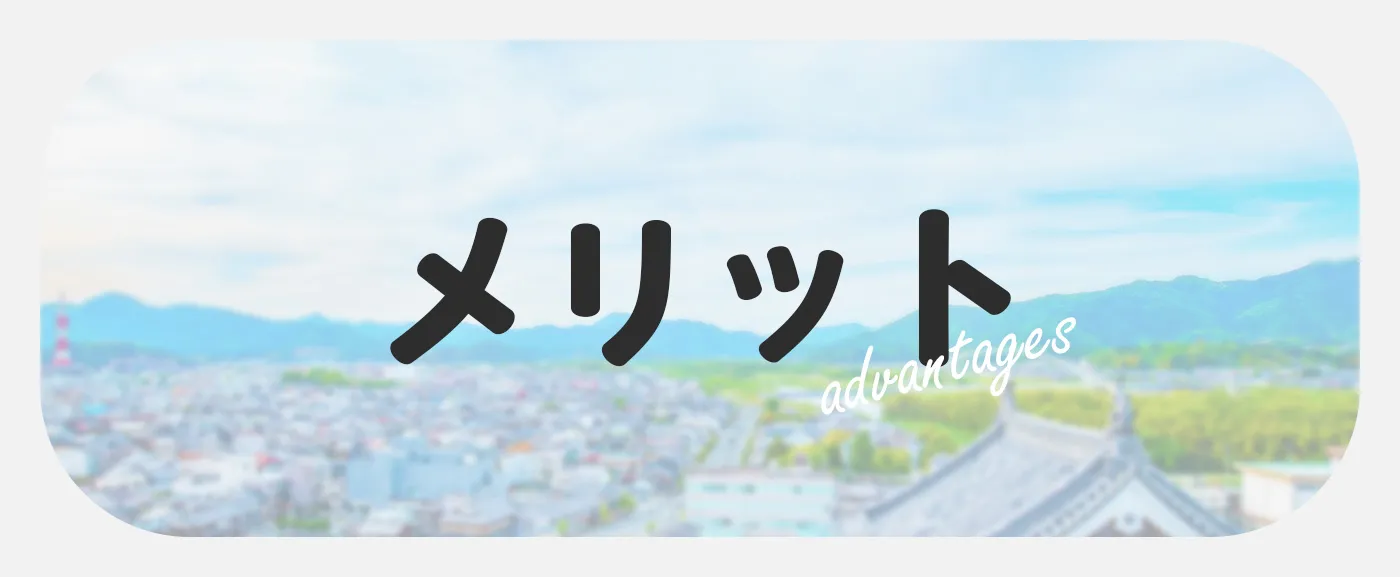
片付け費用を支払ってまで、業者に不用品処分を依頼するメリットは以下の通りです。
- 自身の片付け時間を節約できる
- 解体費用に還元してもらえるケースもある
次項よりそれぞれ解説します。
自身の片付け時間を節約できる
思い出がつまっている実家やゴミにあふれている空き家など、ものが多い家の片付けは大変です。
実家や空き家が遠方にある場合は特に、片付けのために移動時間や手間をかけるのは大変ですが、業者に依頼することによってその負担もカットできます。
解体費用に還元してもらえるケースもある
家財や解体で発生した廃棄物を業者がリサイクルして戻ってきたお金は、解体費用に還元してもらえるケースもあります。
片付けとリサイクルを同時に行なう業者もいるため、リサーチしてみることもおすすめします。
とは言っても、あまりに業者が多くどのように厳選すればいいかわからなくなる方も多いでしょう。
建物の中のものを残したままにするデメリット
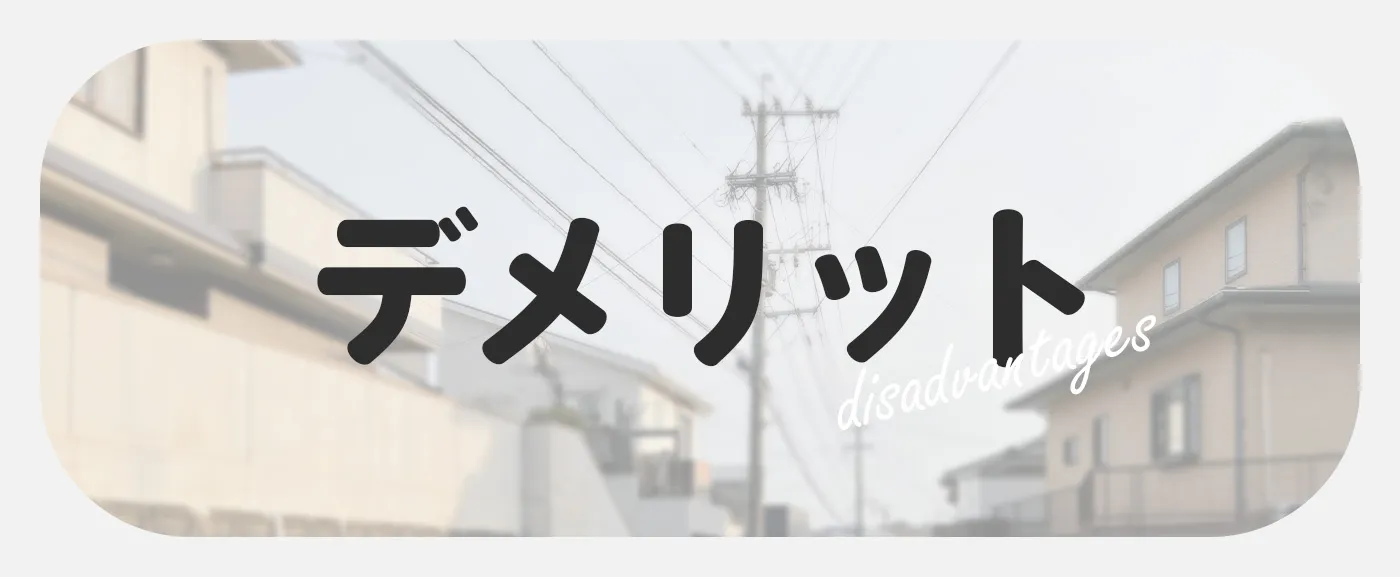
建物内にものがあるまま解体を依頼する場合、デメリットもあります。
デメリットもふまえて、片付けを業者に依頼するか検討しましょう。
- 自分で処分するよりも割高になる
- 片付ける分の工期が追加される
- 大切なものも処分される
ひとつずつ解説します。
自分で処分するよりも割高になる
一般ゴミの処分・運搬許可がない業者に依頼すると、別の専門業者を介して処分する必要があるため「仲介料」が発生してしまいます。
そのため自分で一般ゴミの収集日に出しておけば「無料」で捨てられるゴミも業者に依頼すると「有料」になるため、自分で処分するよりも割高になるデメリットがあります。
片付ける分の工期が追加される
解体する建物の中を清掃したりゴミを分別・処分したりするための工期は、一般的に「1日以内」
解体する建物の中を清掃したりゴミを分別・処分したりするための工期は、「1日以内」が一般的です。
ただし建物内に残っているものが多いほど事前清掃の工期が追加されるためご注意ください。
そのため、自分で片付けておくことをおすすめします。
大切なものまで処分されてしまう
解体前に片付けたいものがある場合、解体業者に相談のうえ解体スケジュールを決めましょう。
解体業者による建物内外に残された残置物・廃棄物処分の流れ
悪質な業者を避けるために、不用品や産業廃棄物の処理手順を正しく理解しておきましょう。
以下の表にて、「解体業者による建物内外に残された残置物・廃棄物処分の流れ」を紹介します。
| ❶解体前のヒアリング | 施主が柱や建材、付帯物などを残したいかどうか業者が確認 |
|---|---|
| ❷事前清掃 | 建物内のものが何もない状態にするため、施主が残した不用品の分別や清掃を行なう |
| ❸家本体の解体 | 家を解体すると同時に、木製の家具やガラス製品を一緒に壊す |
| ❹廃材の収集・分別 | 建物の解体で発生した木くずやコンクリート片、ガラスなどを収集し種類ごとに分ける |
| ❺廃棄物を中間処理場へ運搬 | 集めた廃棄物をトラックで専用の処理場へ運搬する |
解体業者により中間処理場へ運搬された廃棄物は、焼却加工を経て最終処分場で埋立等の処理が行なわれます。
廃棄物処分に関連するトラブルに遭わないようにするためには、事前清掃や解体後に業者が適切に分別しているかどうかを確認すると良いでしょう。
建物内に残したものを業者に処分してもらう際の注意点

業者に建物内のものを処分してもらううえで、いくつか注意すべきポイントがあります。
ここでは「建物内に残したものを業者に処分してもらう時の注意点」について、以下の3つを紹介します。
- 処分可能か事前に確認する
- 処分されては困るものを伝える
- 処分費・リサイクル費が安すぎる業者に注意
処分可能か事前に確認する
解体業者によっては不用品の回収や処分を受けていない場合もあるため、処分可能かどうかを事前に確認しましょう。
特に家庭ゴミは「一般廃棄物の収集運搬許可」を持った解体業者しか扱えませんのでご注意ください。
処分されては困るものを伝える
処分されては困るものがある場合は、「あとで取りに来る予定がある」といったようにあらかじめ業者に伝えましょう。
ただし決められた工期スケジュールを変更することは難しいため、解体業者に依頼したあとは必要なものを早めに引きとることをおすすめします。
処分費・リサイクル費が安すぎる業者に注意
相場よりも極端に「処分費・リサイクル費が安すぎる業者に注意」しなければなりません。
- 不法投棄をして処分費を浮かせている
- 高額な料金を追加費用として請求してくる
- 上記のような悪徳業者可能性がある
複数の業者の比較時に処分費が安すぎる業者があれば、「自社リサイクルをしているため還元できるから」などの安くできる正当な理由を聞いておくと安心です。
建物の解体前の届出手続きも忘れないように!
本ページでは建物を取り壊す前に残してはいけないものをご紹介しました。
しかし、不用品・ゴミなどの「もの」だけではありません。解体前には「ライフラインの停止手続きや関係各所への申請書類」も忘れずに進めましょう。
家の解体前に必要な手続き
- 解体工事届出
- 道路使用許可申請
- 水道を除くライフラインの停止
- <近隣説明会
ひとつずつ解説します。
解体工事届出
- 解体工事届出とは
- 解体工事をすることや廃材を所定のルールで処分することなど自治体に申告する書類のことです。
- 「建設リサイクル法」により、床面積80㎡以上の家を取り壊す時に、着工7日前までの提出が必要になります。
提出の義務は施主にあるものの、一般的には業者が代行するケースが多いです。
委任状の作成のみで済むため、業者に任せるのがスムーズでおすすめです。
代行費用節約のために自分で申請する場合、自治体の窓口に以下を持参します。
- 分別解体等の計画書
- 案内図
- 設計図または写真
- 配置図
- 工程表
道路使用許可申請
- 道路使用許可申請とは
- 解体工事では、家の前に重機やトラックが停まるため、道路交通法にもとづいて「道路使用許可申請」が必要です。
- また、数日間にわたって道路に足場など置く場合「道路占有許可申請」をする必要があります。
提出の義務は施工業者にあり、着工2週間前までに警察署に申請します。
施主がすることは特にありませんが、申請費用がかかるかどうか見積もりを確認しておくことが大切です。
申請費用の節約のために自分で申請する場合、業者に伝えたうえで以下の書類を用意しましょう。
- 道路の使用場所あるいは付近の見取り図
- 道路を使用する施工の内容がわかる書類
- 設計図および仕様書
かえって割高になるおそれもあるため、どのような手続きを踏んでいくか事前に確認しましょう。
水道を除くライフラインの停止
そのため、着工前に停止手続きが必要です。各契約会社などの窓口に連絡して、停止したい日にちを伝えましょう。
ブレーカーなどを撤去するために直前になって連絡すると解体の着工に間に合わないおそれがあります。
明確な期限はありませんが、約2週間前までには連絡しておくと安心です。
解体工事は、粉塵が舞うのを避けるために水を撒きながら施工します。
そのため、水道は止めずに残しておく必要があります。
また、施行の水道代の負担についてはあらかじめ施工会社に聞いておきましょう。
近隣説明会
解体工事では、振動や騒音、粉塵、道路使用などによって近隣に迷惑をかけてしまいます。
最低限、両隣や裏側、向かいの家には挨拶をし、トラブル発展を未然に防ぎましょう。
- 近隣説明の範囲や方法が定められている自治体もあります。
- 東京都世田谷区の場合は令和7年4月に届出方法に変更となり、以下の規定があります。
- 工事の7日前までに解体工事のお知らせ標識を設置
- 工事の3日前までに工事内容を近隣に説明
- 工事の1日前までに報告書を区窓口へ提出
- 建設リサイクル法届出書別表備考欄への標識の設置・近隣説明の実施状況について記入する(電子申請可)
近隣説明は施工会社が代行してくれることも多いものの、施主も同行して顔を合わせておくことによって誠意が伝わりやすいでしょう。
続いて以下は、解体後に手続きが必要なものです。
家の解体後に必要な手続き
- 建物滅失登記申請
- 水道の停止
建物滅失登記の申請については、以下で詳しくご紹介しています。
関連記事
解体前に家のものを捨てるか迷っている場合は…
建物内のものを残したままにするか、それとも自分で捨ててしまうか迷った時は、解体業者に相談しましょう。
ハウスメーカーや不動産会社や工務店などにも不用品や廃棄物に関する相談は可能です。
また、建て替えの際に工務店に依頼すると、下請けの解体業者とのコミュニケーションがかみ合わず大事なものが許可ないまま処分されてしまう可能性もあります。
解体業者は、自社で不用品や廃棄物を回収・処理していることも多く、処分方法や流れをよく理解しています。
後悔しないためにも、不用品処分もまとめて行なえる解体業者に直接委託すべきです。
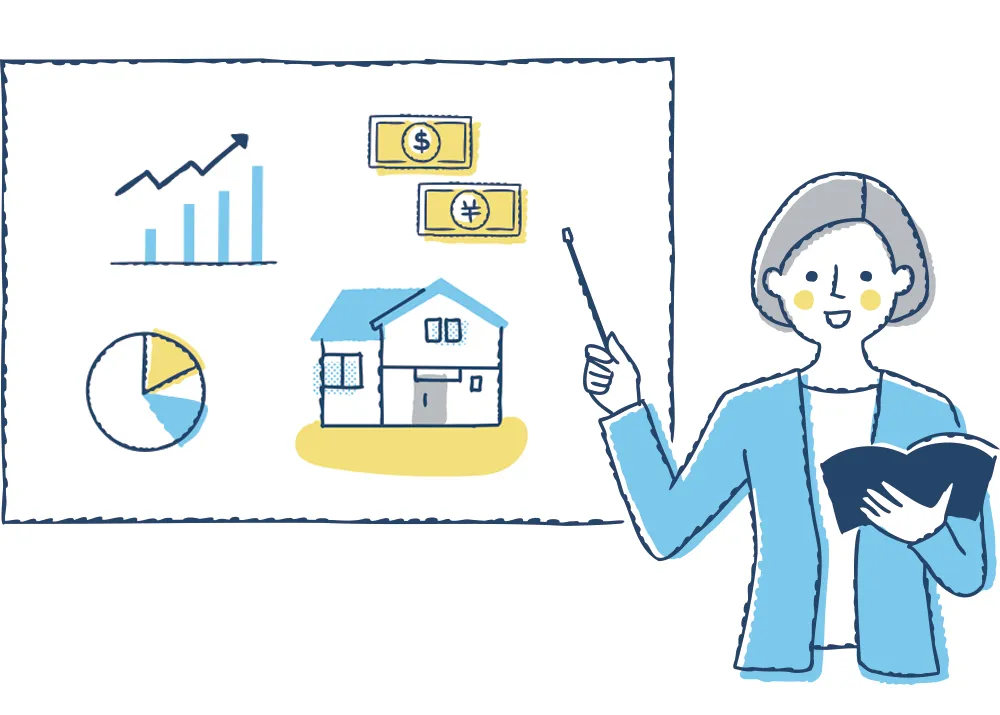
当協会では不用品回収・処分まとめてできる解体業者 数百社と連携しています。
- 解体前に片付けもしてほしい
- 安くて良い解体業者を厳選してほしい
- 片付けや解体にいくらかかるか一括見積もりしたい
すこしでもこのようにお考えの方は、ご連絡お待ちしております。
- 無料相談&現地調査実施中!
- 当協会では数百社の専門業者と連携しています。
- ご連絡いただければ最短即日~3営業日以内に適切な解決策やお困りごとに精通した専門業者を厳選してご案内しています。