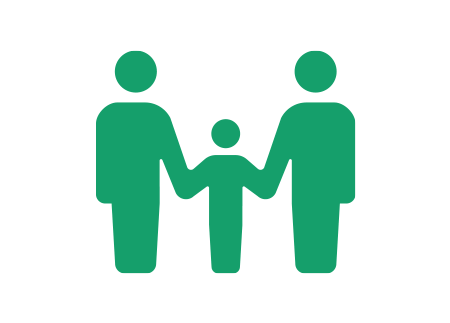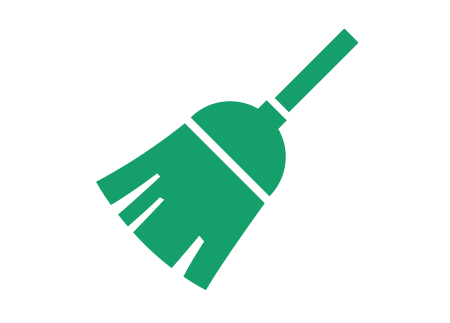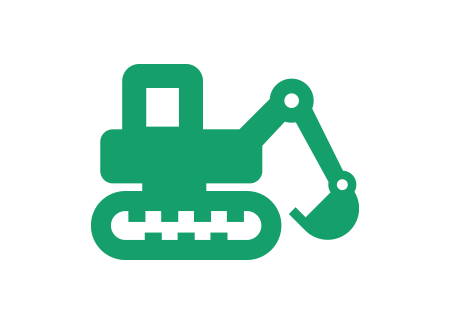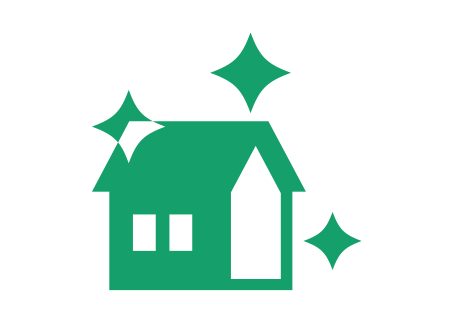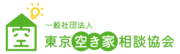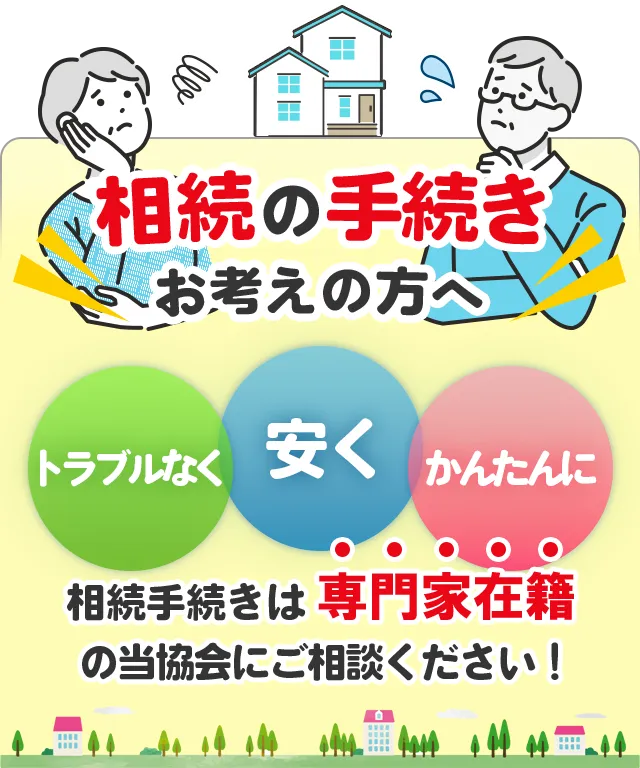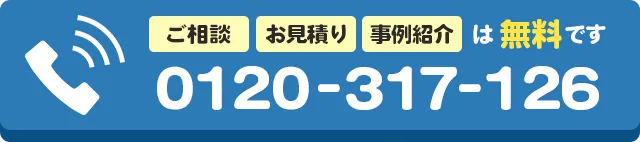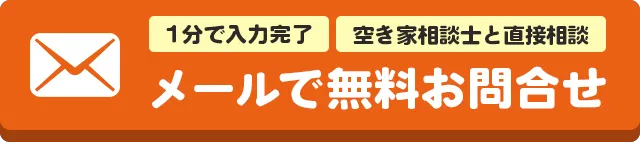親の遺産相続というと、こんな風に思う方もいるかもしれません。
ですが、借金などの負の財産も引き継ぐのが相続です。
- 自分の意に反して他人の債務を負わされる法律はない
- 不動産や預貯金など財産がある人にだけ関係がある
相続関連で悩ましい問題といえば「親の借金は相続放棄で回避できるのか」「その後誰が払うのか、どうなっちゃうのか問題」。
相続をすると債務も引き継ぐことになり、自分の債務として支払う義務を負うなどたまったものではありません。
今回の解説内容
- 相続放棄した負債がどうなるのか
- 借金の回避方法
- 回避できないケース
相続放棄後、どうなる借金返済義務
はじめに、ある債務について誰がその負担を負うかの原則ですが、債務の支払い義務は債務者しか負いません。
よく「親の借金を肩代わりさせられた!」といった嘆きを聞くことがありますが、法律上は支払う義務は一切ありません。
そんな風に言われますが、連帯保証人は保証債務という債務を債権者と契約を結んで負っているため、正しくいうと自分の債務として支払う義務があります。
親などの負債もこの理屈からすると払う必要はないものの、「相続」が発生すると事情が違ってくるということです。
そもそも「相続」とは
人の死亡によって生じる財産の移転のことをいいます。
- ある人は物の所有権を持っている
- 誰かに対して何かをしてもらう権利(債権)がある
- 誰かに何かをしなければいけない義務(債権)を持っている
| 家などの不動産を持っている | 不動産に対して所有権を持っている。 |
|---|---|
| 銀行に預金をしている | 銀行に対し、「預けているお金を返してください」という債権がある。 |
| 人からお金を借りている | 返済義務である債務がある。 |
つまりは、債務者であるという状態も相続人に移るわけです。
この債務の移転により、相続人は「自分の債務」として借金などを返済する必要があるということです。
相続放棄の注意点
相続放棄をすると、借金の返済義務がなくなります。
相続放棄とは被相続人(財産を遺して亡くなった方)の財産を引き継ぐ「相続人」の立場そのものを放棄する行為だからです。
- 一度相続放棄すると撤回できない
- 不動産や預貯金などのプラスの遺産も相続できなくなる
- 相続放棄ができない場合もある
- 被相続人名義の金融機関からの借り入れ
- 被相続人が滞納していた税金や社会保険料
- 被相続人の事業による借金(買掛金、各種未払金を含む)など
- 被相続人に支払い義務のあった損害賠償金
- 被相続人名義の各種ローン
(住宅ローンには「団体信用保険」がついており、名義人死亡時に支払い義務がなくなることも多い)
団体信用保険について
- 団体信用保険とは
- 略称「団信」と呼ばれ、住宅ローンの返済中に契約者が死亡や高度障害状態など万一の事態になったとき、住宅ローン残高がゼロになる保険のことです。
住宅ローンの契約者に万一のことがあったとき、家族や家を守ることができる保険というわけです。
未加入の場合、家族に大きな負担を残すことになるため、家の購入にあたって団信への加入は重要といえます。
相続放棄後、借金は誰が払うんだ問題
次に、相続放棄後の借金返済義務の行方についてですが、まず相続放棄したからといって借金自体がなくなるわけではありません。
相続人のうちの誰かが相続放棄した場合、借金の返済義務はほかの相続人に移ることになります。
通常の相続では、相続人が複数人いる場合、相続される借金の金額は人数にしたがって分割されます。
しかし、誰か一人の相続人が相続放棄すると、ほかの相続人の相続割合が増えて借金の負担額が増えたり、次の順位にあたる相続人が返済義務を追ったりします。
法定相続人が全員相続放棄した場合
相続人が全員相続放棄した場合、借金の連帯保証人が支払い義務を負うことになります。
亡くなった親の子どもが親の借金の連帯保証人になっていた場合、相続放棄をしても借金の返済義務はなくなりません。
相続放棄には連帯保証人の立場を返上する効力はないからです。
連帯保証人はデメリットだらけ
連帯保証人になる=主債務者(お金を借りた人)と同じ責任を負うことになります。
よく言われるように、結論から言いますと連帯保証人になるメリットはありません。むしろリスクを伴います。
連帯保証人として請求を受けた場合、原則として支払いを拒否することはできません。
連帯保証人になる=人の借金を一緒に背負っていることと同じですので、多大なリスクとなります。
以下の場合、「相続財産管理人」が選任されます。
- 相続人全員が相続放棄をした上で連帯保証人がいなかった場合
- 連帯保証人が返済不能(継続して支払いや返済をする能力がない状態)で自己破産をした場合
相続財産管理人について
- 相続財産管理人とは
- 債権者(被相続人にお金を貸していた人)が家庭裁判所に申し立てた場合などに選任される弁護士です。
- 被相続人の財産を調査
- プラスの財産があれば、それらを清算して債権者に配当の手続き
- 債権者への返済分を配当後も残っている財産があれば、国庫に帰属させる(国の所持となる)の手続き
借金の相続権の範囲
借金を含めた相続財産の相続権を持つ人を「法定相続人」といい、民法によりその範囲が定められています。
- 順位が上の法定相続人がいない
- 全員が相続放棄をした
被相続人が遺書を遺している場合は、ここで解説する法定相続分よりもその遺言内容が優先されます(民法964条)。
配偶者は必ず相続人になる
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人となります。
民法により、亡くなった人の配偶者(夫または妻)は常に相続人になると定められています。
また、ほかにどれほど法定相続人がいたとしても、配偶者がいる場合は相続財産を必ず配偶者と分割することになります。
(配偶者は相続放棄ができないという意味ではありません)。
内縁関係の人に財産を遺したい場合
配偶者は相続開始時に存在していれば、常に相続人になります。
ただし、正式な婚姻関係にある配偶者(法律婚をしている配偶者)に限られるため、内縁関係の夫や妻、事実婚のパートナーといった人は相続人にはなれません。
どれほど長いこと夫婦同様に暮らしていようとも、法律上の届け出を済ませていない場合、相続人として認められません。
もし内縁関係の人に財産を遺したい場合は、遺言を遺す必要があります。
子ども、孫
相続人になれるのは、「配偶者+血縁関係にある人」です。
ですが、配偶者以外の相続人には優先順位があります。
亡くなった人の子どもや親、兄弟姉妹には、民法により相続人になれる順位が定められており、第1~第3順位まであります。
ポイントは、第1~第3順位のうち順位の高い相続人がいた場合、順位の低い人は全く財産をもらえないということです。
被相続人に子どもがいる場合、相続の第一順位が子どもです。
| 配偶者 | 2分の1 |
|---|---|
| 子ども | 2分の1 |
| 複数人の子どもがいる | 何番目の子どもかは関係なく等分 |
代襲相続について
たとえば、被相続人の子どもがすでに亡くなっているが孫が存命という場合、父母や兄弟姉妹は財産をもらう権利がありません。
- 代襲相続とは
- 子どもがすでに亡くなっていてその子(被相続人の孫)がいる場合、子どもに相続されるはずだった財産は孫に相続されます
両親、祖父母
第二順位は両親や祖父母です。
被相続人に子どもがいない、もしくは子どもが全員相続放棄した場合、被相続人の両親や祖父母が相続人になります。
| 親と祖父母両方がいる | 被相続人と世代が近い親の方が優先されて相続人となる |
|---|---|
| 配偶者と親や祖父母が相続人である | 法定相続分は配偶者が3分の2、親や祖父母が3分の1 |
| 相続人となる親、祖父母が複数人いる | 3分の1の相続遺産がさらに等分される |
兄弟姉妹、甥・姪
第三順位は兄弟姉妹や甥・姪です。
被相続人に第一、第二順位にあたる続柄の人がいない、もしくは全員相続放棄をした場合、被相続人の兄弟姉妹が相続権を持ちます。
| 兄弟姉妹が亡くなっている | 代襲相続で相続人の甥・姪に当たる人が相続人になることもありる |
|---|---|
| 相続人が配偶者と第三順位の相続人の | 法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1 |
| 複数人の兄弟姉妹がいる | 4分の1の相続遺産がさらに等分される |
借金の相続放棄ができない場合も
相続放棄により相続人は借金の返済義務から逃れられますが、以下の場合相続放棄ができないこともあります。
- 被相続人が存命中の場合
- 相続財産を使った・処分した場合
- 手元に相続財産を置いておきたい場合
- 相続発生を知ってから手続きをせず3か月の期限が経過した場合
- 借金を一部でも返済した場合
被相続人が存命中の場合
現在の日本の法律では、被相続人の存命中に相続放棄をすることはできません。
相続放棄は被相続人が亡くなってからでしかできないことになっており、相続放棄を宣言する念書や契約書を作って残したところで無効とされてしまいます。
つまり、あらかじめ借金があることが分かっている場合でも、被相続人の存命中に相続人が借金ごと相続放棄をすることは不可能です。
存命中に相続放棄できない理由
できないことになっている理由は、相続人の平等性を担保するため、生前の相続放棄についての規定を設けていないからです。
被相続人やほかの相続人から相続放棄を強いられた場合、生前に手続きができることになってしまうと、民法の相続制度の根本から覆されることになり、相続人に財産を平等に分けることができなくなってしまうからです。
したがって、原則的に相続放棄も含めた相続関連の手続きは、被相続人が亡くなってから行うことになっています。
相続財産を使った・処分した場合
- 単純承認とは
- 亡くなった被相続人が遺した財産を、プラスの財産であれ借金のような負の財産であれ関係なくすべてそのまま相続することです。
簡単にいうと、相続する意思があると思われる行為です。
単純承認したとされる例
これに当たるのが、主にこちらです。
- 相続財産である預貯金を解約して使った
- 相続した家を売却した など
これらの行為は明らかに財産を相続した人にしかできない行為であるため、相続する意思があると認められる→単純承認と見なされ相続放棄ができなくなるというわけです。
相続財産のすべてもしくは一部の処分は、民法上の単純承認自由に該当します。
手元に相続財産を置いておきたい場合
相続放棄をすると、借金だけではなく、被相続人名義の財産(家や土地、車など)を手元に残しておくことはできなくなります。
相続財産を手元に残しておく必要があれば、相続放棄は選択肢から外れるといえるでしょう。
相続発生を知ってから手続きをせず、3か月の期限が経過した場合
人が亡くなって相続が開始すると、財産を受け継ぐ相続人は相続手続きをしなければいけません。
勘違い多き3か月ルールですが、結論からいうと3か月が経ってから相続手続きを始めても問題ありません。
相続手続きと3か月の関係について、多くの人が「相続手続きには3か月以内という期間制限がある」と勘違いする原因は民法第915条にこそあります。
相続放棄と単純承認の期限によるものですが、以下の条文をご覧ください。
民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
- 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
- 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
3か月とは熟慮期間
「カタい法律の文面だ」とお思いかもしれませんが、この3か月は熟慮期間と呼ばれ、相続人は被相続人の財産や借金を調べた上で相続の仕方を決めることが許されています。
もし3か月で調査し切れない場合などは、家裁に延長を申し立てることができます。
3か月という期間の理由
延長の手続きもせず3か月が経ってしまった場合、単純承認自由に該当し、相続人が単純承認をしたと自動的に見なされてしまうというわけです。
- 相続放棄とは
- 被相続人の相続を拒否すること(相続人になることを拒否すること)です。
相続放棄をするには自己に相続があったことを知ったときから、3か月以内に相続放棄の申述をしなければいけません。
これは相続放棄の効果が非常に大きいため、できるだけ早く相続関係を確定させる必要があるからです。
そして、3か月が経つと単純承認をしたと見なされます。
「3か月も放っておいたのであればそれは相続したものとされても仕方がないだろう」という法律上の考え方から来ているというわけです。
借金を一部でも返済した場合
相続放棄の手続き前や手続き中、相続した借金を一部でも返済してしまうと、単純承認したと見なされることがあります。
借金を相続するか、まず検討してから対処をどうするか決めた方がいいといえます。
借金の負担軽減方法
何らかの理由で借金の相続放棄ができない場合、相続する借金の返済負担を減らす必要があることも多いでしょう。
その際、選択肢となるのが単純承認や債務整理です。
限定承認
こんなケースが当てはまれば、限定承認で借金の返済義務の負担を減らすことが一つ選択肢になります。
- 「家業のための仕事道具を相続する必要がある」などで相続放棄ができない
- 単純承認に該当する行為をしていない
- 限定承認とは
- 相続で得たプラスの財産の分を限度とし、借金などマイナスの財産も相続する手続きです。(民法第922条)
相続はプラスの財産だけでなく負の財産も引き継ぐことになるため、多額の借金を背負いこむケースも生じます。
こうしたケースから相続人を守る方法の一つが、限定承認ということです。
債務整理
こんな場合、債務整理で返済額の負担を軽減できることがあります。
- 単純承認をしたことで多額の借金を背負うことになった
- 限定承認をしても借金の金額が大きかったりする
- 債務整理とは
- 借金問題について回ってくる言葉ですが、借金問題の正当な解決策で、任意整理、個人再生、自己破産などの方法があります。
任意整理
- 任意整理とは
- 借金の返済方法について債権者と直接交渉し、返済計画を見直す方法です。
相続した借金のこれから払う利息(将来利息)などをカットし、今よりも負担の少ない返済計画に調整できることがあります。
一般的に減額後の借金は、原則3年~5年程度で返済することを目指します。
ブラックリストのリスク
デメリットはいわゆる「ブラックリストに載る」状態になることです。
クレカの返済が滞った場合などにもこの状態になりますが、任意整理をすると残債の完済から5年程度、事故情報として金融機関の個人信用情報に登録された状態になります。
- クレカが使えなくなる
- ローンやキャッシングが組めなくなる
- 結果として、金額の大きな買い物がしづらくなってしまう
ブラックリスト(信用情報機関)に載る主な理由としては、金融業界でいうところの「事故情報の存在が確認されたとき」と言われています。
ブラックリストに登録されていると返済能力に不安があると見なされて発行してもらえません。
そうした申し込み履歴は他社も見ることができるため、ほかのクレジットカード会社にも審査落ちしたことを把握される可能性もあります。
ブラックリストに登録されている期間中は、余計な申し込みなどはしない方が賢明です。
対処法として、クレカの代わりに電子マネーやデビットカードを使うことで、やらないよりはいくらか不便は解消されます。
任意整理のメリット
こうしたデメリットがありますが、任意整理は交渉の対象にする債権者を選べるため、家や車のローン、連帯保証人のついた借金を対象外にし、影響を抑えられるメリットもあります。
債務整理の検討時、借金額が比較的大きくない場合や一定の収入がある場合、任意整理がもっとも選択しやすい方法になることもよくあります。
個人再生手続き
- 個人再生とは
- 裁判所に再生計画を申し立てて認可決定を受けることで大幅に借金の減額を図る方法です。
再生計画が認可されれば、借金を5分の1程度~10分の1程度(減額幅は債務残高や所有財産の価値により異なります)に減額した上、原則3年で分割返済ができることがあります。
借金を大幅に減額できれば相続した借金が多額であっても借金が返せるようになるケースもあるでしょう。
以下のような点もあり、任意整理よりもデメリットが大きい傾向にあります。
- 手続き後、5年~10年程度事故情報が信用情報機関に登録される(ブラックリストに載る)こと
- 国の広報誌である「官報」にも情報が載ること
- 保証人や連帯保証人がいる場合は影響が出ること など
自己破産手続き
- 自己破産手続きとは
- 借金問題でよく聞く言葉ですが、裁判所に返済不能であることを申し立て、借金を原則全額免責(免除)してもらう方法です。
借金が原則として全額免除となる自己破産のデメリットは大きいです。
- 手続き後、10年程度事故情報が信用情報機関に登録される(ブラックリストに載る期間が長い)
- こちらも前述の「官報」に載る
- 保証人や連帯保証人がいる場合は影響が出る
- 家や車など一定の価値をもつ財産は回収される
借金が返済不能と見なされない場合や、借金の理由が浪費やギャンブルなど免責不許自由に該当する場合、免責が認められないこともあります。
まとめ
相続後に「じつは借金があったとは・・・」と負の遺産が発覚しても、すぐに泣き寝入りはしないでください。
民事トラブルに強い弁護士と相談して速やかに着手し、トラブルを最小限に抑えて早期解決に臨みましょう。
今回のおさらい
- 借金の存在を知らなかったことに正当な理由があれば、返済を免れる可能性は十分ある
- 相続人だけで争おうとすると、むしろ自分たちに不利な判断が下されやすくなることも重々ある
- 相続関連の問題をいつまでも放置せず、早めに対応する
- 現在、無料の空き家現地調査を実施中!
- 空き家のご状況や相談者様のご意向に合わせて、最短即日~3営業日以内に適切な解決策や厳選した事業者をご紹介しています。